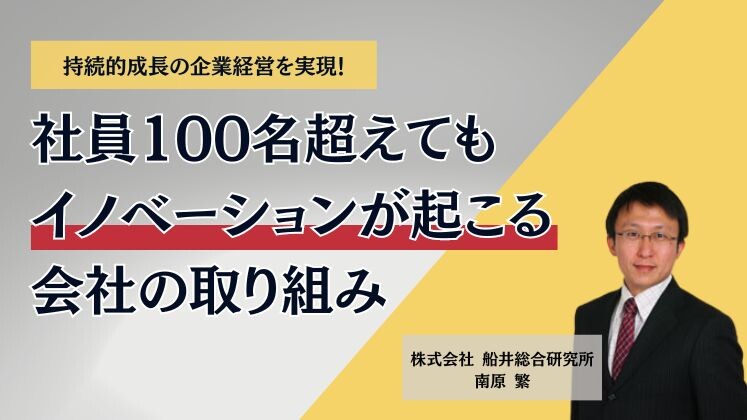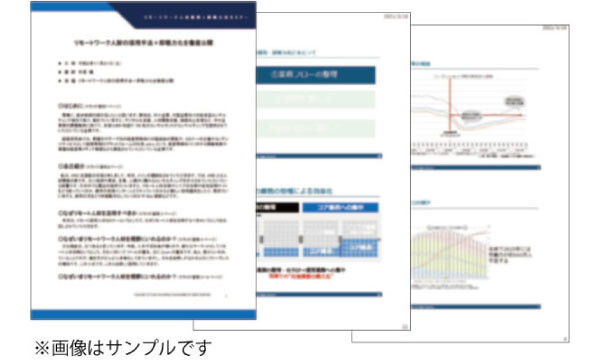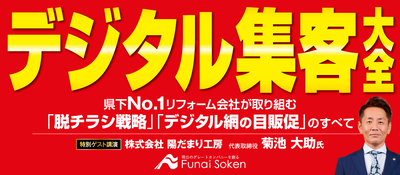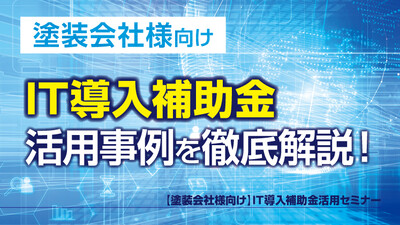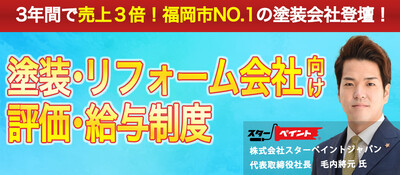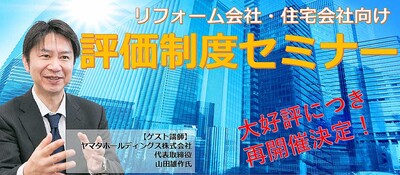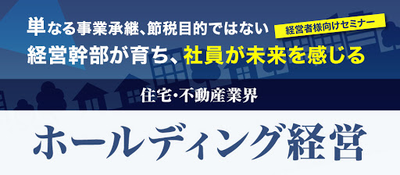はじめに

まず、本日お伝えしたいこととして、この3点になります。
100名超えてから横バイになってしまう会社とは、どういった特徴の会社なのか、どういった要因なのか、逆に100名超えてからも伸び続けている会社様というのは、どのような会社様なのか、どういった要因があるのか、そして今回のテーマである、そういった成長し続けている会社様の理念やミッション、ビジョン、バリューの頭文字を取って我々PMVVと呼んでおりますが、どういったものなのかということをお伝えさせていただきます。
まず、1点目です。100名超えてから横バイになってしまう会社の特徴についてお話させていただきます。
伸びている会社と伸びていない会社の違い、企業成長の要因の分析

船井総研は多くの会社様とのお付き合いがございまして、そのお付き合いしていく中や、また調査分析を数多くの会社様にさせていただく中で、左のA社様、右のB社様のような差が出てくるということを改めて感じました(講演録にて実際のスライドをご覧いただけます)。
左側のA社様は、従業員数がある程度のところまで成長をしてきていたのですけれども、それこそ50~100名ほどを超えてから横バイ、停滞をしていってしまう会社様です。ところが一方で、右のB社様のように、成長の踊り場なく持続的に成長をされている会社様もいらっしゃるなと感じました。

そこで、社員の状態を見てみますと、左側のA社様はやはり社員が成長していなかったり、何かタスクがあった時にやらされ感や疲弊感を感じてしまっている社員が多くいらっしゃるなというのを、外から見ていたり実際に聞かせていただく中で感じております。一方、右のB社様の社員の状態を見てみると、非常にモチベーションが高く、いわゆるトップダウンではなくボトムアップ型の組織となっている、社員の自発的な動きが増えている状態が起こっております。
それでは、この差の要因は一体何なのだろうかということを、我々、多くの会社様の業種業界問わず100社以上、伸びている企業様や成長が鈍化している企業様のヒアリングや調査分析をさせていただいて、様々な特徴の共通点があることに気付きました。
成長していた時には気づかなかった点

まず、成長していた時に気づかなかった点ということで、これまでであれば、いわゆる既存事業でのモデルが好調に推進していたり、人材が補充できるので、あるところまでは成長してきた会社様が多くいらっしゃいました。私もご支援をさせていただいている企業様やご支援し始めた企業様で、例えば自動車業界であると十数年ぐらい前から軽未使用車モデルでの推進がでてきていたり、住宅業界もローコストの商品が非常に好調になってきて伸び続けていたということがございましたが、あるところで、特にこれからは人口減少であったり、コロナはそろそろ落ち着いてきていますが、このような問題はやはりこれからもどこかのタイミングで起こるという時に、実は組織に限界が来ているのではないか。限界が来ている企業はやはり未来に向けて成長する姿がなかなか見えてこないというような声もございます。
ここは組織に限界が来ているという表現をさせていただいていますが、逆にこういった中で社員100名から横バイになってしまう7つの理由を分解して整理をさせていただいております。
成長が横バイになる7つの要因―①経営理念を掲げているだけではないか

本日参加されている皆様はこちら7つの要因のどこに当てはまっているかを見ていただきたいです。
1点目は、経営理念を掲げているだけではないか、ということでございます。

経営理念は、創業時もしくは代が変わってご自身が社長になられた時からの会社運営における目的・哲学である、というのが我々の中での一つの整理でございます。経営理念を掲げているだけでは、存在していない状態と同じです。あくまでも経営理念の目的は企業の的であることを念頭に置き、経営者や社員含め徹底して規定していくことで組織が強くなるというのは、多くの会社様を見てきた我々としても間違いなく言えることだと思います。もちろん やること・やらないことの、対処判断の基準にもなります。言うなれば憲法の心情のようなものが理念にあたります。
間違いなくそのような理念になっているか否かを、ご自身の出されている経営理念を確認していただきたいです。これが間違いなく経営者・社員の目指すべき的になります。
成長が横バイになる7つの要因―②経営戦略での軸となる使命とは何か

続いては、経営戦略での軸となる使命とは何か、ということです。
ここでは役割・ミッションと表現をさせていただいていますが、自社の事業を通して、地域、お客様、社員に何ができるのか、何を提供しているのか、何を与えているのかが明文化されているかどうかを、まずはここでチェックいただけたらと思います。そしてミッションという言葉として事業に当てはまる言葉を出しているだけになってしまっていないでしょうか。他にも、内発的動機のわくわくするミッションになっているかどうかがここから先は重要になってきます。外側からの見え方だけ大事にしたような理念やミッションであると、わくわくしないというのは間違いないと思います。私がご支援をさせていただいたり、実際にお付き合いをさせていただいている当初相談をいただいた時に、「この言葉あるのだけどなかなか浸透していないのだよね」と仰るので「この言葉はどうしてできたのですか」と聞くと、「サイトを少しリニューアルする時に言葉を整えたのです。外側から見える視点であったり、もしくはサイトの期限に合わせて急増で作りました」と仰っていました。「それは本当に心の底から思っていることですか」と伺うと、「いや、そんなこともない」ということもよく聞きます。自分自身の心の底から湧き上がる「これがやりたいんだ!」という理念になっているかどうかをチェックいただけたらと思います。

今お伝えしたのが内発的動機になります。心の底からこれがやりたい、わくわくする、自身が鼓舞されるような、そういった部分が内発的動機になります。一方で、比較して下の外発的動機、こちらはいわゆる給料、評価、地位などの他者と比較して他者から与えられて得られる部分が外発的動機になります。スライド資料には目の前にお金がぶら下がっているというイラストがあるのですけれども、これだとわくわくはしないと思います。一瞬のテンションにはなるかもしれないのですけれども長期的には続かないものが、外発的動機になります。
振り返りますと、内発的動機を持てる使命・役割がそもそもあるかどうか、そのような言葉になっているかどうかをチェックいただきたいと思います。
成長が横バイになる7つの要因―③ビジョンが無いとどうなるか

続いて3点目、ビジョンがないとどうなるか。ビジョンがあるかどうかを是非見直していただきたいです。
ビジョンは、ありたい姿です。理念・ミッションはとことん追求するものなのですけれども、それを逆算した時のありたい姿になっているかどうか、理念・ミッションと全く繋がりがない言葉になってしまっていないかを見直していただきたいです。
これはよくあることで、会社で「ビジョンうちありますよ」と言われ実際に見せていただくと、事業計画や数値計画になっていることが多くございます。数値だけですと、先ほどの外発的動機である外からの動機付けということでわくわくしないものになってしまいます。目標数値だけでやると、数字や期限に追われる毎日になってしまうこともあるので、定性で明文化されているビジョンになっているかどうかが非常に重要です。
今からの延長線上になってしまうとそれはそれでわくわくはしないので、今ではなく、未来・将来のありたい姿を明文化することが重要になってくるのが、3点目のビジョンになります。
成長が横バイになる7つの要因―④社員一体化が図れる・バリューがあるか

そして4点目です。社員一体化が図れるバリューがあるかどうかということです。
バリューというのは日常の判断軸、我々は別の言い方で接着剤と言ったりします。会社の理念・ミッション・ビジョンが重要ということはもちろん皆様ご承知の上で、社員の方もそこは判断されていると思うのですけれども、日常の一つ一つの行動で常に理念・ミッション・ビジョンを考えていますかというと、そんなことはないと思います。そうは言っても普段の目の前の業務に集中しなければならない、ということがあったりします。ただ、その中で少なくともバリューは、理念・ミッション・ビジョンに繋がる日常の判断軸として、これだけはやろう、これだけはやらないでおこうという明確な部分をどれだけ出しているかということが非常に重要です。これも「うちにはバリューがあるのですよ」と聞いて見せていただくと、細かいルール、お客様との対応の一つ一つの行動のチェック項目みたいになってしまっていたり、挨拶をしようなど、正直言って当たり前のことであり、本質的な言葉が列挙されていないということが多くございます。それとルールということで、同じく外発的動機が発露してしまう部分なので、そうではなくて、理念・ミッション・ビジョンを実現するためにこれをやればいいのだ、これをやると私たちの幸せに繋がるのだと思える、そういったバリューになっているかどうかもチェックいただきたいと思います。
ここは、しっかりと社員がそう思うかどうかということが非常に重要なので、社長がまるでルールを設定したかのような判断軸でありますと、社員の一体化、組織の一体化を崩してしまいます。
▼続きは下記からダウンロードいただけます。