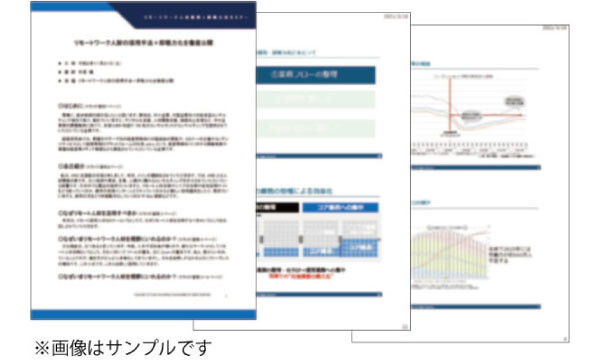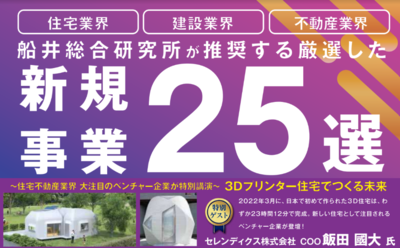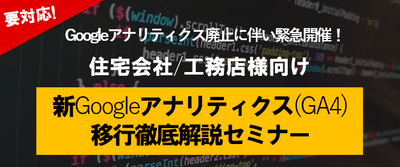はじめに
私からは第二講座として、新人営業の育成に成功している企業様の事例をご紹介していきたいと存じます。
私たちは、本日のゲスト企業様以外にも様々な企業様の育成に携わらせていただきながら、伸び悩む新人社員が活躍できる営業社員へと変貌していく姿を数多く見てまいりました。
ただし先ほど、ゲスト講師の酒井様(以下、酒井様と記載)の講座にもありましたように、「仕組み」が重要です。どの企業様もオリジナルの手法を取って育成を成功させているというわけではなく、実は新人社員の育成には、この手法を取れば、どんな企業でも、あるいはどんな新人社員でもしっかりと育つ、確立された仕組みが存在するのです。
つまり、先ほどの酒井様の取り組みも、育成成功の原則に則って取り組んできた事例の一つということになります。私たちが普段育成のサポートとして取り組んでいることを、酒井様にインストールしていったという背景があるのです。
改めて、酒井様の取り組みを振り返った上で、さらにその他の育成事例からより理解を深めていきたいと思います。
新人営業の育成に成功した取り組みの整理・分類
酒井様の取り組みを大きく整理すると、以下の八つになります。

まず一つ目として、「会社で二位だった」というお話がありましたが、酒井様の中で「日本一のチームを目指そう」という明確な目標設定があったのです。その目標に向かって、新人の方々もしっかり取り組んでいました。したがって、第一のポイントとして「目標設定」がありました。
また、「もっと頑張らないと」という抽象的な言葉ではなく、「今月の達成目標は二棟。そうであれば逆算していくと、この時期にこれを実行しないと間に合わない」という形で、数値ベースでの案件管理を行っていました。これも酒井様の重要な取り組みであったと考えられます。
そして、社内の共通言語として「競合対策をしなさい」と酒井様が指示した際に、取り組み方がそれぞれの社員によって異なってしまうというお話がありました。だからこそ、ルールをしっかりと共通言語として定め、「競合がいる場合は、社名を聞き、決めない理由を聞き、自社が候補に入っているかを確認する」という明確な手順を設けていました。
加えて、明確なルール決めとして、先ほどのスプレッドシートの例にもあったように、詳細なマニュアルを作成し、それに対してルールを一つ一つ全員で確認しているとのことでした。
また、フィードバックの内容をなるべく絞り込むというお話もありました。具体的には、酒井様の場合、「阻害要因に対応できているか」と「テストクロージングがあるか」という二点に絞ったとのことでした。
そして実際に、競合対策のトークスクリプトを作成したり、毎朝のロールプレイを徹底したり、商談音声をフィードバックしたりといった取り組みを実施してこられました。
これらの取り組みは大きく二つに分類することができます。青色の部分とピンク色の部分です。

青色の部分は、酒井様がおっしゃっていた「言い訳できない環境作り」という五点から成り立っています。そして、実際の行動アクションとして、三点を押さえていきました。これらを合わせて八つの要素に整理することができます。
ここで皆様にご注意いただきたいことがあります。例えば、自社に戻って「毎朝30分のロールプレイだけでも実施してみよう」と考えた場合、この行動アクションのみを実施するだけでは、どんな新人社員であっても成長できる仕組みにはなりません。やはり「言い訳できない環境作り」という土台があって初めて、行動アクションが若手に浸透していくのです。
つまり、酒井様の講座から学ぶべき点は、現代の若者たち(いわゆるZ世代と呼ばれる世代)の育成環境として、この五点をしっかりと押さえることが重要だということです。
先ほど「この手法を取れば、どんな企業でも、どんな新人社員でも育つ、確立された仕組み」を酒井様にインストールしたとお話しました。
酒井様が実施していた三つの行動アクション(競合対策のトーク作り、毎朝のロールプレイ、商談音声のフィードバック)は、私たちがお付き合いさせていただいている企業様が共通して徹底している取り組みでもあります。つまり、酒井様の行動アクションが、どんな会社でも新人社員が育つ仕組みの核心部分なのです。
では、なぜこの三つの行動アクションが仕組みとして機能するのでしょうか。それは、これら三点を実施しないと新人社員が成長しない要因、「新人社員の成長を阻害する三大不安」と呼ばれるものが存在するからです。
新人社員の成長を阻害する三大不安
新人社員の成長を阻害する三大不安とは、次の通りです。
1. 「他社と比較しているお客様への対応ができない」という不安
2. 「マニュアルや動画を整備したが、なかなか話せない」という不安
3. 「社内では話せるようになったが、実際の商談の場ではお客様との会話が深まらない」という不安
これらの不安を取り除くために、酒井様は「競合対策のトーク作り」「毎朝30分のロールプレイ」「商談音声のフィードバック」という三つの行動アクションを実施されたのです。
他企業への応用
酒井様の取り組みを他の企業に応用する場合、より抽象的な形で表現すると、
1. 新人社員のファーストステップとして、「他社と比較されても対応できるトークを用意する」
2. 「接客に立つ前段階として、話すべきトークを完璧に話せるようにする」
3. 「お客様の心配事をつかめるテクニックを身につける」
という三段階になります。ここで言う「お客様の心配事をつかめるテクニック」とは、酒井様が言われていた「テストクロージング」のことであり、「お客様の心配事」とは「阻害要因」を指します。
育成事例の紹介① - 他社と比較されても対応できるトークを用意する
今回は三つの育成ストーリーをご用意しております。まず一つ目として、「他社と比較されても対応できるトークを用意する」というステップ1の部分、女性社員お二人の成長ストーリーをご紹介します。
彼女たちの成長の推移を見ると、入社当初から輝かしい成績を上げていたわけではありません。一年目、二年目は思うような成績を上げられていませんでした。では、どのような育成のテコ入れをきっかけに急成長を遂げたのでしょうか。
彼女たちの扱っていた商品を簡単にご紹介しますと、注文住宅の中でも「自然素材」と呼ばれるカテゴリーの住宅を販売していました。通常であれば、競合を検討しているお客様への対応としては、自然素材の住宅がいかに優れているかを説明するアプローチを取るでしょう。
彼女たちもそのような説明を行っていましたが、特に「モミ」という木材を扱っていました。このモミの木には多くのメリットがあり、健康への効果、調湿効果、断熱効果、外観の美しさなど、自然素材の家を建てるメリットを一生懸命お客様に伝えていました。しかし、実際の商談ではお客様の反応が良くなく、成約に至らないという状況でした。
育成事例の紹介① - 課題:顧客ニーズとのミスマッチ
私も実際に商談音声を聴かせていただきましたが、確かにお客様の反応は良くありませんでした。なぜ彼女たちのメッセージが伝わっていなかったのでしょうか。

実際に契約に至ったお客様を分析してみると、アトピーやハウスダスト、花粉症など、健康に対する効果を重視するお客様が多いことがわかりました。つまり、お客様が気にしていない調湿性や断熱性、外観の美しさといった話をしてしまうことで、お客様の関心と矛盾するトークをしていたのです。これによって、営業トークの効果が減少していたと考えられます。
育成事例の紹介① - 改善策:トークの絞り込み
そこで、様々なメリットを総合的に伝えるのではなく、自然素材の効果の中でも特に「健康への効果」に絞ってお話をするようにしました。
このように、トークを絞り込む、つまり話す内容を精選することは、新人社員が競合他社と比較されている状況で営業トークを行う際に非常に重要です。多くの新人社員は、他社の商品と差別化するために、つい多くの情報をお客様に伝えようとしてしまう傾向があります。
このような場合、お客様の反応は大抵「なるほどね」という形で終わり、結果的に「良い話は聞けたような気がするが、よく分からない」という状態で終了してしまいます。そのため、アポイントメントが取れなかったり、競合他社に敗北したりするという状況が生じていたのです。
育成事例の紹介① - 課題:専門用語の壁
しかし、トークを絞り込み、多様な情報ではなく健康への効果に焦点を当てたとしても、それだけでは不十分でした。彼女たちは健康に対する効果に絞って話をしていましたが、その内容は「木の切り方を工夫している」「木の種類には杉やヒノキなどがある中でモミを使用している」「海外から仕入れている」といった説明でした。
このような説明を聞いたお客様はどう思うでしょうか。多くのお客様は家づくりの経験がないため、業界用語や専門用語を使用しても理解できないという問題がありました。
住宅会社の強みは大きく分類すると、デザインに特化した住宅、性能に特化した住宅、価格を抑えた住宅という三つのカテゴリーに分けられるでしょう。どの会社でも最初にトークの内容を確認させていただくと、ほとんどの場合、お客様がすぐに理解できない専門用語が含まれています。このような状況では、お客様が理解に苦しみ、一生懸命に効果を絞り込んで説明したとしても、十分な効果が得られません。
では、先述の女性社員二名は、健康への効果をお客様に分かりやすく伝えるために、どのような工夫を行ったのでしょうか。
▼続きは下記からダウンロードいただけます。