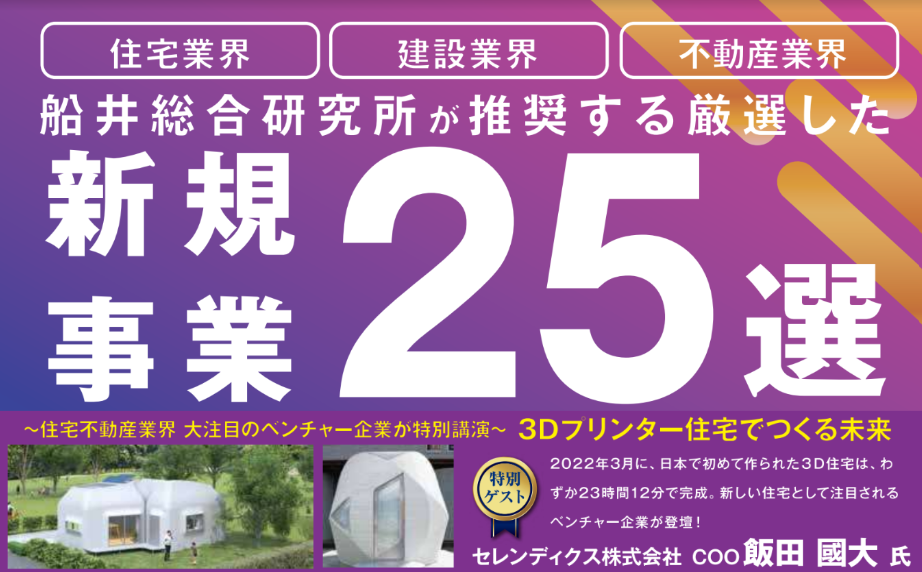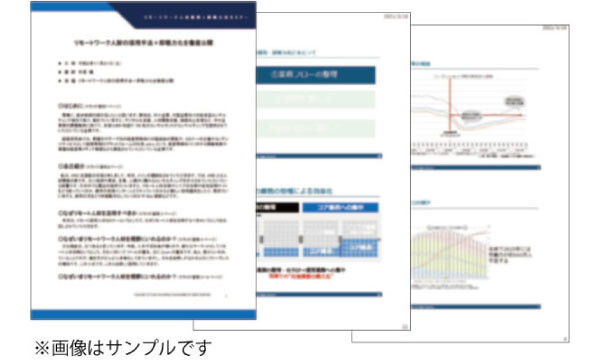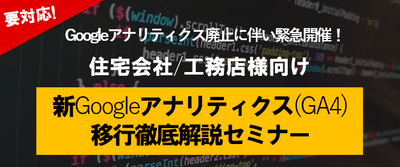2024年の住宅・不動産市場動向
私からは「新規事業で持続的成長×高収益化の実現」というテーマでお話しさせていただきます。構成としましては、住宅不動産業界の動向、今後の経営戦略、そして新規事業のビジネストレンドをお話しさせていただきます。
はじめに、住宅不動産業界の動向についてお話しさせていただきます。
2023年度の新設住宅着工数は81.9万戸となりました。これは10年前の2013年の98万戸と比較すると、約20万戸の減少となっています。近年の動向を見ますと、住宅着工数は2年近く継続して減少傾向にあります。特に注文住宅を示す持ち家数については、毎月5〜10%の減少率で推移しており、28ヶ月連続で前年実績を下回っている状況です。また、分譲住宅の一戸建てについても同様に5〜10%の減少率を示しており、住宅産業全体が構造的な不況に直面していると言えます。
現在の住宅業界における構造不況の主な要因は3つあります。第一に人口減少、第二に労働者人口の減少、そして第三に資材価格の高騰です。特に資材価格については、コロナ禍以前と比較して約1.2倍に上昇しており、これに伴い住宅価格も1.2〜1.3倍に値上がりせざるを得ない状況となっています。この価格上昇により購買力が低下し、潜在的な購入者が他の市場へ流出している状況です。このような構造不況への対応は、今後の経営者にとって重要な課題となっています。この構造的な変化を適切に理解し対応できなければ、5年後、10年後にはさらに経営が厳しくなることが予想されます。
2030年以降、新設住宅着工数は60万戸時代に突入すると予測されています。2024年度においても、すでに80万戸を割り込む可能性が指摘されており、この住宅市場の縮小傾向は長期化することが見込まれます。このような縮小マーケットにおいて、企業は市場環境の変化を見据えながら、持続可能な経営戦略を構築していく必要があります。
その中で、直近の業績についてまとめさせていただいております。
注文住宅・分譲住宅部門では、規模によって業績に差が見られます。大手企業は前年比105〜95%で推移し、売上高100億円規模の中堅企業は前年比100〜90%となっています。中小企業については前年比90〜80%と、やや厳しい状況が続いています。
一方、中古不動産流通市場は非常に好調です。大手の再販事業者は前年比110%の成長を維持しており、中小の再販事業者ではさらに高い前年比110〜130%の成長を記録しています。中古物件のリノベーション事業者も前年比110〜120%と、堅調な業績を示しています。
リフォーム市場も安定した成長を続けており、大手ハウスメーカーは前年比100〜105%、中小事業者は105〜115%の伸びを示しています。
建設事業市場については、住宅部門でやや弱さが見られるものの、全体としては堅調です。大手建設会社は前年比100〜110%を維持しており、特に商業施設、オフィスビル、物流倉庫などの非住宅部門で好調な実績を上げています。これらの市場動向を参考に、皆様におかれましても自社の経営戦略の見直しをご検討いただければと存じます。
住宅不動産業界は構造的な課題を抱えているとされていますが、実際には様々な成長市場やトレンドが見られます。主な成長分野についてご説明いたします。
セカンドハウス市場が特に注目を集めています。コンパクトハウスを中心に需要が拡大しており、これは日本で2番目に人口の多い団塊ジュニア世代(現在50代)からの需要が牽引しています。3Dプリンター住宅、コンテナハウス、トレーラーハウスなど、新しい形態のセカンドハウスも人気を集めています。一次取得市場は減少傾向にありますが、セカンドハウスを含む二次取得需要は着実に成長を続けています。
空き家関連ビジネスも成長分野の一つです。空き家の再生・活用、転貸、解体・リノベーションなど、様々なビジネスモデルが発展しています。
また、団塊ジュニア世代は今後の市場を考える上で重要なターゲットとなります。団塊世代(現在70~80歳)向け市場が一巡する中で、団塊ジュニア世代とその周辺層へのアプローチが経営戦略の鍵となってきます。
インバウンド関連市場も拡大しており、外国人向けの不動産販売や民泊・貸別荘などが好調です。
不動産投資も重要なトレンドです。事業収益に加えて、投資による収益確保の重要性が増しています。コロナ禍の経験から、人的リソースに依存しない収益源の確保が事業の安定性に重要だということが明確になりました。社員の活動が制限される状況下でも、不動産収益や投資収益により安定した収益を確保できる事業ポートフォリオの構築が求められています。
これらの成長トレンドを踏まえ、各社の状況に応じた最適な事業ポートフォリオの構築をご検討いただければと存じます。
中小・中堅企業の持続的2ケタ成長する戦略

中小・中堅企業が持続的な成長を実現するためには、大きく二つの要素が重要となります。一つは時流への適応力、すなわち成長市場を見極め、そこへ適切にマーケットインしていく能力です。もう一つは事業の多角化(コングロマリット化)です。現在の市場環境では、単一事業による継続的な成長は極めて困難になってきています。
従来の収益基盤であった住宅や新築部門は、先ほどの統計データが示すように、年間5〜10%の市場縮小が続いています。この市場縮小は避けられない現実です。政府による少子化対策が強化されたとしても、出生率の大幅な改善がない限り、市場の拡大は期待できません。この状況は10年後、20年後も続くと予想され、その改善には100年単位の時間が必要となるでしょう。
このような時代において、企業が持続的な成長を実現し、生き残っていくためには、事業の多角化が不可欠です。各企業は自社の強みを活かしながら、新たな事業分野への展開を検討し、バランスの取れた事業ポートフォリオを構築していく必要があります。これが、これからの経営者が直面する重要な経営課題となります。
地域コングロマリット企業の特徴

地域コングロマリット化を目指す企業の特徴と今後の方向性についてご説明いたします。
典型的な地域の新築住宅のトップ企業は、現在、売上高20億円、営業利益率5%程度で事業を展開しています。しかし、市場の構造的な縮小が加速する中で、これまでと同じような経営手法では、将来的な業績の維持が困難になってきています。
このような状況下で重要となるのは、本業がまだ収益を生み出している段階で、その収益力を活かして新規事業への投資を進めることです。本業を担保として、将来の収益の柱となる事業への投資を行うことが、経営者としての重要な判断となります。
過去にも産業構造の変化により、業種の縮小や転換を迫られた例は数多くあります。例えば、昭和20〜30年代に存在した石炭販売業者は、時代の変化とともに石油販売や住宅事業など、新たな分野へと事業を転換することで生き残ってきました。現在の住宅・不動産業界も、同様の転換期を迎えていると理解する必要があります。
新規事業展開においては、まずは本業と関連性の高い分野、特に先ほど触れた不動産業界の成長トレンドに沿った市場を探ることが賢明です。その際、最初から自社で一から事業を立ち上げるのではなく、フランチャイズシステムやその事業ソリューションを活用することで、より確実な成功への道筋を描くことができます。
新規事業開発において、一から自社で事業を立ち上げることは成功率が極めて低いのが現実です。そのため、既に成功事例のある事業モデルやフランチャイズシステムを活用し、成功確率を高めていくことが重要となります。成長市場のトレンドを個社で正確に把握することは困難なため、フランチャイズやこのようなイベントへの参加を通じて、適切な新規事業を選択していく時代になってきています。
コングロマリット型の事業ポートフォリオを構築する際、既存事業については現状維持や数%の成長で十分ですが、新規事業については二桁成長を目指し、最低でも営業利益率◯%以上を確保できるビジネ…
▼続きは下記からダウンロードいただけます。