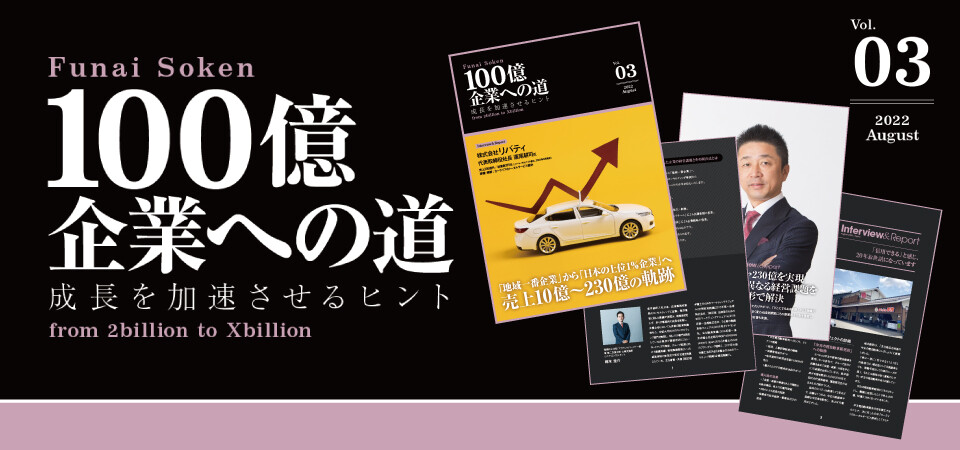トラックへの18億円投資の秘密
橋本:
船井財団主催『グレートカンパニーアワード 2015』においてユニークビジネスモデル賞を受賞された富士運輸株式会社 松岡弘晃社長にお話しを伺います。受賞後、社内の様子に変化はありましたか?
松岡社長:
はい。今まで賞をいただくようなことがない会社でしたので(笑)従業員も皆、喜んでくれました。
橋本:
こういった受賞は初めてでいらっしゃいますか?それは意外です。
松岡社長:
トラックの購入台数などで感謝状をいただいたくことはあっても、こういったかたちでの表彰は初めてです。今回、従業員とお客様への感謝の意味を込めて、各地でお礼パーティーを3回、開かせていただきました。今回の受賞について、不思議に思うお客様もいたようです。どのように面白いのか、何がユニークなのかという問い合わせをいくつかいただきました。中には「どんなことでこの賞をもらったのか、何をしているのか、具体的に教えてほしい」といって来られる大手運送事業者さんなどもおられましたね。あとは、やはりいろいろなメディアに掲載されたことで入社希望者が増えて、今、面接の数もかなり多いです。

<グレートカンパニーアワード2015> ユニークビジネスモデル賞受賞
マルチに対応できる大型車を開発
橋本:
富士運輸さんのユニークなところはたくさんありますが、一番は、やはり車両の管理のうまさではないかと思います。通常なら、お客様の仕事にあわせて車を作って、それごとに車の仕様を変えて要望どおりに作っていくわけですけど、富士運輸さんはいろいろなニーズに対応できる車をメーカーと一緒に開発して、それを大量発注することによってコストを抑えています。さらにその整備力を上げることによって、良い状態で、早い段階で売っていくと。セールバリューも考えながら車を買っていくという、かなり面白いモデルですね。
松岡社長:
そうですね。私は元々、三菱ふそうで働いていました。そこでまず一番感じたのが、日本のトラックの車種の多さです。なぜこれだけ車種が多いかというと、高度経済成長の時に、メーカーはさまざまな運送会社、荷主、倉庫会社の要望に応えて多くの車種を作りました。それは床が高いとか、タイヤが小さいとか、タイヤの数が多いとか、もうキリがないくらいの多さです。ひとつのメーカーでも何百、ともすれば何千という車種があります。そんなにも、なぜ必要なのかとずっと思っていました。
実際にトラックを使って商売する側になったときに、父は大手運送会社の下請けをずっとやっていたんですけど、やはり仕事がなくなったり、「おたくのトラックはいらないよ」と言われたり、そのトラックが使い物にならなくなるということを、私は専務時代に経験しました。このままお客様が喜ぶトラックを作り続けても、結局はそのお客様に「必要ない」と言われたら、もう終わりなんです。そこで、複数社のお客様の荷物が詰める車を作ろうと、約10年前からそういった車の発注に切り替えていきました。単純な話なんですけど、そこになかなか気づかなかったんです。
橋本:
なるほど。
松岡社長:
どのメーカーもマルチの対応ができる車というのは発売していません。ですからメーカーさんと相談して、また、トラックの上に載っているボディーメーカーとも相談しながら、さまざまなお客様の要望に沿うマルチの車をどんどん作りました。
とはいうものの、やはり運んでいくらという運送会社ですので、仕事がなければ従業員に満足な給料は払えません。けれどマルチの車だったら仕事が途切れることがなくなるので、そこから会社の業績もどんどん良くなってきました。
しかし、マルチの車は値段が高い。それと、かなり多くの機能をつけないとマルチ管理ができない。そんなこともあって、1台、2台の発注ではコストが下がらないんです。だから初めてスーパーマルチという車を発注するときに、大型車を100台発注しました。100台というと総額で19億とかになるんですけど、とにかくここで発注していかないと今後の波動に耐えられないなと、そう思い切って決断したのが、ちょうどリーマンショックの時です。
橋本:
そうでしたか。整備力の強化については、その当初から戦略的にされていたんでしょうか。
松岡社長:
そうですね。私も1年間ですがトラックの整備をやっていましたので、これからは整備を自社化しないと、日本のトラックメーカーやディーラーの持つ整備工場の整備士が不足する、整備能力が衰えて修理ができない、そんなことになるのでは?と予想していました。トラックの整備というのは職人さんが多くて、職人さんの勘といいますか、トラックのエンジンの音で何が悪いとか、そうして判断されていたんですけど、もうそんな職人さんがどんどんいなくなると。じゃあこれ10年後には、必ずトラックの整備は困るだろうなと思って、全て自社化しようとしたのが整備工場を作るスタートでした。
では実際はどうなっているかというと、今、日本のトラックリーダーの整備工場に修理に持っていっても3~4日、もしくは1週間放置されるということが起こってきています。
リセールバリューを考えて投資
橋本:
もうひとつ、本当にユニークだなと思うのは、トラックをダメになるまで使って廃車にするのではなく、リセールバリューを考えて、売ること前提に買って回されているじゃないですか。こういう発想って、他にはないなと思うんです。
松岡社長:
トラックや設備を買うときに、3年後、5年後、10年後に、例えば会社の業績が悪くなって、この機械を手放さなければいけないというシーンで、本当に高く売れるものなのか、鉄くずになってしまうのか、そういったところまで考えて投資している経営者は、意外と少ないんですよね。
皆さん目先の仕事や、荷物を運ぶためにとトラックを買って使う。ところが、お客様から要らないとか言われたときに、またはその法律が変わったときに、規制が変わったときに、この車では使えないということが実際に起こっています。ですから先の事を予測して、5年後10年後に高く売れる、そんな車を作れば、まあ一つの投資にもなりますよね。
私の個人的な考えになりますけど、オートマチックのトラックは買わない、できるだけ環境対策ができている車にする、できるだけたくさんの容積が積める車にする、こういったことです。具体的に言えば、オートマチックの車はディーラーやメーカーじゃないと修理ができないんです。もう囲い込みされてるわけなんです。だからまず買わないというのと、環境対策がしっかりできている、例えばドライバーさんが仕事をしやすい、オートエアコンが付いている、仮眠ベッドが広いとか、働く人のためのことを考えて作っている車というのは、やはり中古車市場でもとても人気があるんです。
橋本:
環境対策は、やはり『自動車NOx・PM法』とかで、そのエリアが広がってきたときに使えないエリアが増えてきたら困るからという部分もあってということですね。
松岡社長:
それもありますね。労働環境と、やはり国内の環境ですよね。あとは、できるだけたくさんの荷物が積めるトラックを買うということがポイントです。1回あたりに運ぶ量が多いほどお客様も喜ばれますよね。ところが運送会社っていうのは、たくさんのトラックを使ってほしいから、1回で大量に運べるトラックを買いたがらないんですよね。
橋本:
あぁ、なるほど。
松岡社長:
ですから一般的な車しか買わない。そこで私どもはとにかく1回で大量に運べる、箱が大きいトラックを買う。そうすることによって、3年後、5年後、売却しようといったときに高く売れるということです。
橋本:
松岡社長は将来的なリスクなどを、わりと前倒しで考えていらっしゃるんですか?
松岡社長:
そうですね。とにかく厳しい状態から経営始めましたので、例えば営業所を作ったときに、閉鎖するときどうなるんだろうとか。厳しくなったときに、いかにその変化に対応できるかを考えて、リセールバリューが高くなる車を必然的に選んでますね。
橋本:
19億円なんていったらすごい投資ですし、もうガンガン行くわ!というイメージがあるんですが、リスクヘッジの視点ももちろんしっかり考えていらっしゃるということですよね。
松岡社長:
これはまぁ交渉次第ですけど、トラックは大量に買った方が逆にリスクがない、ということもありますしね。

「スーパーマルチトラック」顧客ニーズをすべて網羅した、安全性の高いトラック
スーパーマルチトラック開発のきっかけ
橋本:
松岡社長はイギリスのウェールズ大学に行かれて、御社のビジネスモデルを卒論のテーマにされたとお伺いしました。どのような視点でまとめられたのでしょうか。
松岡社長:
何かを研究をして修士論文にするなら、この業界のことを研究して、実務に役立てるのがいいだろうと思いました。いろいろな文献を読みましたが、日本国内では運送業に関する論文や研究は、ほとんどないんですよ。宅急便を開発した当時、ヤマト運輸の小倉昌男社長が参考にされたという神奈川大学の中田教授の話や本も拝読しましたが、やはり今の時代にはマッチしにくいところもありました。
そして、日本の運送業界で一番素晴らしいイノベーションとは何かな?と考えてみると、やっぱりクロネコヤマトなんです。徹底的なマーケティングリサーチがすごい。それと、トヨタ自動車と共同開発したトラックです。クロネコヤマトのトラックは荷物を配達するときは助手席側から側道に降りられるようにしてあるんです。運転席から降りると後続車と事故になる危険性があるからですよね。それと3つ目が業態化です。
家に荷物が届く「宅急便」ですよね。これらが本当に刺激になって、とにかくこれに変わるような何かを考えて、それを修士論文にしようと思いました。
橋本:
なるほど。
松岡社長:
その当時、マーケティングリサーチデータをいろいろ見たんですけど、あまりニーズが掴めてないなと思いまして。会社の方でちょっとお金をかけて、日本の物流業界やメーカーはどんなトラックが必要なのか、喜ばれるかをマーケティングリサーチしました。それらを全てまとめて、海外の運送会社のいろいろなビジネスモデルを参考にして生まれた車が、日野自動車と共同開発した『スーパーマルチトラック』なんです。
橋本:
そこにつながっているんですね。
ITへの投資と活用
橋本:
先ほど、物流業界はこれまでイノベーションがなかなか起こっていないという話が出ました。富士運輸の先進的なところは、運送業界の中でも特にITに力を入れていて、しかも自社開発というところではないでしょうか。
松岡社長:
荷物の動きをお客様に見せるというようなIT投資は、やはりヤマト運輸が一番得意だったんです。そういうところも運送業界は全くできていないので、このビジネスモデルは参考になりました。まずお客様が運送会社に荷物の輸送依頼をした時に、何が知りたいかということですよね。今どこにいて何時に着くのか。どんなトラックで運んでくれているのか。それを全てシステムで明確にお客様に答えられるようにというのを、約10年前にスタートしました。
橋本:
たしかに倉庫業界や物流センターなどはITが進んでいましたけど、運送業界はそこまでではなかった印象があります。
松岡社長:
10年前にそこまで公開している会社はなかったこともあって、経済産業省からITの推進、推奨企業として表彰されたんですけど、やはり運送会社というのは中小企業が多いので、IT投資にお金をかけづらいんです。市販のソフトを買って導入するといっても、限界がある。だから当社は全て自社開発で、徹底してやってきました。さらに今年、もっとすごい仕組みができまして、全車輌の位置をお客様がGPSで見られるんです。来年は、どのドライバーさんがこのお客様の荷物を運んでいて…というとこまで見られるようにしようと思っています。最終的には、どのトラックがあいているのか、それを日本地図の上にピンを立てて、その車を使っていただくと。できる限り無駄な走りはしない、そういうことを徹底してIT戦略で差別化を図っていきたいと思っています。
橋本:
昔はホテルの空室も全然わからなかったですけど、今では簡単に見えるようになりましたね。ちょっと予約しようかな?みたいなことが物流業界でできるようになるわけですね。
松岡社長:
橋本さん、まさにそれなんです。ホテルは今日空室になったら、その空室は二度と埋まらないですよね。トラックも同じです。今日、空車だったら、もうそれで終わりなんです。だからとにかく車を遊ばせない。ではそれが何に効果があるのというと、最終的には働いている人の給料なんですよね。できる限り労働生産性を上げて、働いている人に沢山の給料を払える、それが最終目的です。ITを導入する前、当社の空車率は33%だったんです。3年前にIT投資をして17%まで下がりました。2年前に16%、今年は15%まで下がりました。
橋本:
毎年1%ずつでも下がってきているって、すごいことですね。
松岡社長:
この1%って、すごい距離なんですよ。たった1%?と思うかもしれませんが、地球を何週も往復するくらいの相当な距離なんです。これはトラックの台数が増えれば増えるほど、密に走れて、無駄がなくなる。だからトラックを現在の倍まで増やして、もっと空車率を下げて、給料として還元できるようにしようと思ってます。
橋本:
お客様も、空車状況を見ながら運送を依頼できるという部分もありますね。
松岡社長:
そうです。朝に出すよりも、夕方に出す方が、この空車を使えるとか。半分積めるだけトラックがあいているので急ぎの分だけ出しておこうだとか。今までは急ぎの荷物は電話で交渉していたところが、IT化することでお客様に選んでもらえるようになるわけです。1回あたり大量に運んでもらって、単価あたりの輸送コストを下げてもらう。動かすときは一括で効率よくというのをお客さんに提案しています。
管理職は自薦制度
橋本:
では次に、採用と人材育成についてお聞きします。私が出会った2011年当初、650台くらいの保有台数だったと記憶しています。その後4年で1000台を越えて、拠点も増やしていらっしゃいます。そうなってくると、人材育成が追いつくのかという問題が出てきますよね。所長やドライバー採用の秘密があれば教えてください。
松岡社長:
特に秘密はないんですが(笑)管理職になる能力のある人がいないとかよく聞きますけど、それは結局やらせていないからであって、できるんですよ。うちでは、誰か所長やりたい人いませんか?と言うとね、結構いるんですよ。それは学歴とか年齢、性別、全く関係ないです。規模を拡大するときに僕は、やはり理職が不足して困った時期がありました。そこで1人で困っているんじゃなくて、皆に聞いて、やりたい人はいないか?と手を挙げてもらったんです。
橋本:
そこがすごいですね。現場系の業種の会社では、管理職になりたくないという人が多いといわれていますから。
松岡社長:
違うんですよ。管理職になってほしい人材って、大体、社長がこいつを管理職にしたいとか一方的に思っているものなんです。だから社長がやりたいか?と聞くと、やりたくないと言われるんであって、やりたいやつ!って言ったらね、おるんですよ。
橋本:
なるほど。
松岡社長:
当社では、管理職になりたい人は立候補しなさいと言うと、どんどん手が挙がります。最近では入社すると1年2年はドライバーで走りますけど、2年経ったら管理職になりたいって、そんな夢をもった人が来てくれています。
橋本:
それを狙って入ってくるということですね。
松岡社長:
はい。早い人でしたらドライバー入って、半年で内勤になって運行管理、それから2年後に支店長と。そうなっている人も実際いますね。
橋本:
そういう意味では手を挙げさせる風土をつくるというか、そういうことが重要ということでしょうか。
松岡社長:
そうです。あまり経験がなくて20代前半であれば、もう少し経験してから…ということもありますけど、30歳を超えていればある程度は経験していますし。実は、僕が31歳で社長になった時、「あいつが社長になったら潰れる」とか、「あいつが社長になったら社員が辞めて誰もついてこない」と散々言われたんです。その時に自分が思ったのは、勉強しながらとにかく一所懸命やっていれば、人もついてきてくれるんだなということです。ですから自分も経験しているというのもあって、30超えたら支店長くらいできるだろうと思ってますし、やってもらっていますね。
橋本:
その立候補制は、社内公募するのですか?
松岡社長:
はい。毎日全員にメールでニュースのようなものを送っていて、そこで新しい支店ができるよと。運行管理者を募集してるので、立候補したい人は1週間以内に総務の○○さんに立候補してください、あらためて面接します、そんな感じですね。

管理職に立候補するドライバーが育つ環境
ドライバーが集まる理由
橋本:
運送業界はドライバー不足だと言われている中、富士運輸にドライバーが集まる理由は、なんでしょうか。
松岡社長:
まず、運送業界には長時間労働、低賃金、家に帰れないとか、そんなイメージがありますよね。そのためには、まずは長時間労働をなくして、できるだけ労働基準法の範囲内でおさめる。まずそれをしています。最近は、家に帰らず長距離を走りに走って稼ぎたいという人がいなくなってきたんですよね。だから3日は長距離で出るけど4日目には帰れるとか、そういったきっちりしたシフトができているというところが1つでしょうか。
そして、安全な機能がついた新しいトラックにどんどん入れ替えていることでしょうか。当社はトラックの事故や怪我がまだゼロなんです。それと、語弊あるかもわからないですが、態度の悪い社員がいないので、真面目な社員が集まる会社というイメージで、結構いい社員が来てくれています。今でしたら3人に1人が大卒で、家庭もあって、プライベートも大事にする、そんな人材が多いですね。
橋本:
そういえば、最終面接は社長がされているんですよね。全国から奈良の本社に呼んで最終面接をされていると聞いて、僕は本当に驚いたんです。
松岡社長:
橋本さん、それ本当に大事なところです。社長が自分の会社の従業員の顔も知らない、名前も知らない、会ったこともない。これは絶対ダメですよ。僕は必ず全員に会って、最低20分、長くて1時間くらい話をするんです。その話の中身っていうのは、ドライバーとしてではなくて、将来何がしたいのかとか、会社に入って目標を持って欲しいとか、家族構成とかね。今ハローワークでは聞いてはいけない項目がいろいろあるんですね。でもまぁ僕は全部聞きます(笑)!聞いてはいけないことって、だいだい聞きたいことなんですよ。もうとにかく深く深く聞いて、全部メモします。
将来的にその人が3年後4年後に、当社のどこかの支店で支店長になっているかもしれないですよね。でもその人と会っていなかったら、どんな人かわからないです。やはり少しでも話していると印象に残りますし。
最近、面接した子には「社長、僕まだこんなに若いですけど、支店長目指して頑張りますので握手してください!」と言われました。この会社に入ったら社長と会って話しができる、社長に直接いろんなことを言える、やっぱりそういうのが喜ばれているのかなと思いますね。
橋本:
そこにつながっているんですね。
何かあれば社長に電話を
橋本:
そうすると、営業所を回った時もドライバーの皆さんとお話しされたりも?
松岡社長:
そうですね。しますし、基本的に私の携帯番号は従業員に渡しているので、携帯に私の番号が入っていますから、どんな用事でも、苦情でも、遠慮なく私の携帯に電話しなさいと言っています。
橋本:
それは全従業員、全ドライバーから直接の電話もありと。
松岡社長:
ありあり。もう、ぜんぜんありです。
橋本:
実際かかってくることはあるんですか?
松岡社長:
日に1件2件はかかってきますよ。
橋本:
そうですか!
松岡社長:
これって大事な話でね、例えば配達に行った時に、いつもお世話になってここの会社、いつもと動きがおかしいとか。なんか新しい工場を建ててまた出荷をするみたいだとか、もうドライバーさんでなければ知りえない…
橋本:
営業情報ですね。
松岡社長:
そう。どうも今入っている運送会社が倒産しそうだとか、そんな情報をくれるんです。情報をくれた瞬間に必ず動きますので、やっぱり生の現場情報はすごく大事です。倒産情報って倒産したら1週間くらい経たないとわからないですから。ドライバーさんのおかげで大きな仕事が取れたとか、そういうことも本当に多いですね。
得意なところに磨きをかける
橋本:
富士運輸は破竹の勢いで業績を伸ばされてきましたが、その軌跡というか流れを教えていただけますか?
松岡社長:
はい。僕が31歳で社長に就任したときは、まだ7人しか拠点がなかったんです。自分が社長になって奈良県の市場でお客様に営業して仕事をすると、地元の顔見知りの運送会社から「仕事を取られた」とか「営業に来やがって何してくれんねん」というようなことを言われていました。これ以上奈良県で戦って売上を伸ばすよりも、名古屋や東京に出て行こうということで、ちょうど私が社長になる年に名古屋に出しました。名古屋では、しがらみがまったくない、知り合いもいない、大企業がたくさんある。どんどん営業に行って、運送会社で荷物運ばせてくださいと言うと、新しい仕事をどんどんいただけたんです。これは面白いと。だからとにかく企業に飛び込みに行って話を聞いてもらいました。そこから、とにかく新規開拓を自らするようになりました。名古屋のあと、すぐに東京、成田と開拓したんですけど、もうとにかく新規訪問でしたね。大企業であろうが航空会社であろうが直接アポイントを取ってどんどん行って。するとね、意外と会ってくれるんですよ。
橋本:
社長自ら行かれるんですか?
松岡社長:
はい。私が社長の名刺を持って、奈良の運送会社ですと。東京にトラックを走らせて来たんですが、帰る荷物がなくて困っていますとストレートに言ったんです。そんなに君、困っているのかと。一回、話だけならいいよと。そこからだんだん仲良くなって、2回3回会っているうちに仕事をくれるようになるんですよね。
橋本:
そうだったんですね。
松岡社長:
関西の運送会社が東京まで営業に行くのは、意外と少ないんですよ。ここのお客様はこの運送会社で決まっているから仕事は取れないだろうと、だいたい皆さん思うことなのですが、何年も使っている運送会社に不満を持っているお客様は実は多いので、逆に、結構、歓迎されるんですよ。とにかく大手のメーカー、運送会社にも、どんどん飛び込みました。それが現在も当社のメインの荷主さんになっているんです。
橋本:
当初の台数からぐんぐん伸ばして、拠点も今30以上ありますもんね。成長の過程でアグレッシブに攻められたわけですけど、社長の考え方ですごいなと思ったのが、「やらないことを明確に決める」ということです。それだけアグレッシブにされていても、これとこれはやらないと決めている。その考え方を教えていただきたいです。
松岡社長:
はい。運送会社は意外と、「こんな荷物を運んでください」と言われると、それに合わせるようにトラックを買いたがるんです。そうやっていろいろな車を増やすほうがいいのかというと、特殊な車をたくさん持つことによって逆に効率が悪くなるんですよね。昔、父親がやっている頃に、平ボデーも、2トンの小さな車も、4トンのクレーン付きの車もありました。しかしよく見てみれば、月に半分しか動かないとか、稼動が非常に悪いんですよね。ですから今までやっていた2トン車とか、当時やっていた4トンの冷凍車も全部やめました。当社の戦略は、ウイング車でドライの貨物4トンと10トン、これでいこう。そして長距離に特化すると。
先ほど話したヤマト運輸の例ですが、宅急便の開発に何を参考にしたかっていうと、実は吉野家の牛丼だそうなんです。吉野家に入った時に、ここのお店は牛丼しか売っていないのに、なんでこんなに売れてるのかと。それは牛丼に絞っているからです。当社も大型4トン10トンの長距離一品勝負でいくと、それが実はよかったんですよね。余計なこと、不得意なことはしない。得意なところを徹底的に磨きをかけると。そういうのも自分が社長になった時に始めたというのが、結果的に良かったですね。
いい会社とは?
橋本:
以前、2030年には2000台体制を目指すとおっしゃっていました。今の勢いですと、もっと早く達成するのではないかと思います。今後の展開や課題、克服したいことなどあれば教えてください。
松岡社長:
今現在、当社の規模はグループで1000台、売上で170億ですけれど、日本の物流業界の市場規模は18兆円あるんです。ということは、まだ1000倍以上ありますし、まだまだニーズがあります。その中で大型トラックは国内でどんどん減っている。これは中小の運送会社が衰退している、大手運送会社がトラックを持たない、そういった理由からですが、だから大型トラックが必ず足らなくなる。そういうマーケットで伸ばしていこうと思っています。
今は大型トラック約900台ですが、2030年には2000台にして、もっと労働効率を上げて、それをITで管理できて、なおかつ労働基準法がきちっと守れる、法律を守って輸送ができる、そんな会社づくりをしたいです。トラックの数が増えれば増えるほど、お客様は本当に増えてくるんですよ、不思議なことに。もう少し拡大しようかなと思っています。
橋本:
ありがとうございます。とても参考になるお話が多かったと思います。
最後に、これをお聞きしたいと思います。松岡社長の考える「いい会社の条件」は、何でしょうか。
松岡社長:
僕ね、社員によく「いい会社ってどんな会社だと思う?」って質問するんですけど、給料が高くて安定していて休みが多くて…という人が結構いるんですよね。君ら、そんな給料高くても、いつまでももたないよと。休みが多かったら、もっと一生懸命働く、働き者が揃っている会社がもっと勝つよと。
本当にいい会社って何かっていうと、強い会社だと思うんです。生き残れる会社。競合他社に負けないということですね。厳しい話ですけど、やっぱり勝ち残らないと、ダントツ一位にならないと、徹底的に磨きをかけてその業界で1位にならないと、残れない。そうやって生き残る会社って、本当にいい会社なんですよね。そのためには一番にならないといけない。一番になる、規模を拡大する、スケールメリットが出る規模にする、これを達成すれば、これがいい会社だと。僕は思いますね。
橋本:
なるほど。わかりました。とても参考になりました。今日はありがとうございました。

社長の携帯番号を伝えるなど社員との距離が近く、何でも話せる職場環境
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度