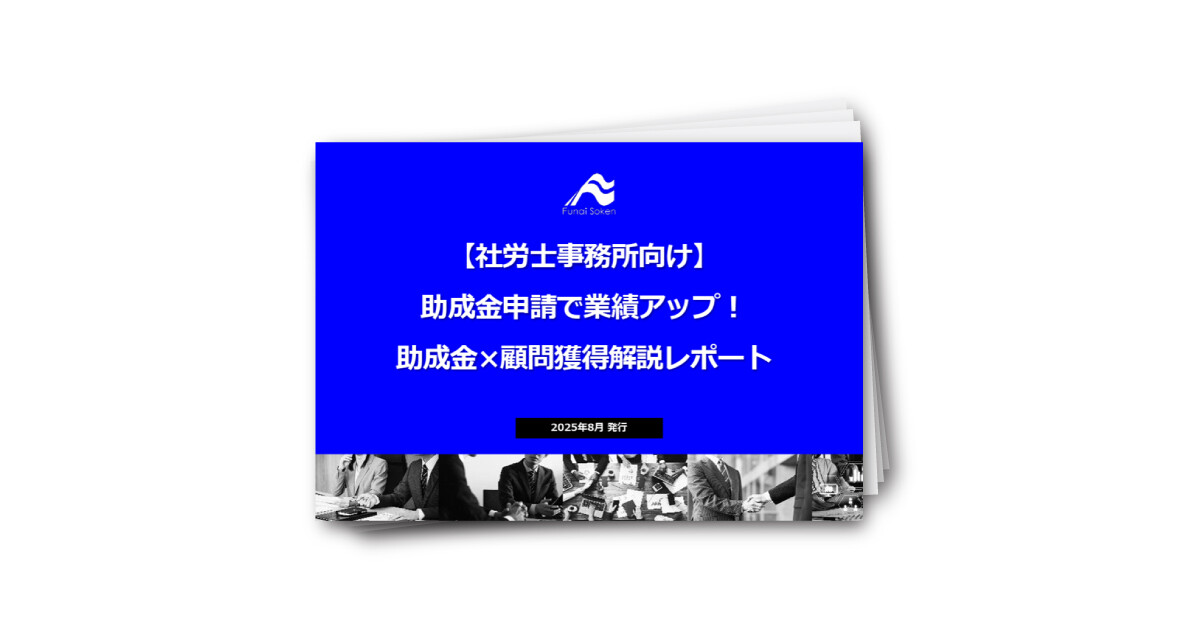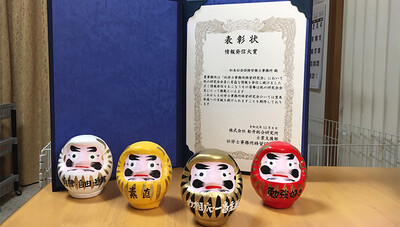大規模事務所向け助成金取り組み方針|リスク回避・組織体制の強化

概要
社労士業界は今、重大な転換期にあります。
登録者数や法人数は増加を続ける一方、顧客となりうる企業数は減少傾向にあり、需給バランスは崩れつつあります。
この構造的な変化は事務所間の競争を激化させ、価格競争から脱却し、独自の価値で選ばれることが、生き残りのための絶対条件となったことを意味します。

この厳しい状況を打破する明確な突破口が、実は存在します。それが「助成金」業務です。
見過ごされがちですが、全国の社労士事務所の半数以上(約54%)が、この助成金業務に未着手のままです。
これは、ライバルがまだ気づいていない巨大な市場が手つかずで残されていることに他なりません。
この分野に専門特化することで、競合との圧倒的な差別化を図り、顧問先への提供価値を飛躍的に高めることが可能です。
私たち船井総合研究所は、この助成金領域こそが、貴事務所の未来を拓く成長の核になると確信しています。

助成金業務で成功するための組織体制と効率的な運用支援
私たちが大規模事務所様にご提案する助成金業務の方針は、単に申請数を増やすことではありません。
品質を担保し、顧問先様からの信頼を維持しつつ、いかに効率的かつ安定的に業務を遂行するか。そのための組織体制と運用フローの構築こそが、私たちの提案の核心です。
1.収益性を高める報酬体系の構築
助成金業務の報酬体系は、事務所の収益性を左右する重要な要素です。
私たちは、成功事務所の事例を基に、以下のような戦略的な報酬体系の導入をご支援します。
成功事例①:成果報酬型と戦略的な着手金設定(A事務所)
顧問先にとって分かりやすい料金体系を提供し、受注のハードルを下げます。
・報酬体系: 成果報酬30% + 着手金5万円
・成果報酬30%の内訳(その助成金に必要な書類を内包)
1 就業規則の作成・変更
2 各書式の雛形整備
3 着手金 ・・・等
・就業規則の費用や助成金コンサルタント料などを別途で請求する場合もありますが、上記のようにすることで、別途コンサルティング料などを請求する必要がなく、明朗な料金体系で顧問先の信頼を得やすくなります。
成功事例②:顧問契約と連動させた柔軟な料金設定(B事務所)
顧問契約の価値を高め、既存顧客からの安定受注を目指します。
・顧問先: 着手金0円 / 成功報酬17%
・スポット(単発): 着手金10万円 / 成功報酬25%
・ポイント: B事務所では申請の9割以上が顧問先です。
この事例は、日頃の信頼関係が助成金業務の安定受注に直結することを示しています。
リスクと工数に見合った料金設定で、収益を最大化します。
2.円滑な申請プロセスと組織的な品質管理体制
大規模事務所が助成金申請を滞りなく進めるには、明確な業務フローと組織的な連携が不可欠です。
フロー構築例①:組織で案件を創出する仕組み(B事務所)
担当者任せにせず、組織全体で助成金案件を創出し、管理します。
1.初期判断:
実務担当者が、社内勉強会や朝礼での情報共有を基に、各顧問先へ提案可能な助成金を判断します。
2.最終確認:
助成金チームが、提案の実現可能性を最終チェックします。
3.提案:
実務担当者が、自信を持って顧問先へ提案を行います。
フロー構築例②:専門部署による徹底した工程・品質管理(C事務所)
業務を分業・標準化し、ヒューマンエラーを防ぎながら生産性を最大化します。
・工程管理:
「受注 → 担当割振 → 資料作成 → チェック → 申請」という各工程を明確化。
専用アプリで案件ごとに進捗を管理し、業務の抜け漏れを防ぎます。
・品質管理:
特に重要なのが、部門長による最終チェックです。
担当者が作成した資料を、必ず助成金部門長が最終確認するフローを組み込むことで、申請書類の正確性を担保し、ミスを最小限に抑えます。
・柔軟な人員体制とミーティング:
・人員: 正社員5名に加え、パート1名(週3日勤務)を配置し、業務量に応じて柔軟に対応。
・月次ミーティング: 担当者全員で案件全体の進捗を確認し、担当業務を調整。
・週次ミーティング: チームごとに個々の進捗を確認し、問題の早期発見と解決を図る。
これらの仕組みにより、組織全体の生産性向上と、担当者一人ひとりへの業務負荷の平準化を実現します。
徹底したリスク回避と不正受給防止対策支援
助成金業務は、顧問先の資金調達を支援できる魅力的なサービスですが、複雑な制度と厳格な手続きが求められるため、潜在的なリスクも伴います。
私たちは、これらのリスクを未然に防ぎ、顧問先との信頼関係を揺るぎないものにするための、徹底したリスクマネジメント体制の構築をご支援します。
1.契約書によるリスク回避と責任範囲の明確化
トラブルを未然に防ぐため、報酬ルールはもちろん、万が一の事態に備えた詳細な取り決めを契約書に盛り込むことが不可欠です。
・報酬と支払期日の明記:
報酬額と支払期日を明確に定め、金銭トラブルを防止します。
・付随業務の追加料金を事前提示:
就業規則の変更など、付随して発生しうる業務の料金を事前に明示し、合意を得ます。
・中止・返還時のルール設定:
申請の中止や助成金返還時の報酬ルールをあらかじめ定めます。
・損害賠償の上限設定:
万一の損害賠償に備え、上限額と発生条件を取り決めておくことで、事務所の過度なリスクを回避します。
・不支給時の対応方針の明確化:
不支給の際の報酬返金の有無や対応方針を定め、不支給の可能性についても事前に顧問先の理解を得ておきます。
2.申請実務におけるヒューマンエラーの防止
日々の申請実務においても、細心の注意を払い、事務所内のルールを徹底します。
・書類管理の徹底:
申請書類の保管方法を統一し、責任の所在を明確にして、将来の監査等に備えます。
・労務リスクの事前確認:
残業代未払いや解雇問題など、助成金申請の前提となる労務管理状況を確認し、必要に応じて改善を促します。
・要件確認と期限管理の徹底:
各助成金の申請要件を厳密にチェックし、申請期限の管理を徹底することで、申請漏れや要件不備を防ぎます。
・顧問先との協力体制の構築:
必要書類の提出が遅れると申請できないことを明確に伝え、期限を厳守いただくための協力体制を築きます。
・迅速な進捗報告:
認定通知書や支給決定通知書を受け取ったら、速やかに顧問先へ連絡するルールを設け、安心感を高めます。
3.不正受給を絶対に許さない厳格な姿勢
助成金業務で最も避けなければならないのが、不正受給への関与です。
これは顧問先だけでなく、事務所にとっても致命的なリスクとなります。
・不正な依頼の即時辞退:
不正受給につながる依頼は、即時辞退、または申請を取り下げることを明確なルールとします。
・虚偽書類での申請不可:
実態と異なる書類での申請は行わないことを、顧問先に明確に伝えます。
・ペナルティの事前周知:
不正受給が発覚した場合の重大な結果(社名公表、刑事告発の可能性など)を事前に伝え、抑止力とします。
不正原因が依頼主にある場合の取り決め: 不正の原因が依頼主にある場合、事務所は不服申し立てを行わないことをあらかじめ定めます。
私たちは、こうした盤石なリスクマネジメント体制の構築を通じて、助成金業務を事務所の強力な収益源へと転換し、顧問先からの揺るぎない信頼を獲得するための基盤作りを推奨しています。
助成金業務を拡大させたい方、新規参入していきたい方は、ぜひ1度、無料相談をご活用ください!
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度