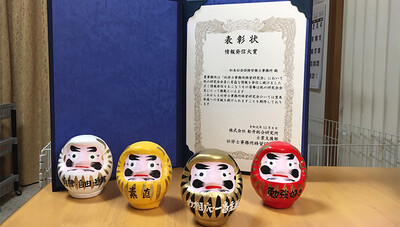業界の現状について
昨今、社労士事務所業界において、「企業型確定拠出年金(企業型DC・401k)」の商品化が注目を集めております。多くの社労士事務所様から、制度の内容や社労士が取り扱う意義についてのお問い合わせをいただいております。企業型の確定拠出年金は、企業が掛金を積み立て、従業員が自ら運用し、60歳以降に個人年金として受け取れる制度であり、2001年より確定拠出年金法を根拠に運用が開始されました。しかしながら、2022年3月時点での導入企業は約4.2万社と、全国の企業数約367万社と比較すると、普及率はまだ1%強程度に留まっており、今後の成長が期待される分野です。個人型のiDeCoは広く知られるようになってきましたが、社労士業界で注目されているのは、企業が退職金制度の一環として導入する企業型の方です。
ここでは、社労士事務所の新たな収益源となる可能性を秘めた企業型確定拠出年金導入支援について、その重要性と具体的な進め方をご紹介させていただきます。
昨今の社労士事務所業界における企業型確定拠出年金導入への関心は高まり続けています。多くの社労士事務所様が、この新しいサービスの導入を検討するにあたり、制度の概要や社労士が取り扱うメリットについて疑問をお持ちです 。ここではそうした疑問にお答えし、社労士事務所様が新たな商品として企業型確定拠出年金導入支援を開発する一助となることを目的としています。
企業型確定拠出年金(企業型DC・401k)とは?
まず、制度の基本的な仕組みについてご説明いたします 。企業型確定拠出年金は、企業が毎月掛金を積み立て、従業員が自己責任で年金資産を運用し、60歳以降に個人年金として受け取ることができる制度です。日本の確定拠出年金制度は、確定拠出年金法に基づき2001年から運用が開始されましたが、2022年3月時点での導入企業数はまだ限定的です。また、確定拠出年金には企業型と個人型があり、近年話題のiDeCoは個人型である一方、社労士業界で注目されているのは、企業が役員や社員のために退職金制度の一環として導入する企業型です。このように、企業型確定拠出年金は、企業の退職金制度としての側面を持つ重要な制度であると言えます。
中小企業で一般的な退職金制度である中小企業退職金共済(中退共)から企業型確定拠出年金(401k)への乗り換えは可能なのかという疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。結論として、中退共から企業型確定拠出年金への乗り換えは可能であり、両制度を併用することも可能です。中退共から企業型確定拠出年金に移行する際のステップとしては、①中退共のみ、②中退共と企業型確定拠出年金を併用、③企業型確定拠出年金のみ、という段階的な移行を推奨しております。特に、②から③へ移行する際には、中退共を解約して一時金として受け取った後、401kに移行する流れとなりますが、高齢の従業員の意向を考慮し、徐々に移行を進めることで社内の反対を少なくできる可能性があります。これは、社労士が企業に対して制度移行を提案する際に重要なポイントとなります。
退職金制度や資産形成制度について
さらに、企業型確定拠出年金の競合となる退職金制度や資産形成制度についてもご説明いたします。競合として挙げられているのは、中小企業退職金共済(中退共)、小規模企業共済、NISA(つみたてNISA)、iDeCo、はぐくみ基金です。それぞれの制度の特徴として、中退共は導入後一定期間の掛金助成、小規模企業共済は加入資格の制限、NISAは個人の柔軟な積立、iDeCoは企業型確定拠出年金との拠出額の枠共有、はぐくみ基金は老後以外の受取時期や確定給付型です。これらの比較を通じて、企業型確定拠出年金が持つ独自性やメリットを理解することが、社労士が企業に提案する上で重要となります。
2024年からの制度変更を踏まえ、社会保険料や所得控除の面で確定拠出年金のメリットは大きくなっております。掛金上限額、社会保険料効果、所得控除、運用非課税、受け取り時の税制優遇、引き出し可能な時期、対象年齢などが比較されており、社長にとっては企業型確定拠出年金を導入してから新NISAを始めることで、老後の資産形成と手元の資金増加の両立が可能となります。また、iDeCo+は、社長が少額でiDeCoを運用している場合に活用できる制度です 。これらの情報は、社労士が経営者に対して、退職金制度としての企業型確定拠出年金の優位性を説明する上で有効な材料となります。
社労士が企業型確定拠出年金の導入をサポートする理由は明確です。企業型確定拠出年金の導入は、税理士や保険代理店なども可能ですが、社労士事務所が導入をサポートすることで、企業にとっては就業規則の変更などを含めた手続きをワンストップで完了できるという大きなメリットがあります。他の専門家に依頼した場合、別途就業規則の変更などを依頼する必要が生じ、手間が増えるため、社労士事務所が導入をサポートすることの意義が強くあります。
企業型確定拠出年金を導入するためには、金融機関等のパートナーになる必要があります。SBIベネフィットシステムズの例として、紹介パートナーと事務取次パートナーの2種類が挙げられます。紹介パートナーは企業を紹介することでスポットのキックバックを得る一方、事務取次パートナーは事務所で企業の事務手続きを代行することで、継続的な事務代行手数料を得ることができます。事務取次パートナーは手間がかかるものの、中長期的な収益につながり、既存の顧問先への提案を通じて顧客満足度向上や顧客保全にも貢献します。社労士事務所がどちらのパートナーシップを選択するかは、事務所の戦略によって異なってきます。
「営業キラートーク集」
企業への提案時の有効な質問と回答をご紹介いたします。
例えば、
Q.「この制度は何がメリットなんですか?」
A.「社長1名から始められること、中小企業での導入がまだ少ないため競合他社との差別化や従業員の採用に貢献できること」など
Q.「中退共との併用やNISA、iDeCoとの違いは?」
A.「企業型確定拠出年金のメリットを強調し、 社労士が経営者に制度の魅力を効果的に伝えるような回答」。特に、企業型確定拠出年金は給与の額面から支払われるため、社会保険料の減額効果が期待できる点が、NISAやiDeCoと比較した際の大きなメリットです。退職金制度としてだけでなく、従業員の資産形成を支援し、企業の魅力を高めるための有効な手段となり得ます。
船井総研への経営相談のお勧め
貴事務所でも企業型確定拠出年金を事業化したいが、具体的な進め方が分からない、あるいは事務所の経営全般について課題を抱えているといったお悩みをお持ちでしたら、ぜひ船井総研の無料相談をご活用ください。
船井総研の無料相談では、弊社の専門コンサルタントが、貴事務所の経営に関する様々なご相談を無料で承っております。貴事務所の収益向上、顧問先への新たな価値提供、そして社労士業界における競争力強化に向けて、船井総研が全力でサポートさせていただきます。企業型確定拠出年金を核とした新たなサービス展開、退職金制度に関するコンサルティングの強化、そして社労士としての更なる発展に向けて、ぜひ一度、船井総研にご相談ください。
皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。