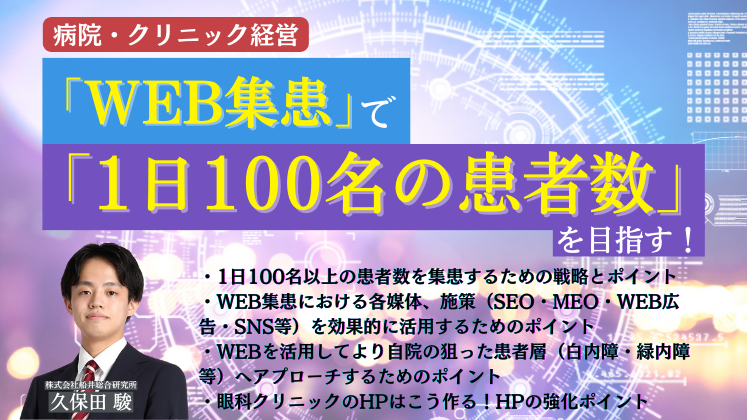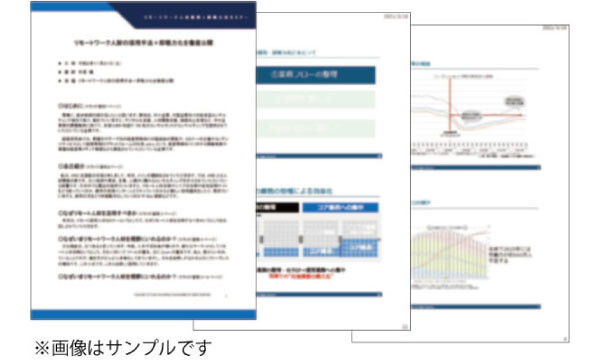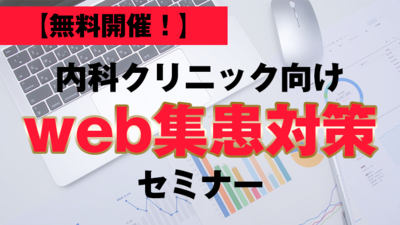患者数を伸ばすために、WEBに注力すべき理由 - 高齢者のインターネット利用者の動向

眼科クリニックの主な患者層は60歳以上の高齢者であるため、「Webによる集患は効果がないのではないか」というご質問をよくいただきます。しかし、総務省の通信利用動向調査によれば、60代以上でもインターネット利用率は80%を超えており、70代でも6割近くの方が利用されています。
さらに、SNSの利用率も増加傾向にあり、コロナ禍を経て70代の方々の約6割がSNSを利用するようになっています。この背景には、スマートフォンの普及が大きく影響していると考えられます。このように、眼科の主要な患者層である高齢者の方々も、スマートフォンを使ってWebを活用する時代となっているのです。
眼科クリニックの新患の来院経路
本日のセミナーは「1日患者数100名を目指す」というテーマで開催しており、患者数の増加を目指す先生方にご参加いただいていると思います。患者数を増やすためには、まず自院にどのような患者様が来院されているのかという傾向を把握することが重要です。

私どものコンサルティングでは、来院経路の調査を実施しています。初診の患者様には問診票で「当院を選んだきっかけ」をお伺いしており、「家族・知人からの紹介」「インターネット検索」「当院のHP」「近隣在住」などの選択肢からチェックしていただく形式で調査を行っています。
調査結果によると、総患者数を100%とした場合、Web経由が40%、近隣からが25%、家族や知人からの紹介が25%、その他という割合が一般的です。クリニックによって多少の変動はありますが、Web経由は30%から50%の間に収まることが多く、これは地域や施設を問わず、ほぼ共通した傾向として見られます。
確かに、立地条件や紹介患者の割合を上げることも重要ですが、立地の変更は容易ではありませんし、紹介患者を増やすためには、まず新規患者数を伸ばし、その患者様に満足いただいて口コミが増えていくという循環を作る必要があります。そのため、新規患者の獲得においてWebからの集患は非常に重要な要素となっています。
眼科クリニックのライフサイクル

また、眼科クリニック業界は現在、重要な転換期を迎えています。あらゆる業界には導入期、成長期、成熟期、安定期というライフサイクルが存在しますが、眼科クリニック業界は現在、転換点に差し掛かっています。
転換点における最も大きな変化は、需要と供給のバランスの変化です。成長期では需要が供給を上回っていましたが、転換点を超えると供給が需要を上回るようになります。この結果、必然的に眼科クリニック間の競争が激化することになります。

実際に、厚生労働省の診療報酬請求データによると、眼科の診療所数は増加傾向にあります。2015年から2020年の5年間で200件以上増加しており、人口減少と相まって、需要と供給のバランスが大きく変化していることは明らかです。
経営戦略の転換

このように供給が需要を上回る状況では、経営戦略も大きく変更する必要があります。もちろん、戦略はクリニックの状況や診療圏でのシェア率、周辺の眼科クリニックの状況などによって変わってきます。
成長期であれば、開業すれば一定の患者数は見込めました。しかし、成熟期に入り競争が激化すると、患者様は複数のクリニックを比較して選択するようになります。そのため、他院との差別化や専門性の確立が重要になってきます。自院独自の強みや特徴を磨き上げ、それを患者様にアピールしていく必要があります。
差別化の方法

弊社、船井総研では創業者の舩井幸雄が体系化した「船井流経営法」に基づいてコンサルティングを行っています。その中核となる考え方の一つに「差別化の8要素」があります。
この8要素は、重要度の高い順に、①立地、②規模、③ロイヤリティ、④商品力、⑤販促力、⑥接客力、⑦価格力、⑧固定客化力となっています。ただし、8番目が重要でないというわけではありません。特に上位3つは、一度確立すると変更が困難である分、優先度が高いという特徴があります。
それでは各要素について詳しくご説明いたします。
まず「立地」です。駅前などアクセスの良さや、住宅街に位置することによる豊富な患者層など、これらは最も強力な差別化要素となります。
次に「規模」です。建物の大きさや美観、医師の人数、多くの再診患者を受け入れられる体制、郊外であれば駐車場の有無が重要です。また、広いスペースを活かした検査機器の充実なども大きな強みとなります。
3つ目の「ロイヤリティ」は第三者評価に関する要素です。地域からの信頼や、クリニックとしての経営実績などが該当します。
ご理解いただけると思いますが、これら上位3つは容易に変更できません。そのため、その下の商品力から固定客化力までの要素が、即時に実行可能な重要な施策となります。
「商品力」は医師の技術力や、医療サービス全体の質、きめ細やかな対応、待ち時間の長短などが含まれます。
「販促力」は、本日ご説明するWeb販促を中心に、院内販促やチラシなどのオフライン施策も含みます。
「接客力」は、医師による診察時の対応や、受付・検査スタッフの患者対応の質を指します。
「価格力」は、保険診療では変動の余地は少ないものの、美容皮膚科などの自費診療サービスにおける価格設定が該当します。
最後の「固定客化力」は、かかりつけ患者様の定着率を表します。

繰り返しになりますが、上位3つの要素は変更が困難です。立地の変更には移転という大きな決断が必要ですし、規模の拡大には費用面や用地確保など様々な課題があります。ロイヤリティの構築にも相当な時間を要します。
そこで重要となるのが、戦術的差別化です。特に4番目の「商品力」について、以下の2つの観点からお考えいただきたいと思います。
1つ目は、先生ご自身が理想とする最適な医療スタイル・医療サービスの追求です。日々の診療の中で、各先生方には独自の医療スタイルをお持ちであると感じております。他院との違いを意識しながら、患者様のために最適と考える医療を追求していただきたいと思います。必要に応じて手術機器などへの投資も検討いただき、医療の質と商品力の向上を図っていただければと思います。
2つ目は、既存患者様からの選択理由のヒアリングです。これは非常に重要な取り組みです。近隣に他の眼科があるにもかかわらず、あえて遠方から来院される患者様、リピーターの患者様には必ず選択理由があります。その理由が、気づいていなかった自院の強みである場合も多々あります。
このように商品力の向上を図りながら、5番目の要素である販促力、特に本日ご説明するWeb戦略を効果的に活用することが、これからのクリニック経営における差別化の鍵となります。
患者数を伸ばすために、Webに注力すべき理由 – まとめ

ここで、Webに注力すべき理由について整理させていただきます。
現代では、眼科クリニックの主要な患者層である高齢者の方々もWebを活用する時代となりました。実際の統計では、新規患者の約4割がWeb経由で来院されており、地域によっては3割から5割にまで及びます。
このことから、Web対策をこれまであまり実施してこなかったクリニックにとっては、ここに大きな成長の余地があると言えます。逆に言えば、Web対策を怠ることは、潜在的な患者様の4割にアプローチできていないことを意味します。特に、1日の患者数100名を目指すような規模の診療を実現するためには、このWeb経由の患者層の取り込みは必要不可欠と言えるでしょう。
また、眼科クリニック業界は現在、需要に対して供給が上回る段階に差し掛かっているという転換期を迎えています。このような状況下では、周辺の眼科クリニックとの差別化が極めて重要になってきます。
先ほどご説明した船井流差別化の8要素に基づけば、まず自院の商品力や独自の強み、特長を磨き上げることが基本となります。その上で重要になるのが、それらをいかに効果的にPRしていくかという点です。様々なWeb媒体を活用し、各段階の患者様に適切にアプローチしていく戦略が必要となってきます。
ただし、ここで注意したいのは、やみくもに様々なWeb媒体に手を出せばよいというわけではないという点です。クリニックの規模や特性によって、効果的な戦略や相性の良い媒体は異なります。本日は、この観点からも具体的な施策についてご説明させていただきたいと思います。
2. Web集患の戦略とポイント - クリニックの規模別の方向性
これからは、クリニックの規模や各媒体の特徴を踏まえた、Web集患の戦略と重要ポイントについてご説明させていただきます。
クリニックの取り組むべき施策は、開業間もない成長期のクリニックと、地域に定着し1日80名以上の患者様が来院される成熟期のクリニックとでは、当然異なってまいります。
規模別の具体的な方向性についてご説明いたします。
▼続きは下記よりダウンロードいただけます