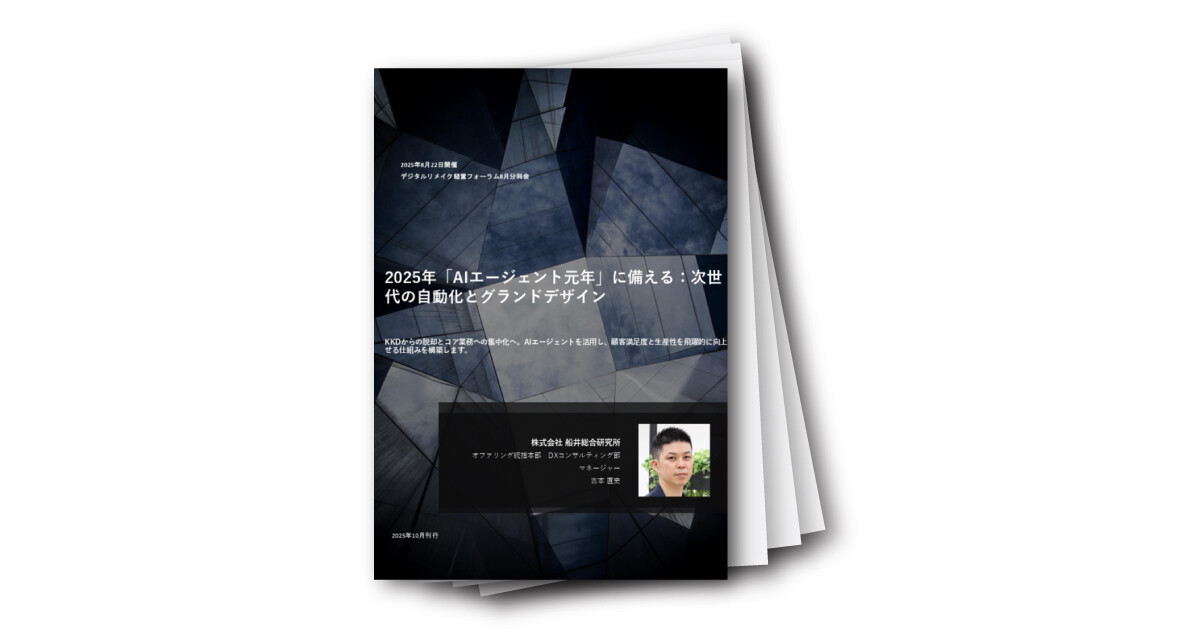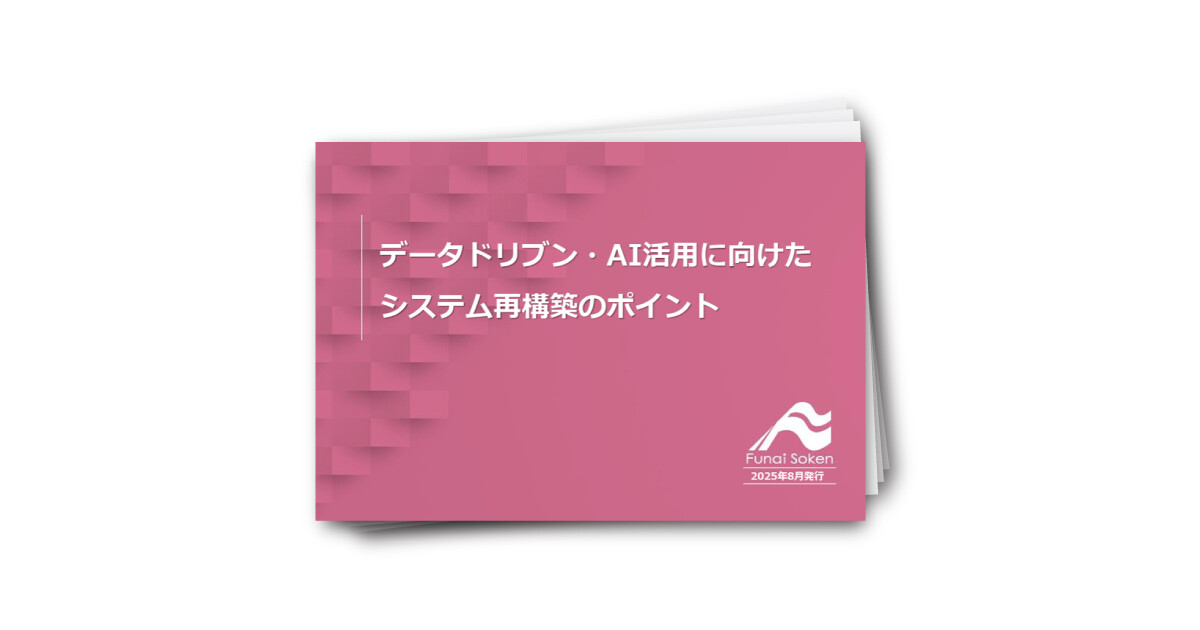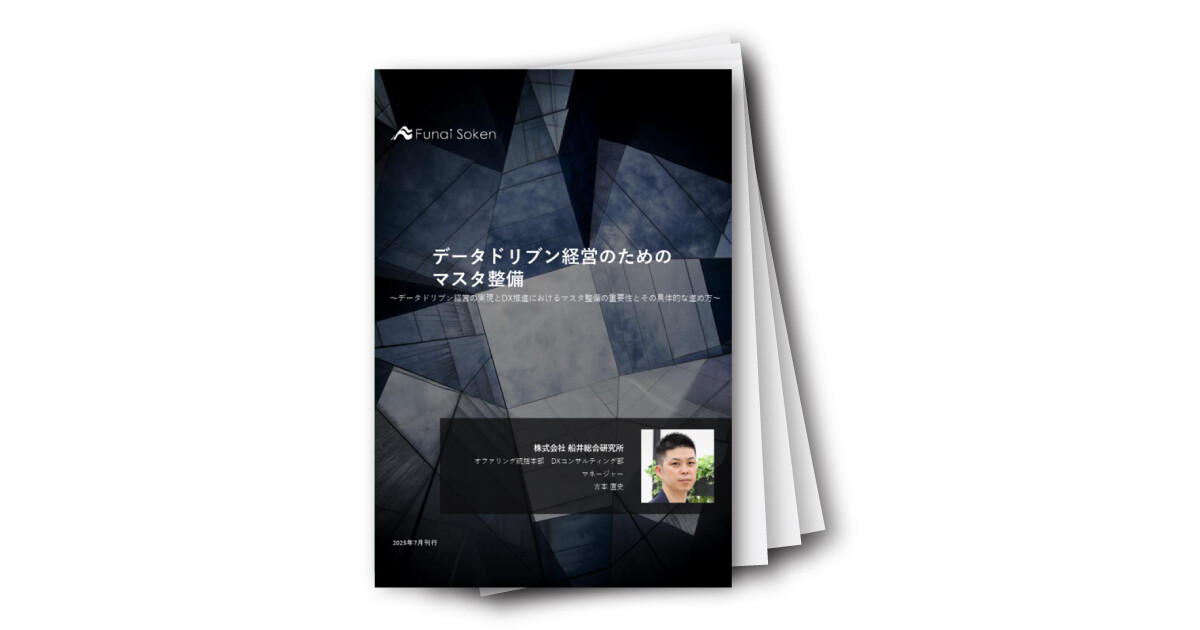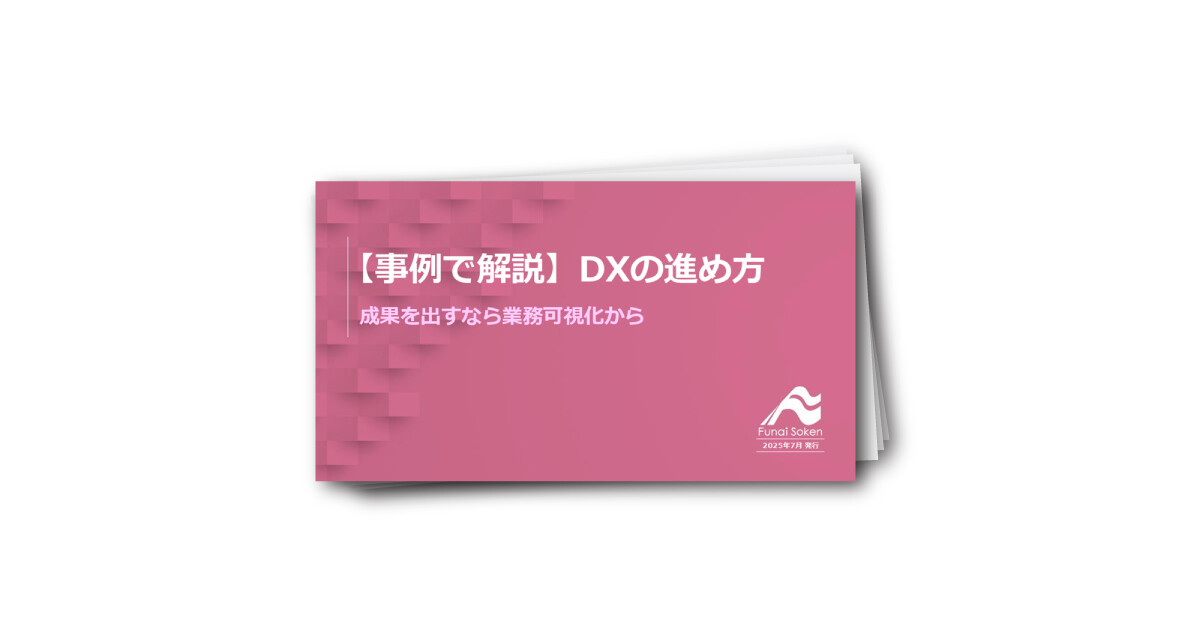本記事のテーマは、「日本企業がIT大国であるインドから学ぶべきこと」です。
GoogleやMicrosoft、IBMなど、アメリカの世界的な大企業のトップは、実は皆インド人というほど、ITに強い国がインドです。
インドで作られたデジタルツールが全世界に広がり、インドは世界のIT、DXを牽引していると言っても過言ではありません。
船井総研ではインド視察ツアーを開催し、インドの素晴らしい企業を視察してきました。
そこで得られた、インドがIT大国たる理由や現地企業の取り組み、そしてその中で日本企業が取り入れるべきことを、以下の4つのポイントから解説します。
①7/24(セブンパートゥエンティーフォー)
②GCC(グローバル・ケーパビリティ・センター)
③ZOHO(ゾーホー)
④IBM
なぜインドがIT大国になったのか?
人口10億人以上が経済的な基盤に
もともとインドは、オフショア、つまり欧米先進国の下請け的な業務をずっとやってきたという歴史があります。
Appleの例で言うと、開発とマーケティングはアメリカでやり、実際はFoxconnという台湾に本社を置く企業(実質は中国の会社)が製造しています。
※オフショア:オフショアリング。企業が業務の一部分もしくは全体を海外に移すこと
中国が安く物を作れるのは、人口が10億人いるからです。
製造業はロットサイズが大きくなればなるほどコストが下がるためです。
インドも人口が10億人を超え、中国を抜いて世界1位になりました。
この巨大な市場と生産能力が、インドの経済的な基盤を支えています。
インドのアドバンテージ
インドのアドバンテージは「英語圏であること」です。
インドは元々イギリスの植民地だったため、英語が準公用語です。
インド国内には17もの言語が存在し、州が変わると言葉が通じないため、共通言語として英語が広く使われています。
また、インド工科大学(IIT)では、理系人材が毎年日本の約10倍も生み出されています。
インドは現在、IT人材の豊富さ、英語圏であることを背景に、世界のIT・DXを牽引する「IT大国」としての地位を確立しています。
新興国のケーパビリティの活用
中小企業であっても、インドの状況は「全く関係ない」と考えるべきではありません。
インドにおける1 ヶ月の人件費はワーカの場合大体 2 万ルピー、日本円に換算すると 4 万円です。
欧米は、インドの安価な人件費(ワーカーで 1 ヶ月約 4 万円)を利用しています。
日本企業も、グローバルに目を向け、新興国のケーパビリティを活用していくことが非常に大事です、と考えられています。
※ケーパビリティ:企業成長の原動力となる組織的能力や強み
①「7/24(セブンパートゥエンティフォー)」の概念
これは、アメリカとインドの時差を利用する考え方です。
アメリカとインドの間には約13時間の時差があります。
この時差を利用することで、以下の流れで生産性を高めます。
1.アメリカでの作業(昼間)
アメリカのチームが日中に要件定義や仕様決定(川上の企画)を行います。
2.夜間の引き継ぎ(インドの活用)
アメリカの夕方にその成果をインドへ送ると、インドは早朝で業務を開始できる時間です。
3.24時間稼働の実現
アメリカが夜間に休んでいる間も、インドのチームがプログラミングなどの作業を進め、翌朝には成果物をアメリカに戻します。
この手法は、単に安価な労働力を利用するのではなく、インドの優秀な人材(ケーパビリティ)を最大限に活かすという新しい発想に基づいています。
時差を利用し、地球の裏側の人材を使うことで、あたかも「24時間仕事をしているのと同じ」という状態を作れるということです。
グローバルに目を向けて、新興国のケイパビリティをどう使うか、という発想が大切です。
②GCC(グローバル・ケーパビリティ・センター)
GCCとは
GCC は、グローバル・ケイパビリティ・センターの略です。
昔は「オフショア」と言っていました。オフショアとは、川上の企画などは先進国で行い、プログラミングなどの川下の作業を新興国が担うことでした。
GCCとオフショアの違い
GCCは下請けではなく、開発拠点としての役割を果たします。
つまり、自社の一部門がインドにあるというイメージです。
例えば、日本でIT人材を確保するのが難しい場合、情報システム部の人材をインドでも採用することで分業できます。
自社の一部門がインドにある、というイメージであり、開発や設計といった仕事も含めてインドやインド人の力を借りようという新しい発想です。
この GCC が、新興国のケーパビリティを活用するという観点で重要です。
リバースイノベーション
リバースイノベーションとは、新興国が下請けで使っていた新興国の技術が逆流してきて、先進国を凌駕する現象です。
ここで、インド企業におけるリバースイノベーションの具体例をご紹介します。
今回の視察で訪れた、「マヒンドラ&マヒンドラ」というカーメーカーがあります。
もともと彼らは農機具のメーカーでした。
アメリカの建設機械メーカー、キャタピラーの下請けでしたが、今では農機具のメーカーとしてアメリカでトップシェアを取っています。
下請けだと思っていた会社がいつの間にか自社ブランドを持ってそれで逆流してくる。
その現象をリバースイノベーションと言います。
③Zoho(ゾーホー)
リバースイノベーションの実現
Zohoも、もともとはデータセンターのログを取る管理ソフトウェアを作っている会社でした。
販売にあたり営業管理が必要になり、セールスフォース・ドットコムを導入しました。
しかし、それをきっかけに「自分たちで営業管理システムを作ろう」となり、自分たちで作った営業管理システムが「Zoho」です。
統合型CRMプラットフォームの市場は伸びており、Zohoは会社名をZohoに変えました。
また主力事業を「統合型CRMプラットフォーム」にしました。
これはリバースイノベーションの代表例です。
低価格・高品質を支える独自の「オール自前主義」
ZohoのCRMはセールスフォースと比べても評価が変わらないほど高いのに、非常に安価です。
その理由は、インドの人件費が安いからだけではありません。
アメリカの場合、エンジニアはヘッドハントをして取り合いますが、Zohoは違います。
インドの貧困地域で、高校卒業生にテストを受けさせ、高得点を取った優秀な人材をZohoスクールという自前の大学で2年間学習させます。
その後インターンを経て、Zohoに採用されるという「オール自前主義」で人材を育てています。
中小企業に焦点を当てた販売・設計戦略
また、セールスフォースが大企業を相手に作られたのに対し、Zohoは従業員500人未満の中小企業をターゲットにしています。
Zohoはインドに拠点をおいているから安いのではなく、売り方が違うのです。
中小企業がシステムを使うことでコストが下がるように設計されています。
さらに、彼らの売り方はPLG(プロダクト・レッド・グロース)です。
これは営業が不要で、プロダクトがプロダクトを売るという手法です。
例えばZoomが無料版を使ったあとに有料版を使うのもPLGです。
PLGは営業が不要なため、コストを安くできるのです。
④IBM
イノベーションのジレンマによる苦戦
IBMはもともとメインフレームと呼ばれる汎用のコンピューターを作っていました。
しかし、メインフレームからパソコンへの変化に伴う「イノベーションのジレンマ」により苦戦しました。
メインフレームという高額な汎用コンピューターを売っていた時代から、安価で誰でも作れるパソコンの時代になり、価格が下がり儲からなくなったのです。
メーカーからサービス業への転身
そこで、IBMはメーカーからサービス業へと転身しました。
自社の商品だけでなく、顧客に最適な商品を提案し、ハードではなくソリューションの提案・提供に力を入れたのです。
そして、IBMはインドにGCCを持っており、世界中の間接業務をIBMが受け、それをGCCでやらせています。
このIBMがインドでGCCをやったことが、IBMが復活できた大きな要因の1つだと言われています。
まとめ
本記事では、IT大国インドの最前線を解説しました。
インドは、豊富な理系人材と英語力を背景に、欧米のオフショアから、自社の開発・戦略拠点であるGCC(グローバル・ケイパビリティ・センター)へと進化しました。
このグローバルな分業体制が、24時間体制の業務(7/24)を可能にし、圧倒的な生産性を実現しています。
Zohoのような安価で高品質なサービスが先進国を凌駕する「リバースイノベーション」も起こりました。
国内人材の確保が難しい今、「中小企業だから関係ない」と決めつけず、インドのケイパビリティを活用することが、DXを成功させるための新たな視点となります。
他にも、最新の業績アップ事例を踏まえて、事業に役立つ情報を発信していく予定です。
楽しみにしていてください。