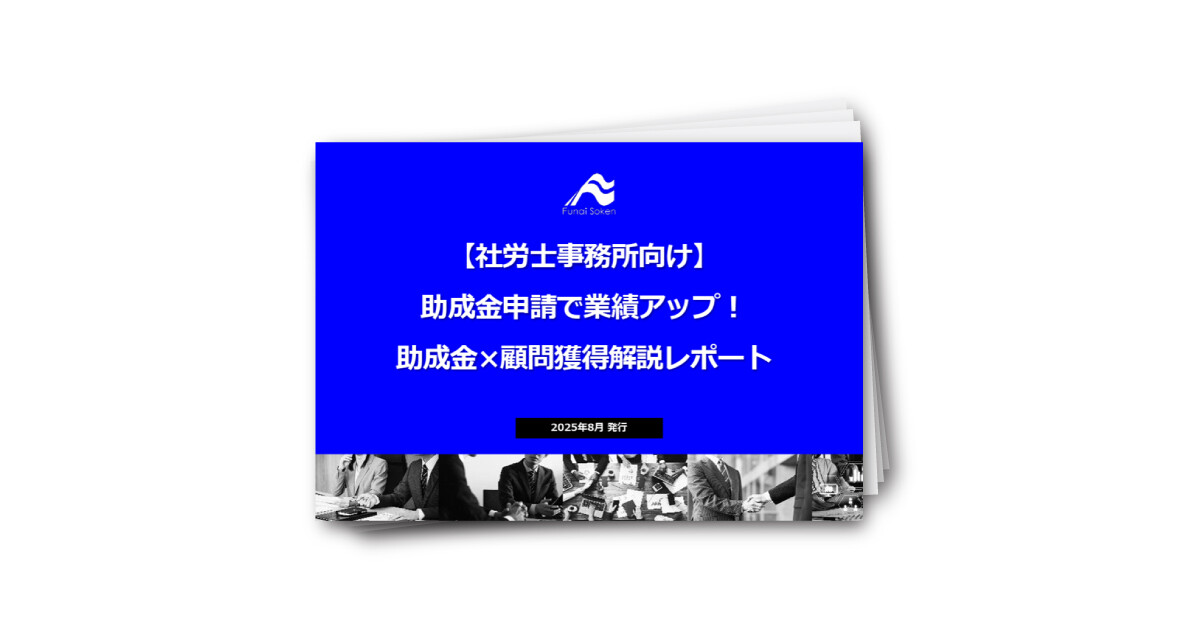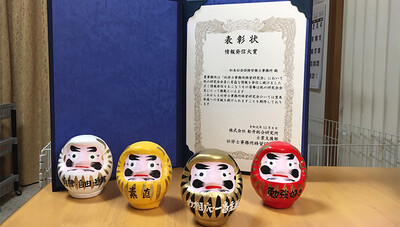【社労士事務所向け】企業型確定拠出年金(401k)導入・運用コンサルティング

業界の現状について
現在、社労士事務所業界では、企業型確定拠出年金(401k)導入コンサルティングが注目を集めています。
多くの社労士事務所がこのサービスの商品化を検討していますが、制度内容や社労士が取り扱う上でのメリット・デメリットについて、十分に理解されていない現状があります。
企業型確定拠出年金(401k)は、企業が従業員の退職金制度の一環として導入する年金制度であり、企業にとっても従業員にとっても様々なメリットがあるため、今後さらに導入が進むと予想されます。
しかし、2022年3月時点で導入企業は約4.2万社と、全国の企業数から見るとまだ1%強程度にとどまっており、その潜在的な市場規模は大きいと言えます。
この状況を踏まえ、社労士が401k導入支援を行うことは、顧問先への新たな価値提供と、事務所の収益拡大に繋がる可能性を秘めていると考えられます。
このソリューションがおすすめな理由
•企業型確定拠出年金(401k)の制度詳細:
企業型確定拠出年金(401k)は、確定拠出年金法に基づいて2001年から運用が開始されましたが、2022年3月時点で約4.2万社程度の導入にとどまっています。
この数字は、全国の企業数約367万社から見ると、まだ1%強程度に過ぎず、今後の導入拡大の余地が大きいことを示唆しています。
確定拠出年金には、企業型と個人型があり、iDeCoは個人型に該当します。
社労士業界で注目されているのは、企業が役員や社員のために退職金制度の一環として導入する「企業型」の方です。
企業型確定拠出年金(401k)は、役員でも加入が可能であり、従業員の制限や強制もないため、1名から導入できる点が特徴です。一人社長の会社でも適用できるため、提案対象となる企業の幅が非常に広いと言えます。
•掛金の上限額と制度設計の詳細:
掛金の上限額は、他の企業年金の有無によって異なり、他の企業年金がない場合は55,000円/月、他の企業年金がある場合は27,500円/月となります。
中退共を併用している場合は、55,000円/月の上限が適用されます。
制度設計方法には、①選択制、②給与上乗せ、③給与上乗せ&選択制、④マッチング拠出の4つがあります。
会社が拠出する際の計算方法には、「定額」「定率」「定額と定率の組合せ」があります。
•受取時期と受取方法の詳細:
原則として60歳になるまで受け取ることはできません。
ただし、障害状態になったり、本人が亡くなったりした場合は、60歳未満でも受け取り可能です。
60歳以降は、75歳までの希望する時期に受け取れます。
ただし、加入期間が10年未満の場合は、受取開始時期が61歳以降になります。
受け取り方は、「一時金」「老齢給付金として年金」、またはその組み合わせで選べます。
「一時金」の場合は、退職所得控除の対象となり、「年金」として受け取る場合は、公的年金等と同様に雑所得となり、公的年金等控除の対象となります。
•iDeCo・NISAとの違いの詳細:
企業型確定拠出年金、iDeCo、NISA・つみたてNISAの違いを比較すると、掛金上限額、社会保険料効果、所得控除、運用非課税、受け取り方法、手数料、引き出し可能な時期などが異なります。
企業型確定拠出年金のメリットとして、拠出の上限額が大きいため、税制優遇メリットが大きくなり、運用効果も高まる可能性があります。
社会保険料軽減効果があるため、社会保険料の等級が下がる可能性があります。
iDeCoから移管できるだけでなく、iDeCoとの併用も可能です。
従業員側から見た場合、事務手数料の負担がない点がメリットです(iDeCoの場合は個人負担)。
•従業員の退職・転職時の手続きの詳細:
転職先の企業が401k制度を導入していれば、資産の引継ぎが可能です。
転職先の企業が導入していない場合や、公務員に転職する場合は、脱退一時金を受け取るか、iDeCoに移管する必要があります。脱退一時金を受給するためには、いくつかの要件があります。
退職後、自営業(第1号被保険者)となる場合や、仕事に就かない場合(専業主婦・主夫)も、脱退一時金を受け取るか、iDeCoに移管できます。
移管手続きには期日があり、退職後6か月以内に行う必要があります。期日を過ぎると、自動的に国民年金基金連合会に移管され、給付時の税制優遇額が低くなったり、手数料が発生したりします。
•社労士事務所の収益化モデルの詳細:
報酬イメージとしては、導入サポート込みで1社あたり年間30万円前後となります。
導入サポート費用は10~20万円程度、運営管理サポートは基本料金+人数変動額、研修サポートは研修実施時の講師料となります。
お客様は金融機関へ事務手数料を支払い、そこから代行手数料が社労士事務所へ入るという流れになります。金融機関の手数料は5,000円程度です。
導入サポートや手数料の設定は自由となっています。
導入次年度からは1社あたり年間10~20万円程度となり、1社導入の年間当たりのインパクトはそこまで大きくありませんが、LTV(ライフタイムバリュー)が長いため、顧問契約と同様にストック報酬型で、長期的な収益が見込めます。
クロスセルにより、顧問契約にプラスオンしたり、スポットのお客様に提案したり、逆に401k経由で集客したお客様に顧問やその他の商品を提案することで、報酬を最大化できます。
•提案対象となる企業の規模の詳細:
401kを導入するための条件は、「厚生年金適用事業所」であることです。
一人社長でも加入可能であるため、多くの企業が対象となります。
近年では、大企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業も導入するメリットが増加しており、導入企業は増加傾向にあります。
どの企業に提案するかは、事務所の方針によって決めることができます。業種や人数を絞って提案することで、集客や営業体制をスムーズに構築できます。
•401kの勉強方法の詳細:
制度そのものを理解するには、セミナーに参加したり、中小企業の社長向けに書かれた制度説明の本を数冊読んだりすることが有効です。
資産運用に関する知識も必要ですが、Youtubeでも多くの情報が得られます。
従業員説明会を実施する際には、投資商品の細かい知識は必須ではありませんが、投資の全体像や401kの中での運用方法は把握しておく必要があります。
まずは顧問先等、事務所との接点がある先からトライアルしていくことで、実務経験を積みながら知識を深めることができます。
•企業が制度を導入するメリット・デメリットの詳細:
企業側のメリット:
▪役員でも資産形成が可能:中退共等の制度と異なり、役員も加入できるため、経営者層のニーズにも応えられます。
▪税制優遇:企業が拠出した掛金は全額損金算入でき、拠出金は給与とならないため課税対象外となり、所得税や住民税、社会保険料の計算対象外になります。さらに、運用益も非課税で、給付時にも税制優遇があります。
▪採用力・定着力の向上:福利厚生として資産形成ができるため、従業員の企業選びの際の選択肢となり得ます。
特に、2022年4月から高校での金融教育が義務化されたことで、今後、金融知識を持つ世代が採用市場に登場するため、福利厚生の充実がより重要になります。
企業側のデメリット:
▪制度運営の事務費用が発生:導入時に制度構築のためのコンサルティング費用や、運営管理機関への手数料が発生します。
▪既存の社内制度の見直しが必要:退職金規定だけでなく、賃金制度の変更が必要になる可能性もあります。
導入サポート機関がどこまでサポートしてくれるかが重要です。
▪従業員への投資教育が必要:従業員への継続的な投資教育が義務付けられているため、そのための仕組みづくりや体制構築が必要です。通常は運営管理機関などを活用します。
船井総研がお手伝いできること
船井総研は、企業型確定拠出年金(401k)導入支援に関する豊富な知識と実績を持っており、社労士事務所の皆様のビジネスを強力にサポートいたします。もし、貴社が企業型確定拠出年金(401k)導入コンサルティングを商品化する上で、以下のような課題をお持ちでしたら、ぜひ弊社の無料相談をご活用ください。
•制度導入に関する具体的な手順を知りたい
•従業員への説明会をどのように実施すればよいかわからない
•金融機関との連携方法がわからない
•効果的な営業戦略を立てたい
•リスク管理の方法を知りたい
•他社事例を参考にしたい
弊社では、貴社の状況や目標に合わせて、最適なコンサルティングプランをご提案いたします。
また、導入後の運営サポートや、従業員への継続的な投資教育まで、トータルでサポートいたします。
無料相談では、
•貴社の強みや弱みを分析
•競合他社の動向を把握
•具体的な行動計画の作成
•収益モデルの構築
•リスクヘッジの方法
など、より実践的なアドバイスをさせていただきます。
関連するダウンロードレポート
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度