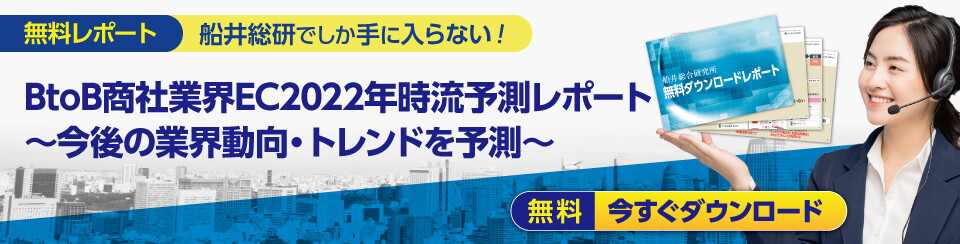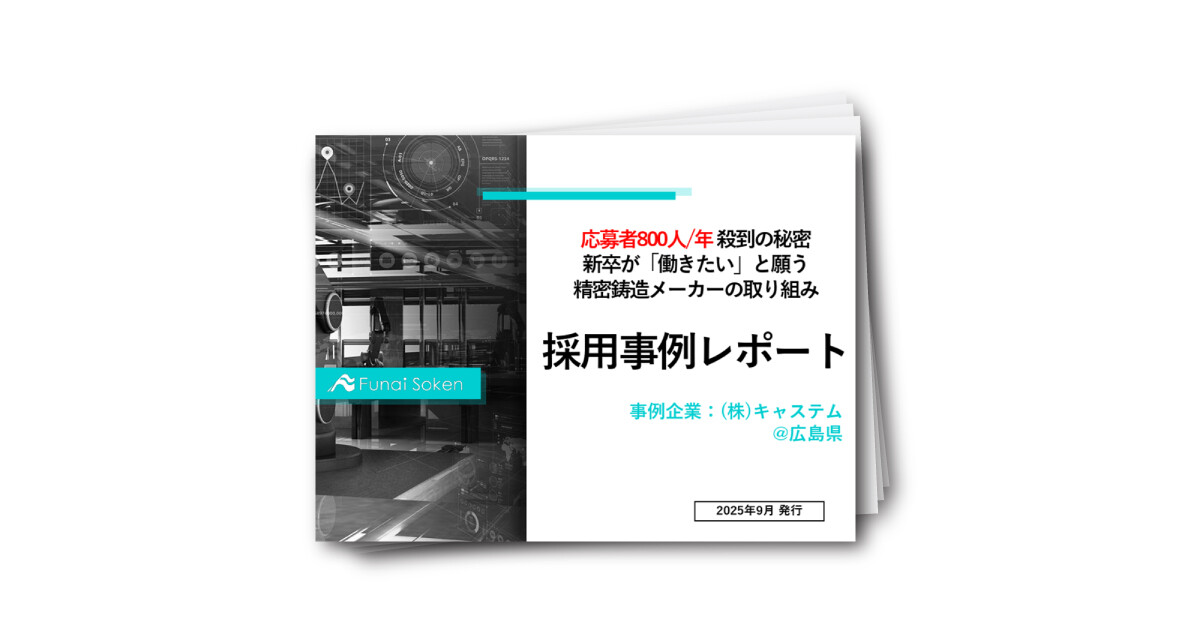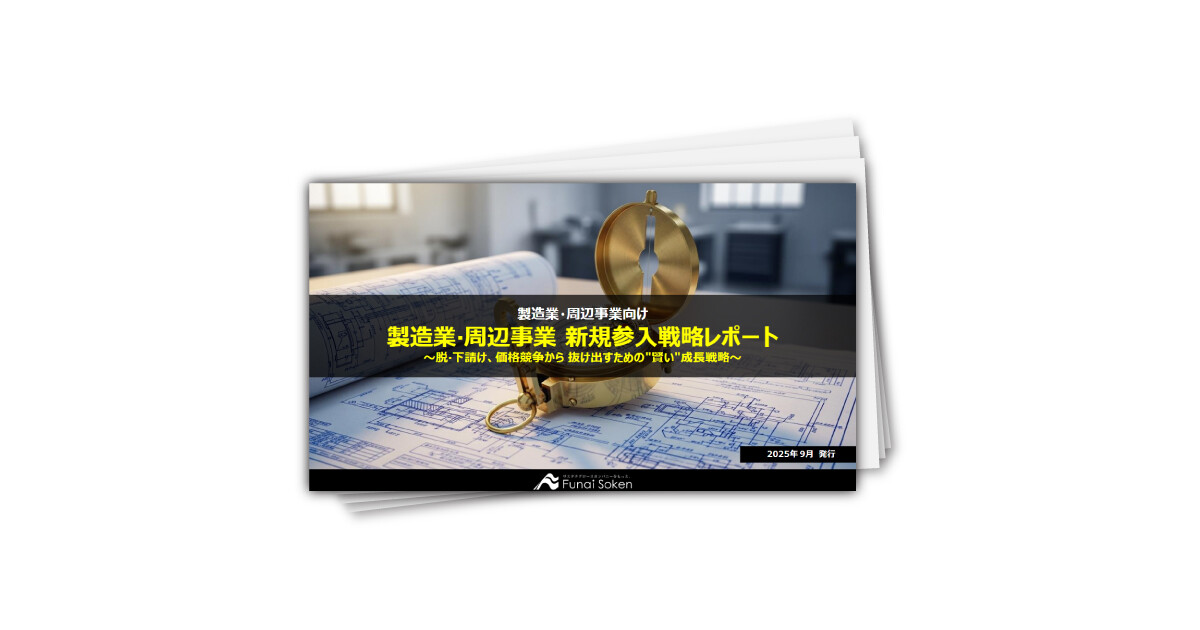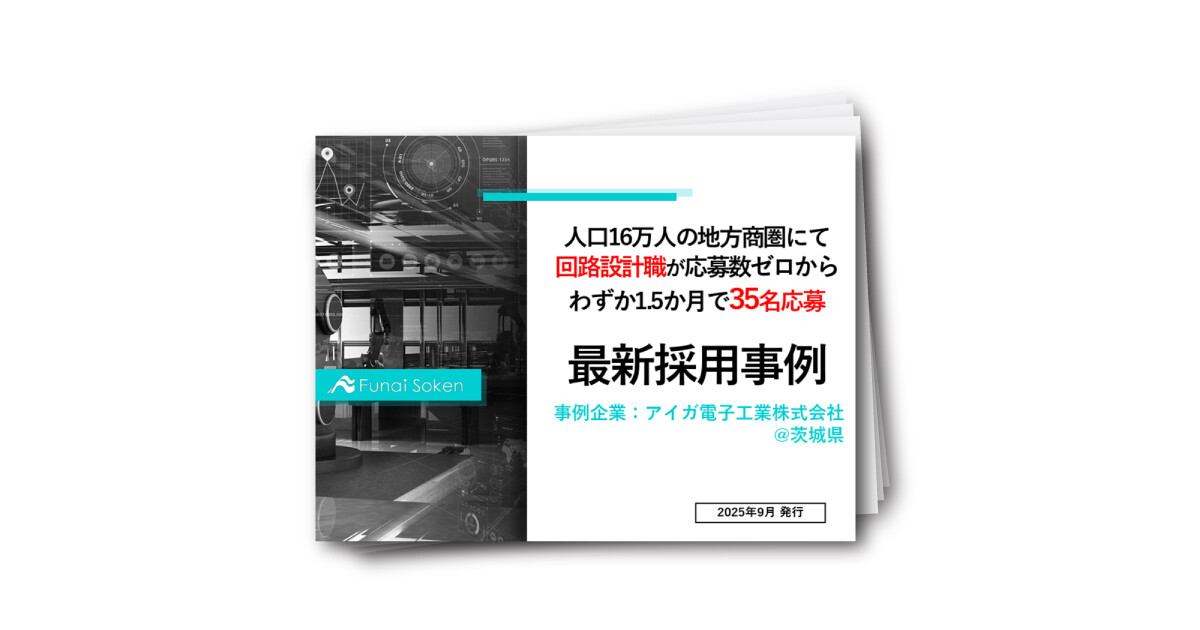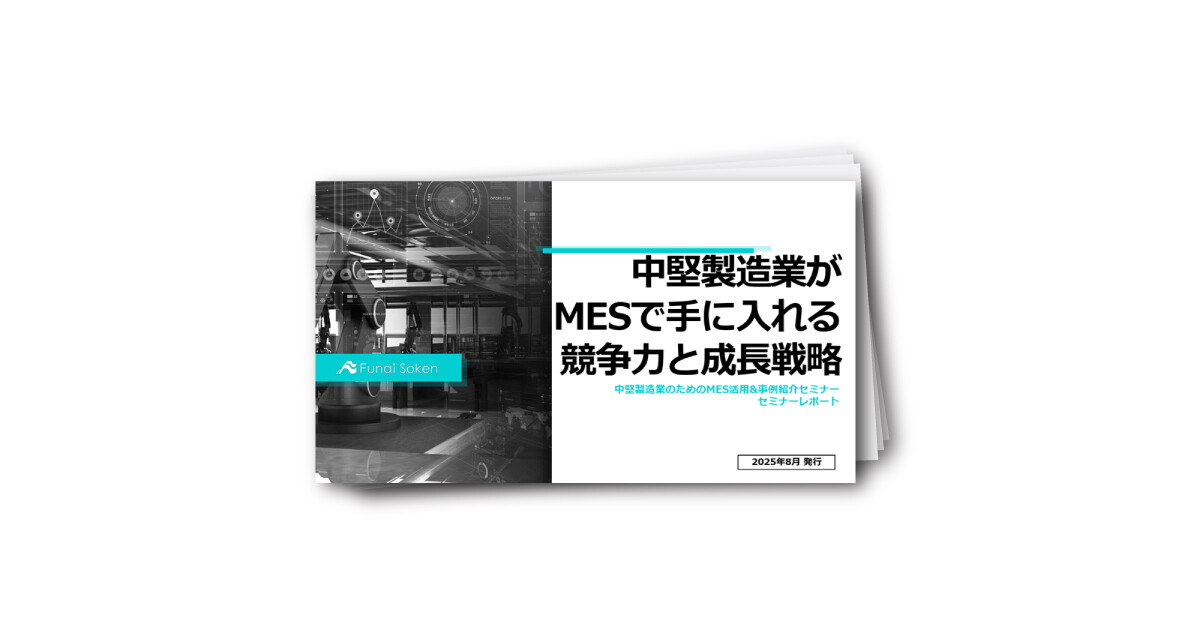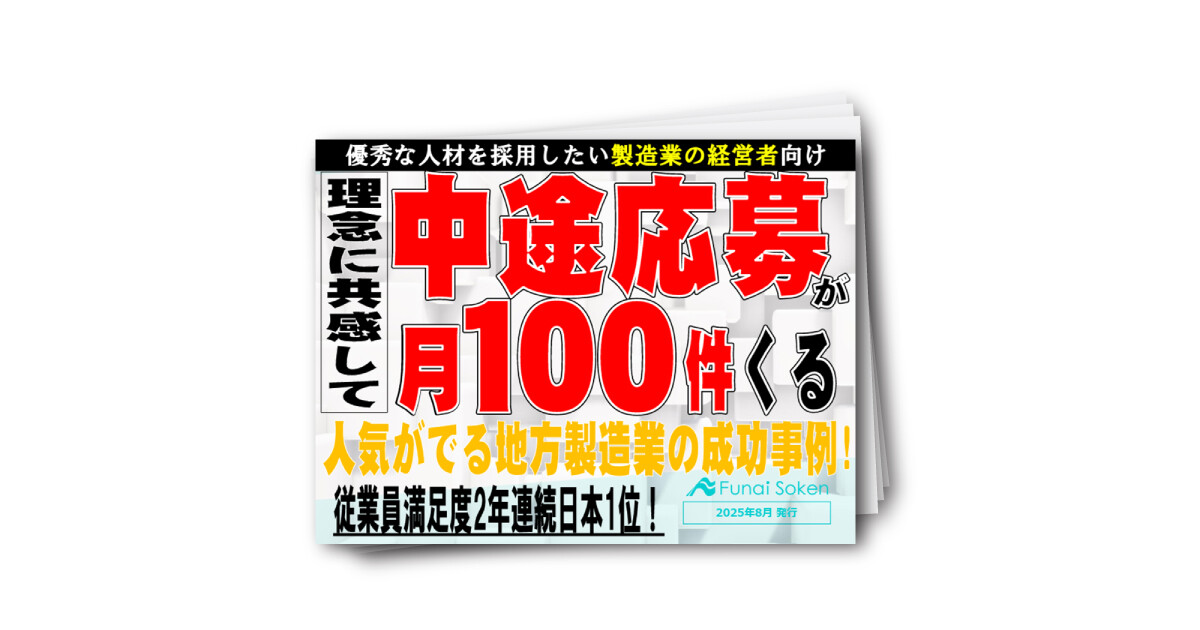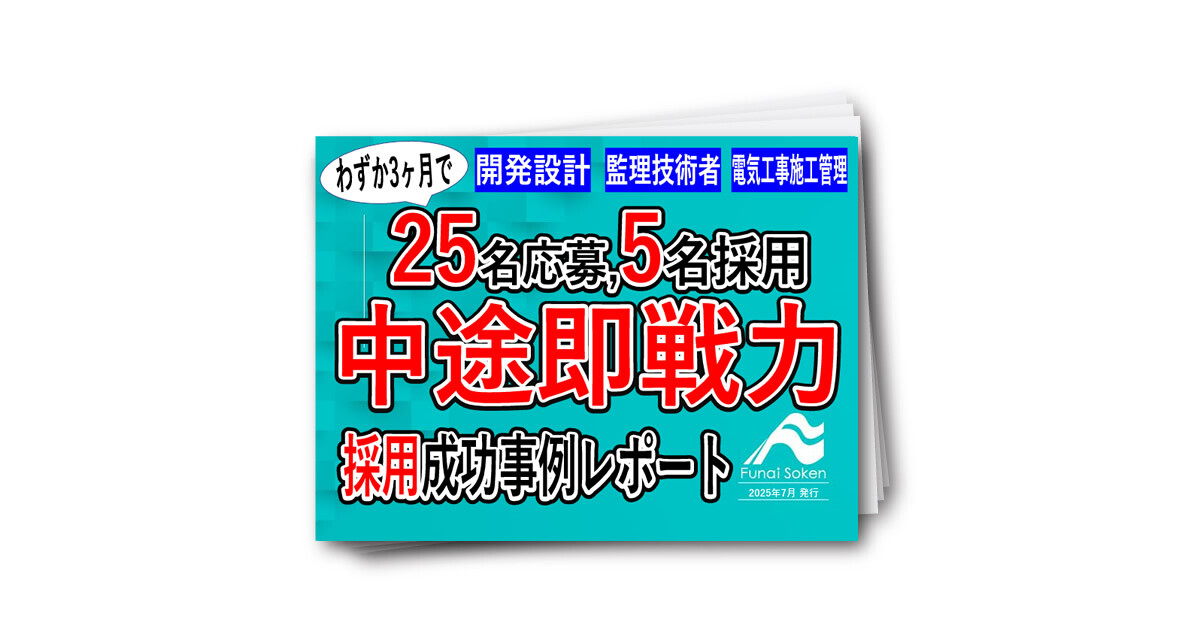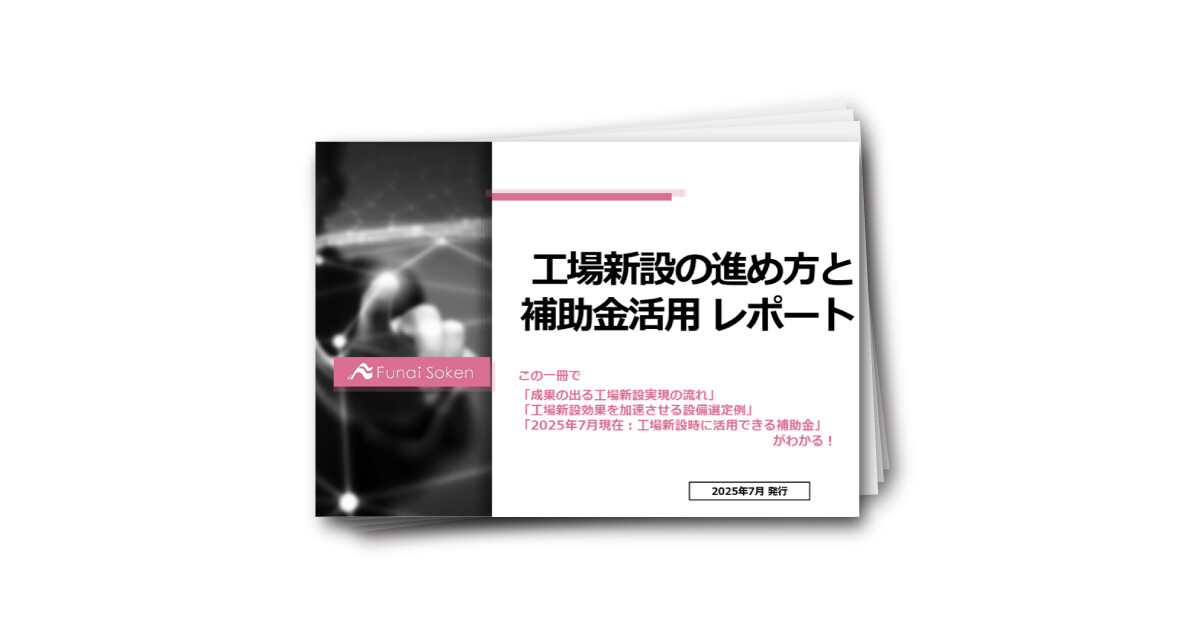日本トップの成長率(※) MonotaROの挑戦!
※日経ビジネス2016年1月11日号「成長率ランキング100」
聞き手:FUNAIメンバーズ事務局 編集部
ファクトリービジネス研究会 部品加工業経営部会 機械工具商社経営部会
主宰 片山 和也
編集部:
弊社の第90回経営戦略セミナー 研究会全国大会でご登壇いただいた株式会社MonotaRO(以下、モノタロウ)代表執行役社長 鈴木雅哉氏にお話を伺います。まずは御社の事業についてお聞かせください。
鈴木社長:
当社は主にインターネットを通して、国内の、主に製造業や工事業、または自動車整備業の事業所に対して、原材料以外となる間接資材を販売しています。現時点では950万商品を当社のプラットフォームであるインターネットのサイト、そしてカタログ、チラシなどを通して販売させていただいております。
編集部:
創業されて今年で16年目、そして14期連続で増収でいらっしゃいます。
鈴木社長:
はい。2000年10月に会社を設立した当時、インターネットをビジネスでいかに活用するかという黎明期でした。今の親会社であるアメリカのグレンジャー社と住友商事のジョイントベンチャーでスタートしたんです。私も住友商事の出身ですが、当社の創業者で現会長の瀬戸が、間接資材とその事業者において、インターネットを通じて「検索する、探す」という価値提供を事業化できるのではと考えました。当時アメリカで間接資材においてナンバーワンであったグレンジャー社と話をして事業をスタートさせたのが16年前です。
編集部:
最初にインターネットという流れがあって、そこからのビジネス展開だったということですね。
鈴木社長:
はい。インターネット活用において、どんな事業内容・商材がそこに適しているのかという事業調査をもとにスタートしました。我々が着目した間接資材という領域は、総計して必要とされる商品の数で考えると、現在およそ1,000万商品を販売しているわけですけども、それでもまだ十分でないくらい裾野が広い領域なんです。
実際に原材料になるような商品と、原材料以外の副資材、間接資材、そういった商品には間の事業が必要になります。BtoBであれば、そのお客様ごとの事業内容、またはお仕事によって必要となる資材が違いますし、BtoCと違って、必要となる商品資材とその量のバラつきがとても大きいです。通常はそこを見極めるために、セールスマンがお客様のニーズを確認し、個々に見積もりをしてきたわけですが、一つの商品を1ドルや2ドル価格交渉するために時間をかけては、まったくその価値がなくなってしまいますよね。それがインターネットならばより効率的にワンストップで販売できると。これはお客様にとっても価値になるんじゃないかというのがビジネスモデルの着眼点だったと思います。

通販カタログ(年2回更新)
編集部:
当時の製造業のお客様にとっては、これで資材の調達が楽になるぞと喜ばれたと思いますが、いかがでしたか。
鈴木社長:
2000年当初は、お客様がインターネットを通して探すという習慣がなかったので、やはりカタログ、チラシ、FAXという媒体が強かったですね。今は約26万商品を在庫し、翌日までにお客様にお届けするようにサービスも良くなっていますが、当時は電子カタログも、そもそも在庫も物流センターもありませんでした。まずはインターネット販売できる体制を作って、次に仕入れ先を見つけに行って、という流れだったので、お客様からすると、アイデアはいいし商品もあるけれど、まだ価格は高いなとか、そういった印象だったと思います。ですから受け入れられるサービスレベルの事業を築くまでに、たぶん2年以上かかっていたと思います。だんだんとお客様を獲得していきながら会社の規模を大きくしていったのが最初の5年間だったと思います。
編集部:
そうした試行錯誤を繰り返されながら、今ここまで成長されてらっしゃると。
鈴木社長:
本当に試行錯誤っていうのは、毎日いろんなところにあると思うんですね。おかげさまで事業規模も少しずつでもここまで大きくなっていますが、社会全体のシステムやテクノロジーの速度、もちろん競合もありますし。周りの世界も同時に変わっていく中で、いかにお客様に自分たちを選んでいただくかということのためには、いつも試行錯誤とチャレンジだと思っています。
間接副資材というニッチマーケットで日本一
編集部:
今もチャレンジは続いているということですね。
ではここで、製造業のコンサルティングを行っている片山にもお話しを伺います。片山さんは、モノタロウさんのビジネスはどのように見られますか?
片山:
はい。私はまさに2000年くらいから御社の生い立ちをずっと拝見しているんですが、率直にお話ししてもよろしいですか?
鈴木社長:
どうぞ。
片山:
先ほどモノタロウの設立が2000年10月とおっしゃられましたけど、実は2000年から2003年の7月まで景気がすごく悪かったんです。まさにITバブルが崩壊した時期で、アメリカでBtoB通販をEコマースでやっていたようなドットコム企業が軒並み潰れました。市場規模的にネット通販の世界もBtoBよりもBtoCが大きいというのは数字としては出ていて、アメリカでも鉄鋼や自動車部品のネット通販会社がどんどん出てきたんですけど、ほとんど潰れてしまいましたね。
鈴木社長:
ええ、マーケットプレイスですね。売り手と買い手をつなげるために、これまで電話でコンタクトしていたものをインターネットというネットワークに乗せるというビジネスアイデアに、ものすごく巨額な資金が投下されてきた経緯がありましたけど、今はアメリカも日本も、ほぼ残っていないんじゃないかと思いますね。
片山:
モノタロウさんの凄さは14期連続増収ということと、日経ビジネスにも取り上げられていますが、世界企業で第9位と。日本だとNo.1ということです。では業界は伸びているかといえばそうではなくて、頭打ちといわれる製造業の、いわゆる間接副資材というマーケットで、世界で戦える日本一の会社になられている。これは凄いことです。
おそらく皆さんは、それはインターネットだからだろう、物量作戦だろう、と当たり前のように思われるかもしれないけども、実はBtoBのマーケットプレイスや通販というのは凄く難しいです。
鈴木社長:
はい。
片山:
賛否両論あるかもしれませんが、僕のコンサルタントとしての経験値でお話しさせていただくと、店舗販売と通販なら、僕は通販が勝つと思っているんです。ところがBtoBですからルートセールスが必要になる。では通販と人的販売が勝負したらどっちが勝つかといえば、僕の経験では人的販売なんです。

プライベートブランド商品も多数ラインアップ
片山:
今、日本には会社が約400万社あると言われていて、製造業がそのうちの1割で約40万社です。経済産業省が工業統計を出していますが、実は従業員4名以上のところしか出ていません。4名以上の工場で20万~22万社あると言われていますから、残りの半分はデータが出ていないわけです。
対して、機械工具商社、販売店、問屋が約1万社あります。その販売店や問屋の営業マンが全国津々浦々の製造業に訪問していますが、彼らは従業員が数名のところには行きません。なぜなら売上の元が取れないから。だから大手企業で1,000名とか、中小企業で300名というところに一生懸命行くわけです。ではどうやって間接副資材を調達していたかというと、個々に工具屋まで買いに行っていたんです。とはいえ工具屋はルートセールスが主業態ですから、こうやって買いに来る現金客が迷惑でもあった。
鈴木社長:
そうですね。
片山:
日本の製造業は、従業員3名4名というようなガレージ企業のようなところが支えていて、そして彼らはすごく困っていました。例えばベアリングを1個買いたいと言っても工具屋は来てくれないし、買いに行ったら高かったり、3日とか待たされたり。そんな中でモノタロウが現れて、「えっ、こんなに安いの?!」「スグ届くの?!」と。夢のような話ですよ。でもそれは既存の勢力、業界の問屋やメーカーからすれば、「おいおいカンベンしてくれよ」と。今まで値段を伏せていたのに、そんなにオープンにして、どえらい迷惑だということで、圧力をいろいろかけた時期があるんです。あれはいつ頃でした?
鈴木社長:
2001年、2002年くらいですね。
その、ベアリングを1個くださいと現金を持って来るというお話ですが、実は取引のためにかかるコスト、トランザクションですが、人件費という面においては1個でも100個でもあまり変わらないんですよね。けれどもBtoBでセールスマンを通して販売する以上は、顧客によってその価格が違う、商品が違う、量が違うのはあたりまえなんです。取引に対してのコストと考えれば、当然といえば当然なんですよね。そこで我々は、アウトバウンドでお客様のところにルートセールスに行かなくても、カタログやチラシ、FAXを通してお客様を獲得してきました。
今はネット上でいかにお客様に見つけてもらえるかに注力することで、毎月4万近いアカウントを獲得できています。世の中のネットワークもどんどん変わっていく中で、自分たちが人とは違うお客様へのアプローチ手段を見出すことで、通常のセールス形態ではアクセスできないようなお客様に対して、コストを安く到達できるようになったというのが一番の大きな理由だと思います。
片山:
モノタロウは、社名を住商グレンジャーからモノタロウに変更されましたよね?
鈴木社長:
2006年の上場前に変えました。
片山:
モノタロウにされた理由は、MROの頭文字で?
鈴木社長:
もともとは「モノタロウ.com」というサイトで、モノタロウというドメインは当初からあったんです。会社として一番大事なことは何かといえば、お客様がその会社のことをどれだけ信じられるかということなんですね。先ほど片山さんがおっしゃったような、フェイストゥフェイスでない販売チャネルが抱える問題は、その会社のことがよくわからないという理由が結構多いと思うんです。それもあって事業の立ち上げ時には住友商事と、今の親会社でもあるグレンジャーの名前を使いました。だんだん規模も大きくなっていたところで、やっぱりモノタロウという名前をより理解してもらうために変えました。
片山:
そうでしたか。

メインとなる物流センター
営業ゼロ、紙媒体を重視するこだわり
編集部:
では次に、先ほどインターネットのサイトやカタログで、今も試行錯誤されているとお話しくださいました。工夫されているのはどういった点でしょうか?
鈴木社長:
お客様にとって適切な商品を表示して提供するということは、どの媒体においてもかなり努力が必要です。インターネットやダイレクトマーケティングにおいては、通常のセールスルートでたどり着かないお客様のところに到達できるという利点もありますが、やはり弱点もあります。例えば、商品に対するお客様の理解が浅いですとか。ネット上では購買を促すようなプッシュする行動はできませんし、提案営業は、やはり人が強い。そういう面では、これまでお客様が購入されてきた商品や、お客様の事業など、数々のデータを分析・解析することで、まだまだこれから発展の可能性がありますし、やるべきことだと思いますね。
編集部:
インターネット上において、人によるセールスに近いところまでサービスの精度を高めていきたいと。
鈴木社長:
例えば実際に人が動かなくても、今ならスマホがあればスカイプだとかフェイスタイムが使えますよね。それを乗り越えるテクノロジーがすでに世の中にあるわけです。一番非効率なのは、人件費がだんだん上がっていって、さらに人が移動するというコストですよね。だから訪問することに時間やコストをかけられなくなってくる。人が移動しなくても、すでに深いコミュニケーションをはかる手段があるんですから、それらをもっと活用すべきではないかなと思います。
片山:
BtoB通販は、通販といいながら、実は結構な営業人員を抱えている場合があります。例えば業務用食材を扱う企業などです。とくに食材は口に入るものですから、人が行って補う必要が出てくる。やはりBtoB通販でも営業が不可欠かと思われる一方、モノタロウでは営業活動が一切ありませんね。
鈴木社長:
当社のサービスをプレゼンテーションする担当者はいますが、いわゆるルートセールスは一切ないです。もともとの事業が、インターネットを活用してEコマースしますというところからのスタートでしたので、セールスマンありきの通販スタートでなかったことは、むしろラッキーだったかなと思います。
当社がセールスをするならば、セールスっていう機能は何ですか?というところからもう一度、分解しなければいけないと思います。なぜ行くのか?どういう信頼なり役割をお客様に提供できるのか?どのようなコミュニケーションが必要なのか?必要があるとすれば、今度は移動時間がかかってくる。それをどのようにして削減できるか、乗り越えられるか、他と違うチャネルを提供できるのかを検討しなければいけないと思います。
片山:
なるほど。ありがとうございます。
鈴木社長:
ここ数年は新たな領域として、大手の企業向けに商品を提供しています。その中でプレゼンに行くことはあります。これは大手の企業内の購買システムにモノタロウの商品データベースをリンクしてもらうというやり方で、社員の方は社内承認等のワークフローを活用して当社に発注していただくと。すると請求や決済が一本化されて、各事業所の担当の業務量も大きく削減できるという試みです。

オフィス風景
編集部:
インターネットの販売サイトを始め、物流など、すべて内製化されているということに、とても驚きました。
鈴木社長:
創業当初から、システムや物流に関して、ほぼ内製しています。
正社員が国内で240~250名います。役割でいうと、大きな組織では商品仕入れ部門と、約1,000万点という商品情報を追加・改良していく役割の商品部門に、60~70名ずついます。それとITエンジニア部門、年間20冊のカタログを発刊している制作部門があります。
もちろんまったくアウトソースがないわけではなくて、例えば会計システム。これは世の中のルールに則ったシステムをパッケージとして使えばいいと思うんです。ただ、独自性を出す必要がある、競合なり世の中において価値を創出するポイントだと思うところは、やっぱり自分たちで作り上げることによって価値が発揮できると思います。いろいろな学びを見つけることで機能は進化しますし、コストは抑えられるという信念はあります。
編集部:
むしろ内製化することでコストが抑えられ、独自固有の価値の最大化ができるメリットがあったのですね。
鈴木社長:
一般的にはアウトソースした方がコストは下がるという話もあるけど、それは全般の領域においてではないと思います。物流もITも、いかに自分たちのオリジナルの方法でコストを下げるかだけでなく、よい生産性、よりよい機能を発揮するためには、絶対に自分たちでやらなきゃいけないと思うんですよね。
片山:
そういう中では、先ほどお話にあった紙のカタログですが、紙はコストが掛かるから減らそうという声が多くなる中でも力を入れている理由は何でしょうか?

副資材、間接資材の調達に中小零細企業から熱い支持
鈴木社長:
紙のカタログの一番のメリットは、新商品を認識いただくことと、他商品との比較だと思います。必要な商品が具体的に決まっていない段階でお客様がカタログを見たときに、今はこのメーカーを使っているけど、こんな商品もあるのかとか。例えばモノタロウのPB商品やオリジナルブランドを使うと値段がこう違うとか、こんな機能があるということを理解いただくためには、今のところまだインターネットよりも効果があると思っているので、紙は必要だと思いますね。
片山:
御社のカタログを見ていると楽しいですもんね(笑)パラパラ見るだけでも読み物みたいな感じで。
鈴木社長:
ありがとうございます。とはいえ、ほとんどお客様の初めての接点はインターネットです。いろいろ検索いただいて、モノタロウを知る。全部トータルに総合的に考えて、これでいいや、注文しようと判断ができて、初めて取引がスタートする。その時点でお客様の業種は入力いただきますし、また、お客様がその商品を購入するまでの間にどんなページと商品を見られたのか、そのデータをもとに過去の似たようなお客様と比較して、今回はこれを購入されたけれども、実際はこの商品も使っているはずだから、この商品のカタログも送っておこう。そういうことはしているんです。ここは営業活動といえるかもしれません。
片山:
なるほど。
鈴木社長:
先ほどの話に戻ると、営業マンによるセールスに近いところはシステムで代替していると言えますね。4名以下の会社を訪問することが割に合わないと言っていた世界が、インターネットを通して新たな市場に変わる。人が一番得意としているところが機械学習によって可能になるという意味では、そのツールであるカタログは重要な媒体だと思います。
社員とのアナログなコミュニケーション
編集部:
世の中やニーズが変わっていき、新しいことにもチャレンジされる中で、社員のスピード感というところも大事になってくると思います。何か取り組んでいることはありますか?
鈴木社長:
はい。新卒社員も受け入れられるようになってきて、今30~40名くらいいます。つまり、この4年で社員数が倍になったわけです。ここで一つ大きな課題となるのは、皆が一生懸命に働いた結果が、いかに会社の方向性や、新たなサービス、価値のあるものにつながっていくのかを明確にできるかどうか。組織のあり方や仕事への取り組み方、結果につながるような働き方をしていけるように注力しているところですね。
編集部:
具体的にはどのように?
鈴木社長:
グループでも個人でも、それぞれの領域の中で、まずはどんなコミュニケーションをとるかが重要ですよね。単に作業するだけとか、社長が言っているからやるのではなくて、何を目指していて、どんなゴールを描いているかを、皆が理解できるように説明することは重要だと思います。
世の中の動き、サイクルが加速する中で、ただ変化に対応するだけでは、自分たちのアイデンティティーはなくなってしまうと思います。行く先の変化が速かったとしても、少なくとも自分たちの方向性や指している姿は理解しないと、絶対にうまくいきません。一生懸命走っているけど、どこにたどり着くのかわからない、そういった危うい速さは違うと思います。
編集部:
それを何かのタイミングでお伝えしているのでしょうか?
鈴木社長:
月に一回、全社員が集まって話すタウンミーティングという場があります。あとは私自身、全社員とワン・オン・ワン、一対一の個人面談を年に二回しています。また、リーダーは各メンバースタッフと、週に一度、ワン・オン・ワンコミュニケーションをしています。
片山:
これだけの人数で年二回の個人面談とは、相当大変ですね。
鈴木社長:
一人当たり約15分です。朝から晩まで一生懸命やっても30人くらいしかできないので、8営業日くらいかかります。
編集部:
それだけの時間をかけてでも、大きな方向性を示していくべきだと。
鈴木社長:
そうですし、逆もそうだと思うんです。私だけでなく、各リーダーは声を吸い上げなきゃいけない。聞かなきゃいけない。社員には言ってもらわなくてはいけないんです。実際にやってみたら、こんな気づきがありました、発見がありました、もっとこうしたほうがいいですよ、そういう声をちゃんと聞いて、それを皆で共有して、ならばこうしようという積み重ねが、先ほどお話しした試行錯誤につながると思うので。
編集部:
意外にアナログなところにあったんだなというのが…
鈴木社長:
そうですね。創業当初から会長の瀬戸も言っていることですが、社員に一番求めることは、お互いに敬意を払うということなんです。会社の中にはいろいろな仕事があって、それがどんな持ち場であっても、お互いの仕事や存在に敬意を払う。そうすることで、会社にとって最適な判断というのは何であるのか、今のグループ、チームにとって、今掲げている目標のために必要な判断とは何であるのかということを、全社員が考えてもらえるようになれれば、それは本当に強い力を発揮するのではないかと思います。
片山:
鈴木社長のおっしゃることは、とても合理的だと思います。私もコンサルティングをする中で、例えば従業員30名40名といった中小企業でも、社長が全社員と面談されている会社って、実はものすごく少数派です。やはり時間もかかりますし、面談はする側もされる側も大変ですからね。
鈴木社長:
ええ。ただやはり、働いていて幸せを感じるか、自分の仕事ぶりがちゃんとその会社の中で評価されているか、これはもちろん金銭的な報酬のこともありますけど、会社という社会の中に存在するにあたって自分が満足感を得られるのかどうかはモチベーションにつながると思います。ですから面談は社長として優先順位ではかなり高いほうにあります。いろいろな仕事があってもやり続けるべきことと思っています。
編集部:
やはり、起点は人だったということですね。
鈴木社長:
はい。やっぱり結果を出すのは人ですし、チームですね。トップセールスマンがいて数字を上げていくという組織ではありませんので、そういう意味では営業を持たない組織としてチームはすごく重要なポイントです。会社は長続きしなくてはいけないし、長く続くことで、より安心できる会社、働く社会の場として存続し続けるべきなので、そこはすごく重要だと思います。
編集部:
ありがとうございます。では最後に、今後の目標や夢を教えてください。
鈴木社長:
一番は、より多くの人が仕事や社会、世界に対して満足できるようなきっかけが与えられるような会社でありたいし、個人でありたいというふうに思っています。そのためには会社が長続きしなくてはいけないですし、どうすればお客様に長く支持いただけるかを常に考えていきたいです。そして、社員の皆さんには長くこの会社で働いていただかないといけないですし、そのためには会社として成長を、個人として成長して考え続けなければいけないだろうなと思っています。
編集部・片山:
ありがとうございます。今日は貴重なお話をありがとうございました。

取扱い商品数950万点を超える販売サイト
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度