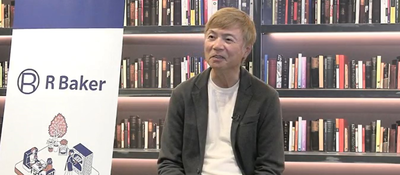横山:
船井財団主催『グレートカンパニーアワード 2015』において「勇気ある社会貢献チャレンジ賞」を受賞された恵那川上屋の鎌田社長にお話を伺います。
生産、加工、販売の一気通貫で、恵那栗のブランド化とともに地域の活性化に貢献されています。農業生産法人をつくり、栗農家の方と契約栽培をされることになったきっかけをお聞かせください。
鎌田社長:
はい。僕は実家が菓子店だったことで、高校を出てすぐに、東京の洋菓子店へ修行に行きました。
あるとき百貨店で、秋になると栗きんとんが出ていたので、あるお菓子屋さんの栗きんとんを買って食べたんですよ。岐阜県恵那市は栗の産地なんですが、僕が昔食べた栗きんとんと、ちょっと味が違うかなと感じたんです。なんでだろう?と思いながら、修行期間が終わりました。
田舎に帰って、親戚の和菓子屋さんを手伝わせてもらっているうちに、栗の流通事情がわかってきたんです。栗きんとんが百貨店で売れるようになったとき、地域の和菓子屋さんはどんどん進出していきました。老舗から順番に出店し、ものすごく成長していったんです。でもその裏で何が起こったかというと、生産者が20㎏30㎏の栗を持ってきても足りず、いくつもの農家から集めたところで品質もばらばらになりますから、地元の栗を買わなくなってきた。要は、栗きんとんが売れれば売れるほど、地元の栗はほとんど使われなくなったんです。
横山:
そうでしたか。
鎌田社長:
修行時代に味が違うなと感じたのは、そういうことだったんです。栗は少ない量で炊き上げるのと大量に炊き上げるのでは味が違いますし。ましてや大量にとなると、市場にはだいたい燻蒸(くんじょう)して入ってきています。燻蒸は、虫を殺すための薬をちょっと使うんですよ。品質にも関係してきますよね。
僕の父が坂下町というところの出身で、そこにはそれぞれの地権者がいる栗の団地がありました。そこでとてもいい栗の栽培方法をされていたので、うちの和菓子屋と契約しようと決まりました。それまでは農家はどうやっていけばいいかと模索していたし、後発の僕らは老舗には勝てないだろうし、お互いが困っていたんです。だから、お互いの価値を交換することにしました。僕にはお金とモノの交換という発想はなくて、お互いにいいことをすればいいなあって。

<グレートカンパニーアワード2015> 勇気ある社会貢献チャレンジ賞
すべては「価値」の交換
鎌田社長:
農家は、相場ではなくて手取りという単位があります。あれこれ引かれて100円か200円になってしまうんです。市場で600円で売れたとしても、本人の手取りは200円くらいしかない。ならば、600円という約2倍から3倍の値段をつけて、そのまま農家に返せば同じことですよね。そうやって、ほとんど手取りが取れる仕組みを作ってあげられたらいいなあと。ロジスティクス自体を変えてしまうということです。その代わり品質に関しては塚本先生という栗の博士に頼んで、農家を統制していくような形になりました。
最初は、理念とかいろんなものを作っていく中で、三者が喜ぶ仕組みづくりをやろうっていったときに、いきなり三者って儲からないんですよ。
横山:
三者は、生産者と販売とお客様ですね。
鎌田社長:
そう。まずは生産者が喜ぶ仕組みを確立させようと。それに5年か6年くらいかけましたね。当時、年商1億円くらいでしたから、栗きんとん用の栗も間に合うくらいでした。ではどうやって売上を上げていくかと考えた時、勝負に出たのが恵那峡に作った本社です。土地を買って本社を建てたら、全部で4億くらいかかってしまいました。1億の売上で4億借金するなんてバカげたことを(笑)僕は職人でしたから財務を知らなかったですね。まったく無知でした。オヤジもよく許したなと思いましたね。
横山:
売上を伸ばすための勝負と(笑)
鎌田社長:
ええ。でもそれがあったから必死でした。借金を返済するために百貨店をたくさん回って、1年で、20数店で売りました。
ある日、東京の繁華街の地下商街で売らせてもらえることになって、こんなありがたいことないなと思って売りに行ったんですけど、一日5万円も売れませんでした。帰りに商品を廃棄する時にはひどい罪悪感で、百貨店での商売をやめ、結婚式場などの卸もやめました。その時気づいたのは、地元で何の評価もされていないのに、百貨店で売上を作ろうとしているんです。「何で俺は外で売ってるんだ。これが大きな間違いだ」と思ったんです。
横山:
なるほど。
鎌田社長:
地元でブランドをつくろうと話をしていた時に指摘されたのは、「お前はお金の話しかしないな」ということでした。返済しないといけませんから当然ですが、これは間違っていると気づいたのです。まずは農家に自信を付けさせることと、地域の自慢をつくることが必要なんだなと気づきました。
横山:
ええ。
鎌田社長:
例えば農家さんが「これちょっとあれだけど、加工ならいいと思うから使ってくれ」というのではなく、「絶対旨いから食ってくれ」っていうのを僕らは加工したいんです。それから地域の自慢とは、いろいろな商品を開発していく中で、今から100年先でも残っているような栗きんとんを作っていくのが僕らの仕事だと思ったんです。そのために、まずはどの農家の素材を使っているかが見えるようにするなどしました。
僕が狙っていたのは生産者の自主性です。利益を追わずに生産者が儲かる仕組みに注力していました。そして、いいモノをつくろうという生産者の誇りを取り戻します。そうすると、いいものを作ったら値段が上がるといういい循環ができてきたんです。そのうち農家に「ダメだと思ったらスグ処分」っていうキャッチフレーズができたほどです。農家さん自身がいいものを作りたいと思うこと、それが大きな狙いだったのです。
横山:
自分たちの中で、もう一回、自信を取り戻していただこうと。
鎌田社長:
そうです。恵那に住んでいるのが自慢になるような、そういうものを育てようよと。だから徹底的に商品開発をします。今までで1,200以上は作ってきたと思います。その中で残っているのが200くらいで、売れているのは2、30だろうと思います。やればやっただけ返ってきました。
農業法人をつくる
横山:
農家の方にまず儲けていただくという仕組みを作る中で、恵那川上屋も順調に大きくなっていかれました。企業成長と、原料となる栗の供給バランスについては、どう進めていかれたのでしょうか。
鎌田社長:
この取り組みを始めた頃、農家の平均年齢は65歳でした。僕が危機感を感じたのは20年後にはもうないなということです。その時、「僕たちは会社を潰さないし、生産者は跡継ぎをつくる」と約束したんです。今、その20年が経ちました。でも、まだ半分くらいしかできていないですね。まず農業法人をつくったんです。廃業していくところを引き受けていって、とにかく減らさない。それを維持しながら技術を磨いていくようにしました。
横山:
なるほど。
鎌田社長:
難しいのは、農業法人でリーダーを決めても、なかなか続かないんですよね。利益を生まないからです。商売としての農業法人として考えなかったので、そこで働く人たちのヤル気とか希望とか夢が生まれなかったのです。つまり農業から販売までのことは、サプライチェーンなんですが、これを他の地域に持って行って展開した場合はバリューチェーンに変わりますよね。そっちだな!って思って。
この、技術と生産者とのつながりをひとまとめにして、商品別に産地化しちゃおうと決めたんです。例えば恵那栗は栗きんとんに使おうと。恵那の生産者は、栗きんとんをつくるための栗を作っているわけです。あとの産地は、例えばむき栗のための栗。そういうふうに加工や産地で分けていきながら、その資源を蓄積するためにいろいろな地域を飛び回ったんです。

地元の栗農家の方々
横山:
最近では日本各地で、6次産業化や農業による地域活性化が聞かれるようになりました。とはいえ、うまくいかない地域もある中で、鎌田社長が地元の恵那やその他の産地、または農家の方と一緒に進められた、成功のポイントとはどのような点でしょうか?
鎌田社長:
連携と融合という言葉がありますね。例えば融合というのは素材どうし、連携というのは資源の交換をするんです。
これ実際にあった話なんですけど…。僕は長野の松本が好きで、松本の居酒屋に通っていたら、そこのオヤジが「オレはこの店に来るやつで好きなやつが二人いるんだ」とポロッと言ったんです。「一人はお前だ」って言ってくれて。「ありがとうございます。もう一人は誰ですか?会わせてください」って言ったんです。そしてその人と一緒に飲むことになって。
彼は僕と同じ年齢でしたね。すごく苦労されていて、お兄さんと二人で掃除から始めて、長野でビルメンテナンスの会社をしていました。その彼がポロッと言ったのは、「今まで自分の仕事ができなかった」と。好きな仕事をしたいと言うので「農業やりませんか?」って言ったの。栗やりませんかって。やらしてくれるか?ってところから始まりました。そしたら、たまたま彼の友達が長野県の安曇野でりんごを作っていて、その人の空いている土地に栗を植えたんです。
横山:
ええ。そこがスタートですか?
鎌田社長:
「安曇野栗」というブランド栗を打ち立てたんです。仲間が集まってきて、大町(長野県)の農業委員会も集まって、二つの地域でやることになりました。
僕は生産者と一緒に、「どうやっていこうか」と話をします。さらには商品開発ができるという資源を持っています。ビルメンテナンスの彼は地元に強い。りんごを作っていた彼の友達は農家を束ねるのが強い。そうやって資源を連携していけば、産地はうまくいきます。僕が好き勝手にやるわけじゃなく、社長は彼です。彼が有利なのは、お菓子屋さんに売れるんですよ。
横山:
お菓子屋さんに売れるというと…
鎌田社長:
僕はお菓子屋さんですから、加工したものを僕が売るのはちょっと違う。でもビルメンテナンス業の彼が売れば問題ないですよ。彼が加工所を立ち上げればいい。彼から栗を買ったお菓子屋さんは、安曇野栗で新しいお菓子を作ればいい。だから、資源というのは何か?を考えて、全部強みにしていくんです。その融合とか連携っていうのは、やっぱり地域の活性化も含めて行わなきゃダメですね。みんな喜ばなければダメですから。

「安曇野栗」というブランド栗を空いている土地に栗を植えた
恵那を越えた展開
横山:
鎌田社長は地元の恵那を越えて、全国各地にそのような展開をされていますね。
鎌田社長:
展開するには、まずは横の関係づくりが必要です。例えば、飯田町というところに栗農家の団地を作ったんです。地権者が45人いて、全員が出資して栗農家の会社をゼロから作りました。栗農家100人で1年に45トンくらい採れ、息を吹き返しました。
彼らは農業者出身ですから、農業の経営に関しては長けています。剪定や農作業が早い。農協出身者も入っていますし、おそらくその会社は黒字化しますよ。そうなってくると、代表は変わっていけばいいし、跡継ぎは関係なくなります。今このような会社は2箇所にありますが、それぞれが教えていきながら連鎖していきますよ。
横山:
かなり戦略的ですね(笑)
鎌田社長:
ひとりでも「やるぞ!」っていう人がいればできます。飯田町の町長は、「このままではダメになる。もう一度、農業生産で目玉になるものを作っていきたい」っていう狙いがあったんです。そこで『栗の里構想』っていうのを打ち出しました。
横山:
町長の狙いと合致したということですね。
鎌田社長:
そう。やはりそれも「価値の交換」ですよ。だから、モノやサービスとお金の交換ではないですよ。みんなが何を求めているかっていったらお金の豊かさもあるけど、働く楽しみはお客様の感動とかなんです。
僕は、震災時のボランティアも価値の交換だと思うんです。ボランティアをしたい人とボランティアを受けたい人がいる。これ、価値の交換です。以前、被災地の友人に車をあげようと、会社のスタッフと一緒に車を持って行ったことがありました。うちのスタッフは僕を社長だと思っていますから、上下感をもっていますよね。でも現地の人とは一人の人間として向き合っていますから、関係ないんです。それが人間の本質ですよね。自分たちが上下を勝手に決めて、そこで権力とか権威とか言っているだけじゃないかと。「ひと」の間で生きている、本来、それだけです。だから、持っている資源という価値をどこで交換するか、それだけです。それが有効に使われれば、お客様がお金を払ってくださるだけだと。僕はそう考えてますね。
売上10億のときに見えたもの
横山:
なるほど。そうするうちに、恵那川上屋は売上も伸ばされたのですね。
鎌田社長:
いつの間にか20億ですよね。本当にコツコツっていう感じがします。でも10億くらいの時が一番利益が出たんじゃないかな。
実はね、20億になってからとても悩んだんです。この時の4~5年、社長に向いてないって思って悩みましたよ。僕は高卒だったし勉強していなかったんです。勉強って知らないことを知ることですよね。だから知らないままでいると不安になる。これが原因だと思って、マーケティングを学ぶために明治大学に2年間通ったら、いろいろなことがわかってきました。ここからのステップを論文にしようと思ったんです。未来の、50年先の自分をデザインしたいと思ったんです。でも結果はひとつしかなかったけどね。
横山:
それは何ですか?
鎌田社長:
何年たってもお客様はお客様だということです。お客様がお店に通い続けられる風土が会社に創れるか?ということですね。社員が自分都合で考えていることには、僕はものすごい叱るんです。その代わり、それ以外は何も言わないです。
横山:
なるほど。
社員に伝えたいこと
横山:
会社が成長していく上で、恵那川上屋と農家とのつながり、素材、風土、この地元ということはもちろんですが、商品開発、技術力、加工力には当然、社員の力もあると思うのですが。
鎌田社長:
最初の頃は、これをやってほしい、とお願いするだけで十分でした。でも組織を変えなきゃと思ったとき、それではダメでした。一番重要なのは、農家でやった自主性で、そこを育てないと正しいところに行かないと気づきました。
現代は、「言われたとおりにできました、ほめられました」という時代ではないです。それに、そういう会社でもないです。支え合って助け合う風土を作りたいと思った時に、自分たちが率先して決めて意思決定して行動して、反応を見て、反省して、次のステップを決めることが必要になるわけです。今、僕が決めるのは方向性だけです。
横山:
社員たちの自主性をとおっしゃっていましたが、それを発揮するために工夫されていることや取り組まれていることはありますか?
鎌田社長:
一番簡単なのは、僕が会社にいないことです。社内にいるよりも、外の情報を集めてきてみんなへのフィードバックをやったほうがいいですね。ただ、お客様目線の客観思考性、環境整備、それから支えあって助け合う風土を作りたいというこの3つだけはものすごく意識しています。これを中心にみんながどう動くかっていうことしか僕は見てないですね。
毎年お祭りをやっているんです。
横山:
1日に6,000人集まる、お菓子屋さんの業界であんなに集まるイベントはないっていうくらい大きなイベントですよね。
鎌田社長:
ええ。あるとき委員長が「俺らが楽しい祭りがしたいんだ!」って言ったのでひどく叱ったら、半年間、僕の傍に来なかったですよ(笑)半年くらいしてやっと僕のとこに来て話すのを聞くと、いろいろ考えるようになっていましたよ。なぜ僕がそう言ったのか?というのを理解してくれれば、いずれわかると思うんです、社長はこのことを言っていたのかって。僕は僕の考えを言い続けることしか手がないんです。教育だからと変な押し付けをしても嫌がるし、自分で気づいてほしい、そこに重点を置いています。生産者と一緒です。

支えあって助け合う風土作り
横山:
人の採用についてお伺いします。
岐阜県恵那市にありますが、何か工夫されていることがあればお願いします。
鎌田社長:
田舎が不利なのは、人を募集するにはハローワークしかないことです。だからみんな都会に出ていきます。そのため募集のやり方をNPOの人たちと話して変えようとしているところです。これからは田舎にいていい仕組みを作らないとダメだと思うんですよね。それをどうやって実現するか、具体的に考えているところです。
狙っているのは、やっぱり基本的な概念とか、会社のプラットフォームみたいなのをきちんと伝えてあげること。田舎に住んではみたけれど、仕事がどうもあまりおもしろくない、そんなのダメでしょう。
横山:
なるほど。
鎌田社長:
先日も新宿の駅ビル施設の方が来たんです。田舎と都会を、それも若い女性が結ぶようなことをしたいと言っていて、NPOの人たちが2日間一緒に観光して、えらい感動して帰ってくれたんです。例えば、これを田舎のNPOが旅行代理店やってあげれば、みんな満足できるんじゃないかなって。人との関係もつくれるし。つなぐ人とつなぐ場を得れば、田舎でもいけるんじゃないかと思うんです。ドラえもんで、のび太やジャイアンが集まる土管公園みたいな場所、ああいう場所があれば人は集まってくるんですよね。
というのは先日、『岐阜ナイトin Tokyo』というのを東京の神田でやったんですよ。100人以上が集まったらしいです。何もしていなくても、岐阜ナイトやるぞ!というだけで岐阜好きの人や出身者が集まってくるわけですよね。NPOの人たちが東京に行って、こういう活動をしていると話しながら、おそらく飲んだだけだと思う(笑)でも集まるんだよね。
横山:
ちょっとしたコミュニティーというか。
鎌田社長:
そう。コンセプトがしっかりしていれば人は集まる。それは田舎でも同じ。
この間、大学生のインターンを募集したら10人くらい来たんです。彼らは何かを求めて来ていて、僕らは栗拾いをしてほしかった。だからそこの交換をしないか?と持ちかけた、まさにそれなんですよ。
よく、田舎を都会にするって表現しますけど、都会の人がうらやむような何かを価値として見つけていければいいですね。その価値をつくることの方が、ビルをたくさん建てるよりも意味があることのような気がしますね。
横山:
なるほど。
鎌田社長:
だから僕はそういう考え方です。組合だとか横のつながりではなくて、栗を食べるのが好きな人、作るのが好きな人、加工するのが好きな人、栗にまつわる人たちが横につながっていて、それぞれが一緒になればいい。でもその先にはお客様がいてタテのつながりもある。タテと横がクロスして、それが本当の意味で固まればいいと思います。

農家が自信を取り戻す高品質の栗が地域の自慢をつくる
業態の再定義
横山:
鎌田社長は折に触れて、自分たちは何屋かということを再定義するのが大事だとおっしゃいます。今の恵那川上屋は何屋になるでしょうか?
鎌田社長:
サプライチェーンを効率化して農家に還元しますよね。その仕組み、バリューチェーンを活かしていく、そういう会社だと思います。だから菓子製造業ではないですね。
今、6次産業化って言われているでしょう?そのためには、その素材はだれが求めていて、何に喜ばれるのか、というのがわかっていないとダメだと思う。何屋かっていうのは、実は組み合わせだけで変わるんですよね。ITって言葉も今は当たり前ですけど、昔はなかった。だから6次産業化の次は8次産業化かもしれないし、12次産業化まで行く人もいるかもしれない。これからはそうなるだろうと思います。福祉とお菓子をつなげるとかね。
連携と融合が大事だと言っているのは、これからはたぶん、そういった隙間を掛け合わせていくような人が出てくると思います。僕らは原点から何も変わっていないです。
横山:
世代が変わっても、そこは変わらないと。
鎌田社長:
いいものしか出さないということです。今の超特選恵那栗部会のメンバーたちとの共通の理念は「美しく生きる」。それを言い続けます。だから全部の情報と戦略をみんなで共有しますよ。本当は発表しちゃいけないかもしれないけど(笑)それでまた夢を持てれば、「あっそうだ、俺、このためにやってたんだ」って思えますよね。これができなければ6次化なんてやっても無駄だと思うんですよ。
それと今、関東のお客様が増えたなという実感があったこともあって、一度は止めた百貨店への出店を始めています。その際に、過去、一日5万円も売れなかった東京の地下商街のところにもう一度お願いに行ったんです。そうしたら春の催事では40万円くらい売れました。秋の催事の時はみんな総動員で行くぞ!って(笑)一日100万円くらい売れましたね。その時は涙が止まらなかったです。地域の自慢って、そういうことですよね。自信があるところ、そこをこつこつやるしかない。売上って本当にこつこつしか上がらないです。
横山:
なるほど。おっしゃるとおりです。
鎌田社長:
あと変えるとすれば、深くする。例えば店舗をセレクトショップ化するとか、今の時流に合ったものにしなきゃいけないなとは感じています。コミュニティーができるような空間を広げるとか。そういったところが変化すれば、もしかするとお客様の感じ方も違ってくるかもしれませんし。
未来にのこすもの
横山:
では最後に。先ほどおっしゃっていた、未来の、50年先の自分、そして恵那川上屋についてお聞かせください。
鎌田社長:
やはり、育てていく、ということです。資源が蓄えられる場所という意味では、健全な赤字部門に投資することも重要です。
例えば、種子島では2、3人しか黒糖を作る人がいないそうですが、うちには7人います。それは文化を伝承できます。だから栗きんとんもそうですね。資源さえ入れば最初は赤字でもいいんですよ。その資源を1000年先に、ないかもしれないけど1000年続けようぜ!って言ったときに、自分に残された仕事、与えられた仕事は何かなと思ったら、やっぱり原料の確保です。そこだけなんとかしてあげれば続く可能性ができますし、その可能性、あるかな?ないかな?って考えた時に、ないなら自分でやるしかない。だから僕のこの先の仕事は何かって言ったら、お菓子を売っていくことでもなんでもなくて、原料になるものをうまく将来のために作り上げておくことなんです。
いいものを作り続けますし、だから日本一高い栗になりますよ(笑)そのためにどうするかってことしか、僕は考えていないです。
横山:
そこは変わらずやり続けると。
本日は貴重なお話をありがとうございました。

一つひとつ手作りの栗きんとん
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度