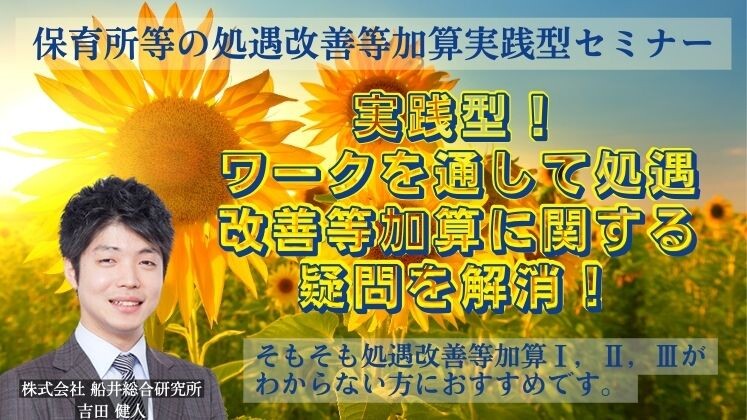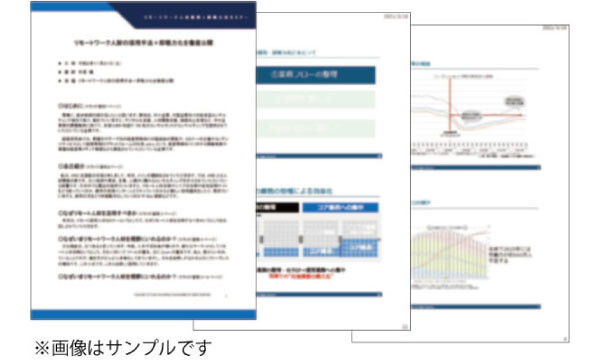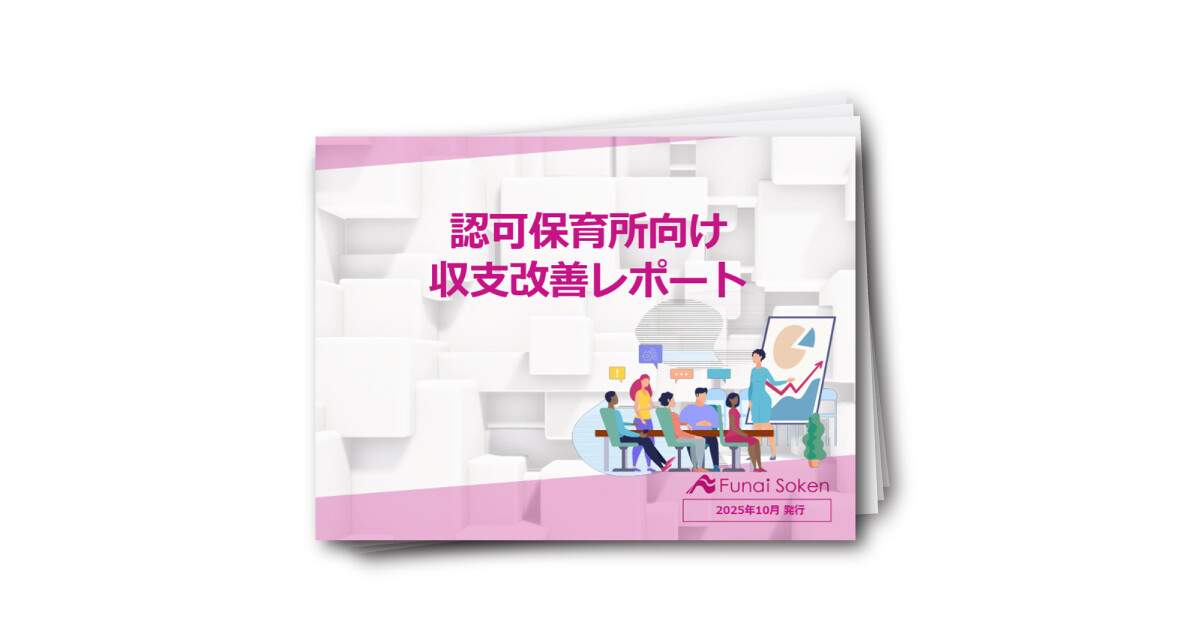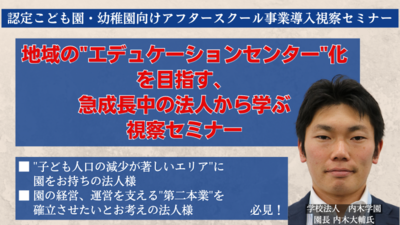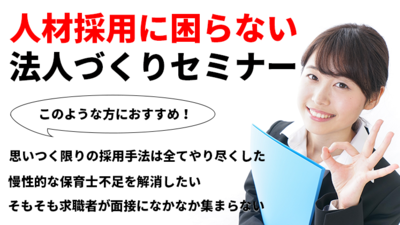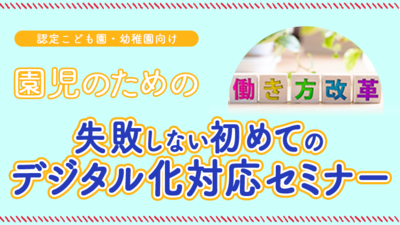1、保育業界を取り巻く外部環境

はじめに、令和6年度の保育業界の動向について、特に処遇改善等加算に関連する重要な制度変更をご説明します。
令和6年6月に子ども・子育て支援法の改正案が成立しました。この改正により、今後「こども誰でも通園制度」や「産後ケア」など、現行の施設型給付や地域型給付に加えて新たな給付制度が創設されます。これにより保育所等は多機能化が進み、受け入れ範囲が拡大していく方向に進んでいきます。
この「こども誰でも通園制度」の令和8年度給付については後ほど詳しくお話ししますが、現在は施設型給付の中に処遇改善加算Ⅰ~Ⅲが含まれ、一本化が進んでいます。今後創設される乳児のための支援給付においても職員配置が必要となるため、現在の認定こども園、保育園、幼稚園で実施されているものと類似した処遇改善制度が新たに加わる可能性が高いと考えています。
一方、産後ケア事業については地域子ども・子育て支援事業として位置づけられることが決まっています。これは病児保育事業や延長保育事業、現在の一時預かり事業などと同じ枠組みに入ることになるため、現在の保育事業のような複雑な処遇改善制度が個別に設けられる可能性は低いと考えられます。しかし、今後の認定こども園や保育所に求められる機能の一つとして、こうした新たな役割が期待されていくことをご理解いただければと思います。
さらに、処遇改善と密接に関わる重要な変更として、事業の公定価格の見える化やDXがあります。子ども・子育て支援法の改正案には、保育給付を含めたワンストップサービスの推進が盛り込まれています。
令和6年度から、職員の給与に処遇改善が適切に反映されているかの情報公開が義務化されました。また、デジタル化については令和7年度までにICT導入率100%を目指しており、今後はデータの効果的な活用が求められています。
これにより、処遇改善に関連する残額や人件費の改定状況、社会保険料の事業者負担分など、これまで把握が困難だった部分についても、データとして適切に連携・管理される方向に進んでいます。

また、最後に重要なポイントとして、現在Ⅰ~Ⅲまである処遇改善加算は、令和7年度の一本化に向けて現在議論が進行中です。本日のセミナーを通じて、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの内容を理解し計算方法をマスターしていただくとともに、令和6年度に予定されている事業者に関わる重要な変更点については赤字マーカーで強調してありますのでご確認ください。なお、今年度は大きな制度変更はありません。
令和7年4月1日からは、先ほど触れた「こども誰でも通園制度」が地域子ども・子育て支援事業として始まります。この段階ではまだ処遇改善の概念は導入されないと思われますが、令和8年4月1日に予定される給付化の際には、現行の処遇改善加算に類似した、誰でも通園制度に従事する職員向けの処遇改善制度が創設される可能性があります。
また、令和7年4月1日から経営情報の継続的な見える化として、令和6年度分の人件費比率やモデル賃金の公開が義務化されます。さらに処遇改善等加算の一本化も進められるため、今年度はⅠ~Ⅲに分かれた状態で実績報告や計算を行いますが、将来の一本化を見据えた理解は非常に重要です。
なお、この後詳しく説明しますが、処遇改善加算が一本化されたとしても、現在の賃金底上げ部分や、一定の経験・技能を持つ職員への配分、役職者への加算といった基本的な要素が完全になくなる可能性は低いと考えています。最終的な形は今後の議論で確定していきますが、すでに一本化が進んでいる福祉業界の事例を見ると、制度は一つになるものの、現行の処遇改善加算Ⅰ・Ⅱの本質的な要素は残る傾向にあります。
本日のセミナーで処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの詳細をしっかり理解しておけば、一本化後も事務手続きが簡素化されつつ、制度の本質的な理解はそのまま活かせるかかと存じます。

まず「こども誰でも通園制度」の給付についてですが、令和6年度7月時点では115自治体ほどで試行的事業が始まっており、皆様の関連自治体でも実施されている可能性があります。現状は一時預かり事業に非常に近い形で、補助金形式で運営されていますが、令和8年度に向けて法律に基づく新たな給付制度として「乳児等のための支援給付」が創設される予定です。
この制度が本格実施されると、各自治体が需要見込みを定め、保育施設の定員と同様に、すべての施設で実施が求められるようになります。
現在の試行段階では、一時預かりの余裕活用型の仕組みを採用している場合は追加人員が不要な場合もありますが、本格実施に向けては人員体制や給付の補助単価の詳細が検討されています。特に「誰でも」という名称が示す通り、障害児や医療的ケアが必要な子どもたちの受け入れも想定されているため、施設の実施体制をどのように整えるかという点について、令和7年度を通じて具体的な基準が決定される予定です。

現在、115 自治体で試行的事業を実施しています。多くは保育所や認定こども園との併設、あるいは子
育て支援拠点との併設形態が主流です。今後は専用施設の設置や、児童発達支援事業などの福祉事
業所内への設置も視野に入れて検討が進んでいます。自治体や園で実施することになった際には、ど
のような形で事業を展開するか具体的な検討が必要です。特に今回のセミナーの議題として重要なの
は、処遇改善に関する課題が出てくる可能性がある点です。
▼続きは下記からダウンロードいただけます。