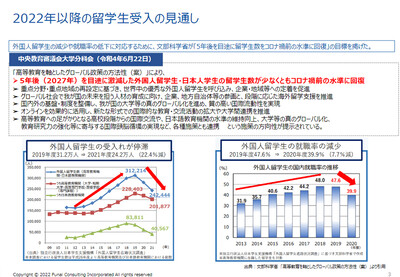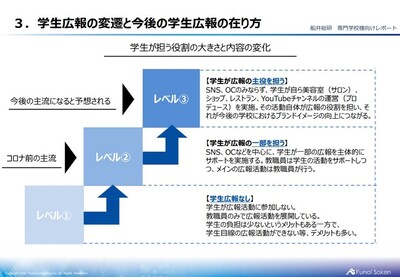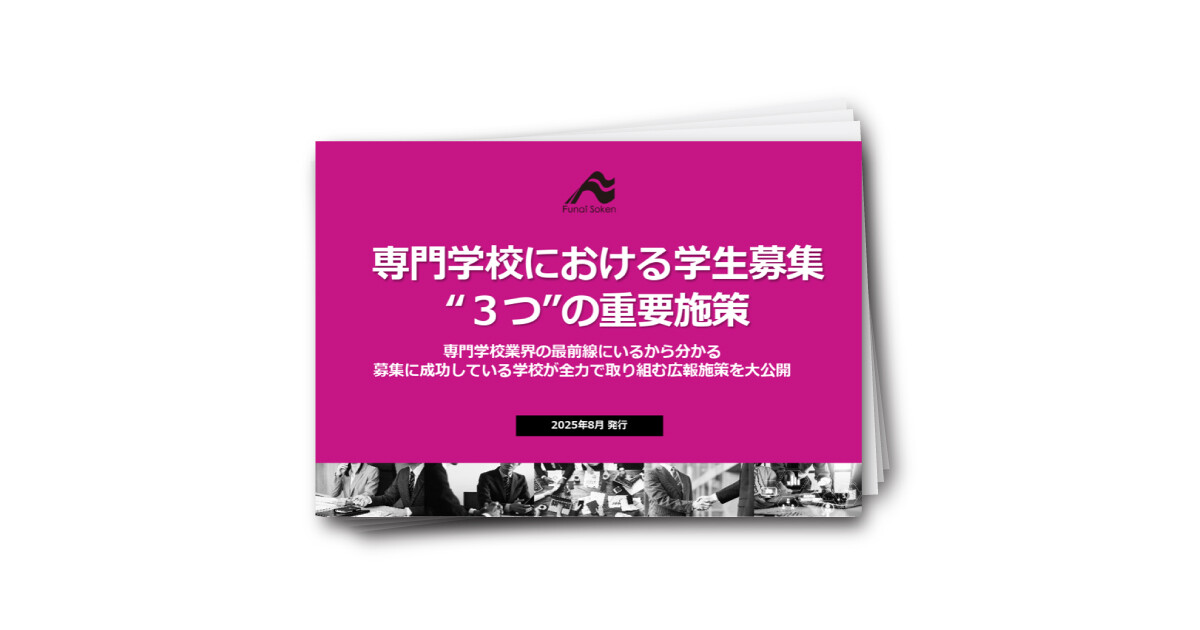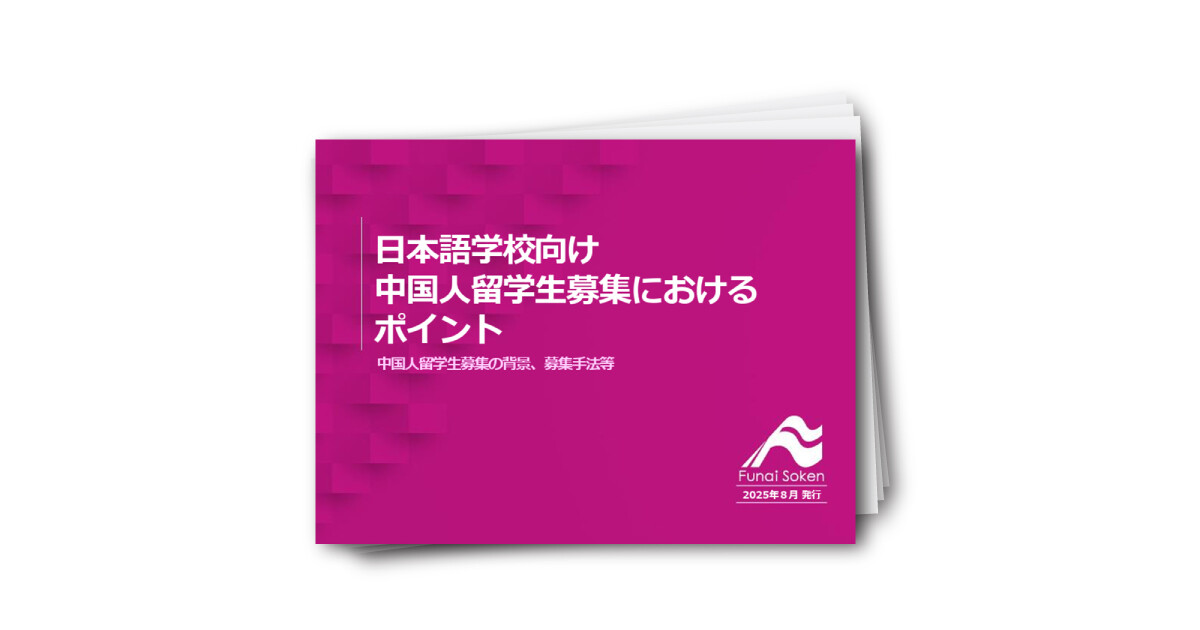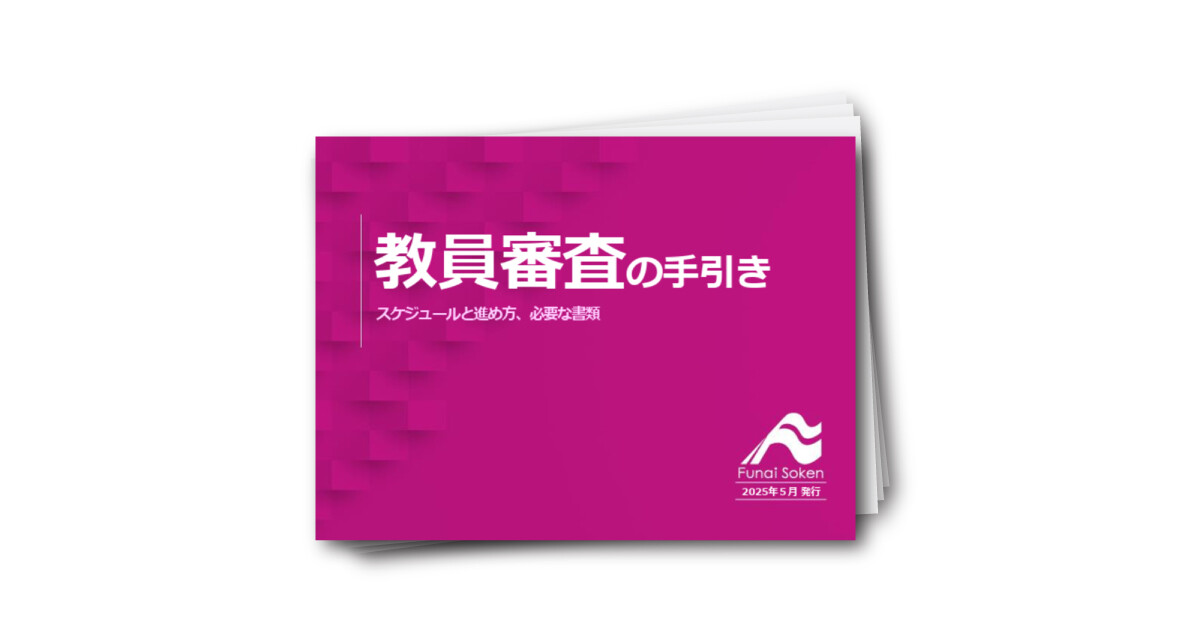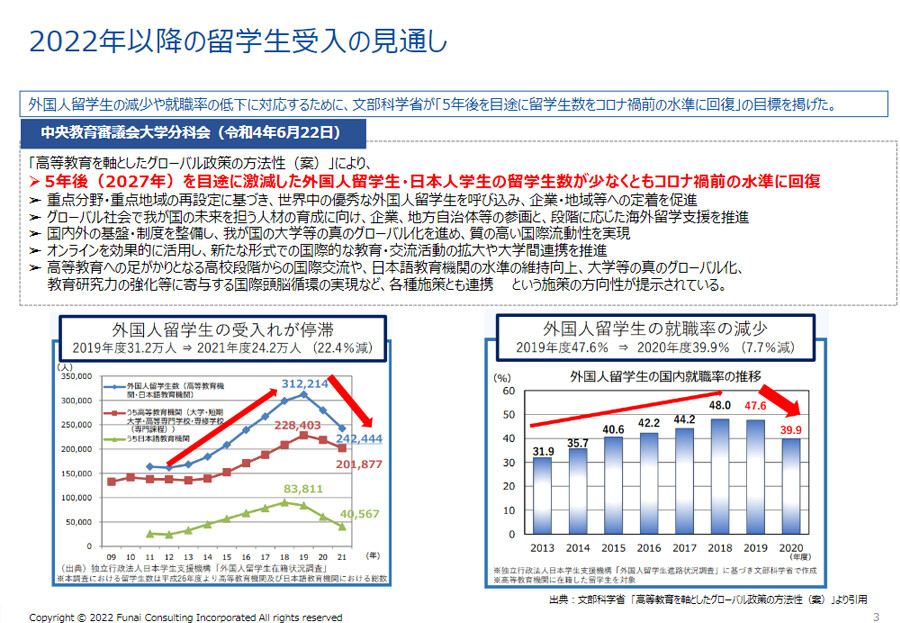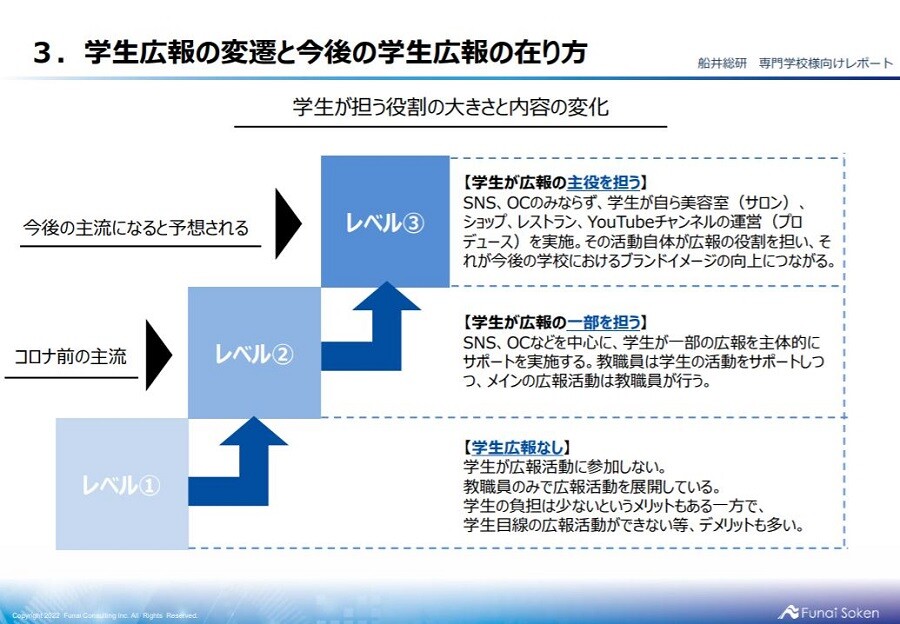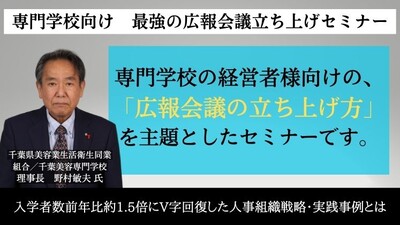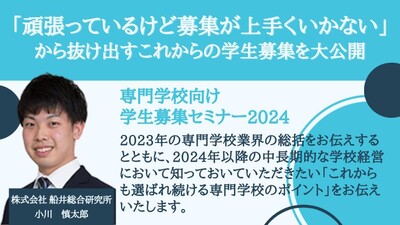レポート試し読み
続きは「ビジネスレポートをダウンロードする」ボタンより
無料でお読みいただけます
このような方におすすめ
- これから認定日本語教育機関の新規開設を目指し、申請の全体像を把握したい経営者様
- すでに法務省告示校を運営しており、経過措置期間内(2029年3月31日まで)に認定日本語教育機関への移行を確実に成功させたい経営者様
- 認定申請の準備を進めているが、審査のポイントや面接で何を聞かれるかがわからず、具体的な対策に不安を感じている経営者様
- 一度、申請が不認定または取り下げとなった経験があり、再申請に向けて課題を克服したいと考えている経営者様
目次
1. 認定日本語教育機関について
• 認定日本語教育機関とは? 法務省から文部科学省へ管轄が移管され、「教育の質」を重視する新制度について解説。
• 過去の申請状況を紹介 認定率が30%台と非常に低い現状と、多くの機関が申請を取り下げている背景について説明。
2. 認定のスケジュール、変更点
• 認定までのスケジュールを解説 事前相談から認定、新規開設までの年2回の申請スケジュールを紹介。
• 法務省告示校からの主な変更点について 経過措置期間に触れつつ、特に重要な「教育課程」と「教員(登録日本語教員)」の要件変更点を解説。
3. 認定のポイント
• 審査で重要視されるポイントを解説 文部科学省が求める基準や、カリキュラム、教材選択、運営体制など審査の焦点を説明。
• 合否を分ける面接審査について 審査における面接の位置づけ、時期、参加対象者、そして審査官が納得できる回答の重要性を解説。
4. 面接の質問内容について
• 過去の事例に基づく具体的な質問内容を紹介 「設置目的」「学校運営」「カリキュラム」「生徒支援」など、実際に問われた質問の概要を解説。
• 質問の意図と回答のポイントについて 学校運営や教育の質に関する厳しい審査の意図を説明し、面接出席者が十分に内容を理解して説明できるよう準備のポイントを紹介。
レポートの内容
本レポートでは、今後日本語学校を運営する上で必須となる「認定日本語教育機関」の認定申請について、最新の動向と具体的な対策を解説しています。
まず、制度が変更された背景や、法務省から文部科学省へ管轄が移管されたことによる審査の重点(特に「教育の質」)について説明します。
次に、申請から認定までの詳細なスケジュールや、法務省告示校からの移行における主要な変更点(教育課程と登録日本語教員の要件)を分かりやすく整理しました。
特に、認定率が30%台と低い現状を踏まえ、合否を分ける重要なポイントとなる「面接審査」に焦点を当てています。
過去の申請事例に基づき、面接で実際に問われた質問内容や、審査官が重視するカリキュラム、運営体制に関する回答のポイントを具体的に紹介しています。
このレポートを読むメリット
このレポートをお読みいただくことで、複雑で厳しい認定日本語教育機関の申請プロセスを乗り切るための具体的な道筋が見えてきます。
最大のメリットは、合否の鍵を握る「面接審査」への万全な対策が可能になることです。
過去の申請事例から分析した「設置目的」「学校運営」「カリキュラム」といった頻出の質問内容と、それらに対する準備のポイントを把握することで、自信を持って面接に臨むことができます。
また、新しい制度で重視される「教育の質」、特に「日本語教育の参照枠」に沿ったカリキュラム編成や教材選定の理由など、文部科学省が求める基準を深く理解できます。
これにより、申請書類の精度を高め、実地確認や面接での鋭い質問にも的確に答えられるようになります。
漠然とした不安を解消し、認定獲得の確率を高めるための一助として、ぜひ本レポートをご活用ください。
ダウンロード特典
東京本社・大阪本社ではもちろん、オンライン会議でも行うことができるため、全国どこの場所からでも相談可能です。
無料経営相談をぜひお気軽にお申し込みください。