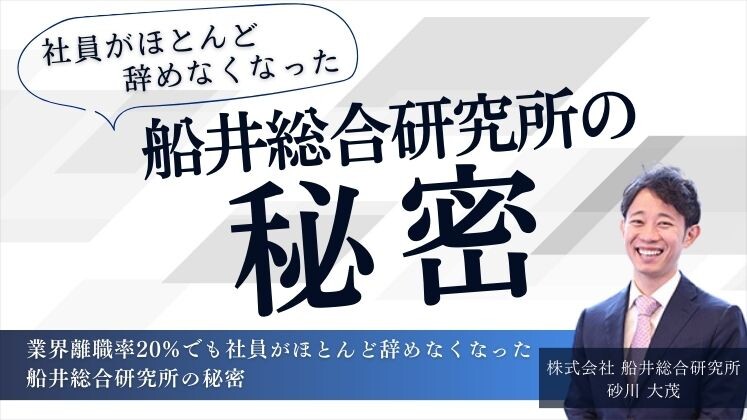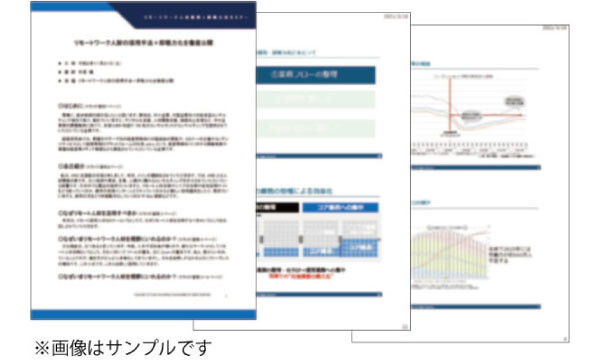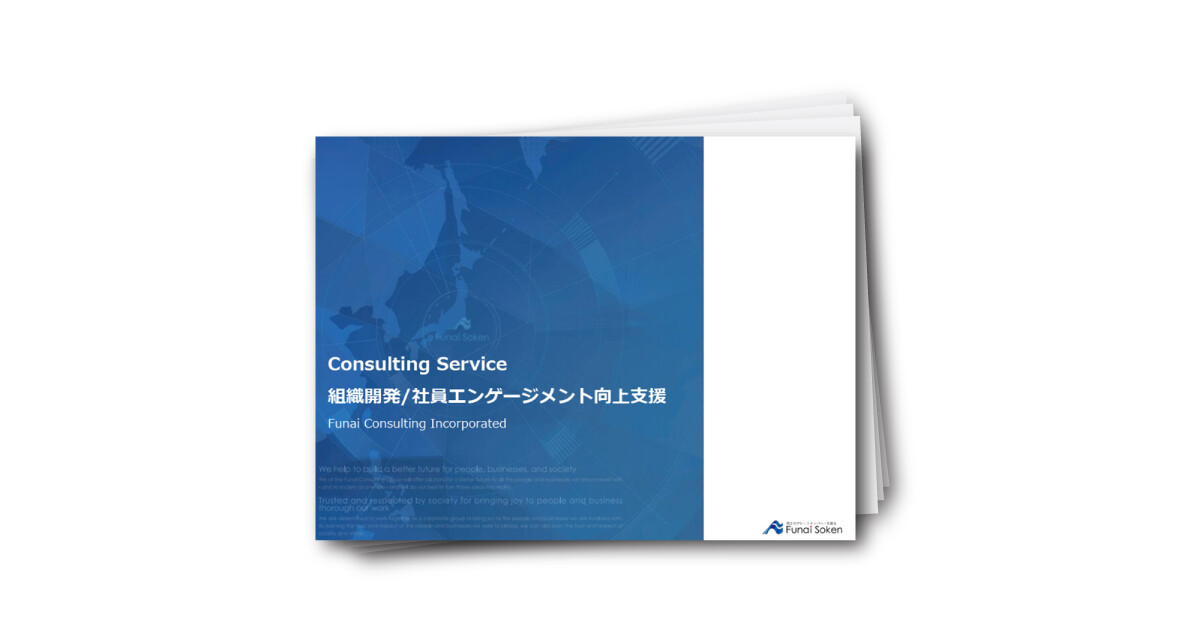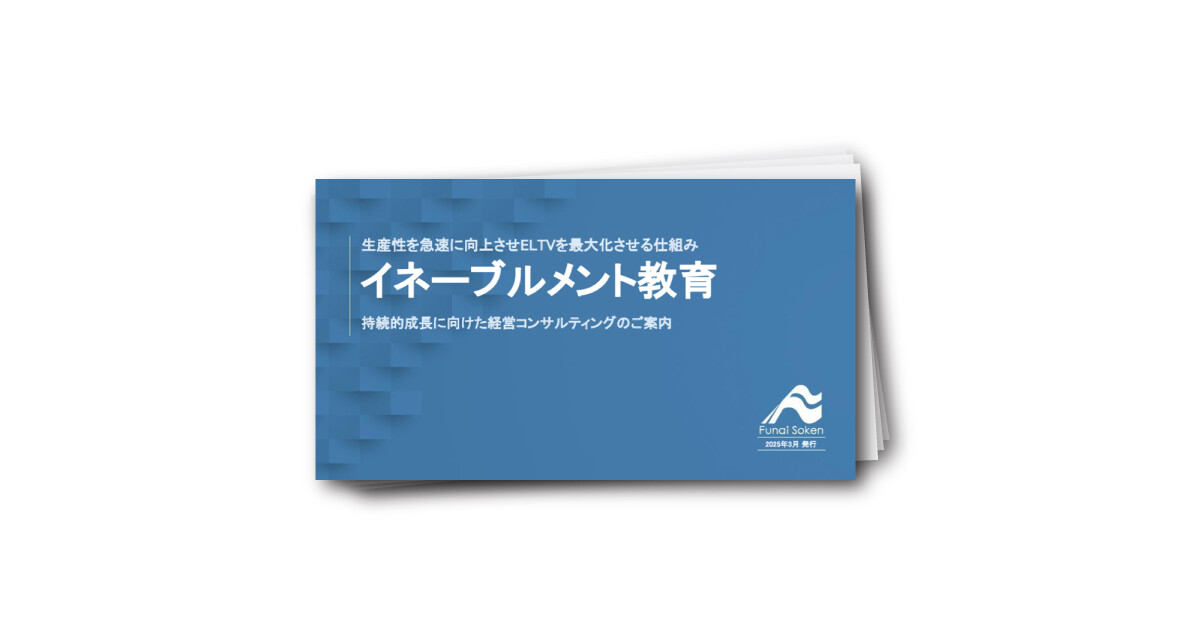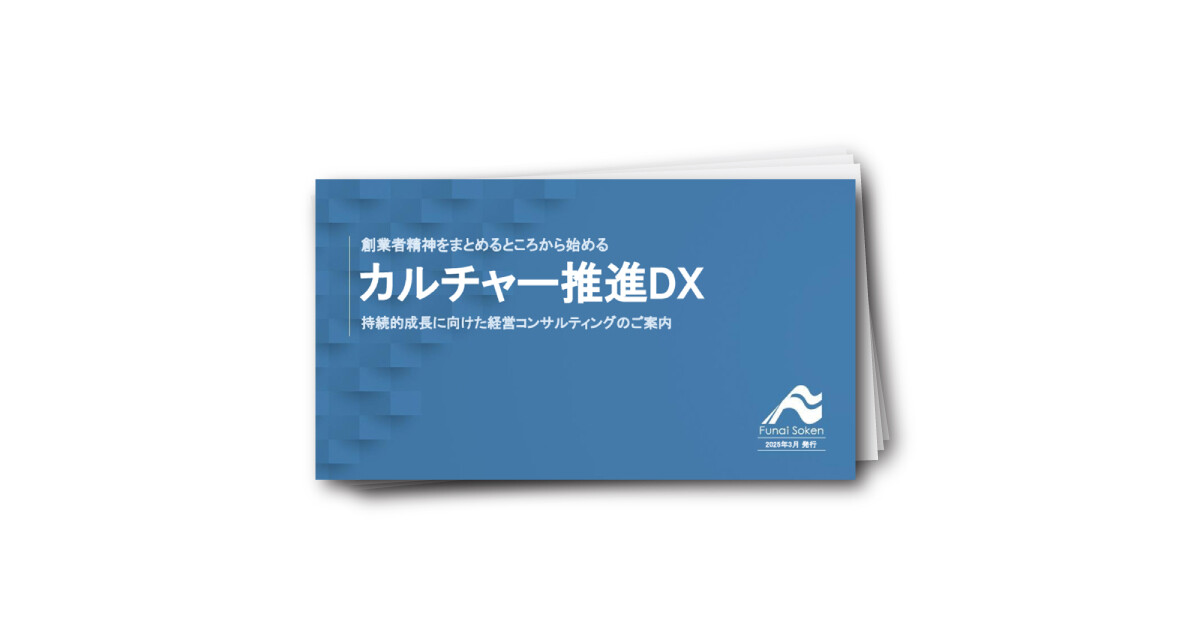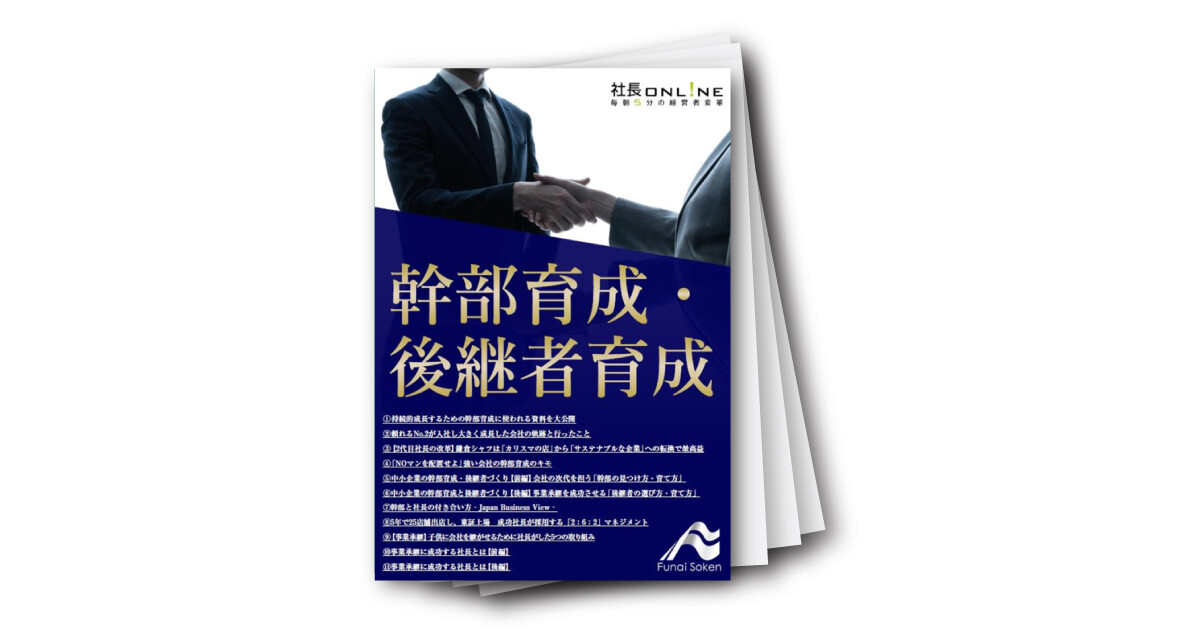日本を取り巻く社会問題

それでは、早速本講座の内容に入っていきたいと存じます。まず最初に、日本においては様々な社会問題が存在しております。とりわけ採用や離職といった領域に関しては、主に次の4つの問題が皆様の会社を悩ませているのではないかと考えられます。これらは実際に船井総合研究所も直面している課題です。
1つ目として挙げられるのが、人口減少・少子高齢化という問題です。いわゆる労働人口、つまり働き手となる若い人口が継続的に減少しているという点は、日本で長年にわたり指摘されている問題となっております。
続きまして、「日本型人事システムの実質的崩壊」という点についてです。大手企業を含めて終身雇用が破綻してしまうことや、労働組合の問題、年功序列など、高度経済成長期に確立された日本特有の人事システムといったものが成り立たなくなってきているという状況があります。
「働き方、生き方、価値観の多様化」については、これは特にZ世代を中心に見られる傾向ですが、働くことに対する価値観が大きく変化しております。以前は、初めて新卒で入社した会社で長く働き続け、その中で役職を昇進していき、キャリアアップしていくといった価値観が主流でした。
しかし現在は副業やダブルワークなど、スポット的に収入を得るような仕事を別途行っていたり、「合わなかったらやめればよい」といった、働くことに対して比較的フランクな価値観になっているのではないかと考えられます。
現在のニュースでは、テレビをつけていると退職代行会社を活用する方が増加しているといった報道も見られます。このようなことも、今の若い世代、特に若い世代の人との向き合い方や会社・仕事への向き合い方、この価値観の変化によって、様々なサービスや退職の方法も変化してきているという現象が起きております。
最後に、現実的にかなり頭を悩ませているのが最低賃金および人件費の増加、さらには働き方改革を進めなければならないという課題です。最低賃金も毎年秋には改定され、年々どのエリア、どの都道府県でも上昇してきております。東京都はもっとも高い地域であり、もう1,500円まで待ったなしという状況かと思われます。
また人件費も、採用が厳しい状況ゆえに、例えば初任給について、これまでは20万円を下回るところも多かったかと思いますが、現在は25万円、都心部であれば30万円を超える企業が多数増加してきたという実情があります。そういった初任給の底上げに伴い既存の従業員の給料も上昇させる必要があり、これは現在、物価高など何を購入するにも価格が上昇している状態であるため、生活が厳しいという状況の中で、給料を上げていかなければなりません。しかし会社としては、業績や生産性がそれに伴って向上していればよいのですが、そこは伸びていないため、給料を急に上げることが困難です。
働き方改革についても、休暇の取得方法や残業の問題、この領域もかなり厳しくなってきている状況です。逆に残業が過度に多い、あるいは年間休日数が極端に少ない会社は「ブラック企業」というレッテルを貼られるというのが昨今の時代の特徴であると考えられます。
これからの人的資本経営

エンゲージメントの話をする前に、現在の全体的な状況としては、「人的資本経営」という言葉が非常に注目されてきたという事実があります。この点について、少しだけ説明いたします。
人的資本経営とは皆様も一度は耳にしたことがあるかと存じますが、内容としては人材を資本と捉えるという考え方です。企業価値を向上させていくという点ではそうなのですが、この人材をコストではなく、資本として投資の対象としていくことが重要です。そうすることによって、戦略面ではイノベーションを生み出したり、経済面においては現在、決算書などの金額面でしか見えない部分以外の要素、つまりESG投資や社会性、人材の部分、見えざる資産がどのように有効活用されているのか、離職が多いのか少ないのかといった点も注目されるようになってきました。
社会面に関しては当然、今後、上場企業をはじめとして情報開示といった動きもますます強まっているという状況です。組織に関しては、若い世代や新しい世代の価値観を確実に取り込んでいかなければ採用もできませんし、その若い世代が次々と退職していくという事態につながります。この人的資本系について、経済産業省内で紹介されている伊藤レポートでは、3つの視点と5つの要素が示されており、これらを皆様と一緒に確認していきたいと存じます。

3つの視点については、人材に対して適切な人的資本の経営を実践しようとする場合、経営戦略と人材戦略が連動しているか、また人材や組織に対して戦略を立て、そこに十分な投資や時間が割かれているかといった点が重要な視点となります。

5つの要素についても、まず流動的に人材ポートフォリオを構築し、それを効果的に運用できているかという点があります。また、構成員の経験や知識を組織としてエネルギーを生み出すようにすることができているかという点も重要です。さらに、現在「リスキリング」という言葉があるように、特にデジタルスキルを向上させて生産性を高めるために、社員一人一人に対して教育や学び直しの機会を提供していくことが必要とされています。
今回の話題となるのは4つ目の要素であり、多様な個人が仕事に主体的、意欲的に取り組めているかという点です。近年、「エンゲージメント」という言葉が頻繁に使用されるようになってきました。これは働き手と企業の関係において、単に給料の上昇や休暇の増加による満足度(ES面)だけでなく、企業と個人が確実に双方向で結びついている状態を指しており、このエンゲージメントを高めていくことが重要です。内部的には従業員と企業の間でエンゲージメントを向上させていくべきということです。
5つ目は働き方に関する要素です。コロナを契機に様々な場所での業務遂行や、時間に縛られない柔軟な働き方が進展したため、こうした点も考慮していかなければなりません。このような体制が整備されていなければ、多様なニーズを持つ働き手に対応することができず、採用の困難さや人材募集の不調といった事態に直結してしまいます。

今回テーマとなる人的資本経営とは、人材を単なるリソースではなく「資本(エクイティ)」として捉えるという考え方です。これまでは人材を資源として捉えることが多く、それは商品調達と同様にコストとして考えられていました。商品を購入する場合はコストとなり、その結果、商品は資産(アセット)として計上されます。しかし人材を資本と考えるならば、それはバランスシートの右下に位置づけられ、人材の調達は投資として捉えられます。したがって、人的資本への投資を確実に行うという考え方が重要なポイントとなります。この前提を踏まえながら、採用・育成・定着について皆様と共に考えていきたいと存じます。
資本であるため、いかに効率的に成果を上げるかという点では、企業業績においてROE(自己資本利益率)という指標が存在します。これは資本に対してどれだけの利益を生み出しているかを示す指標です。したがって、人材の資本に対してどれだけのリターン、すなわち生産性向上や企業への利益貢献を生み出していくかが、企業価値を高める上で必要な考え方となります。この人材のROEを高めていくためには、エンゲージメントが重要となります。
▼続きは下記からダウンロードいただけます。