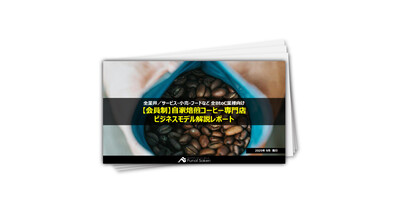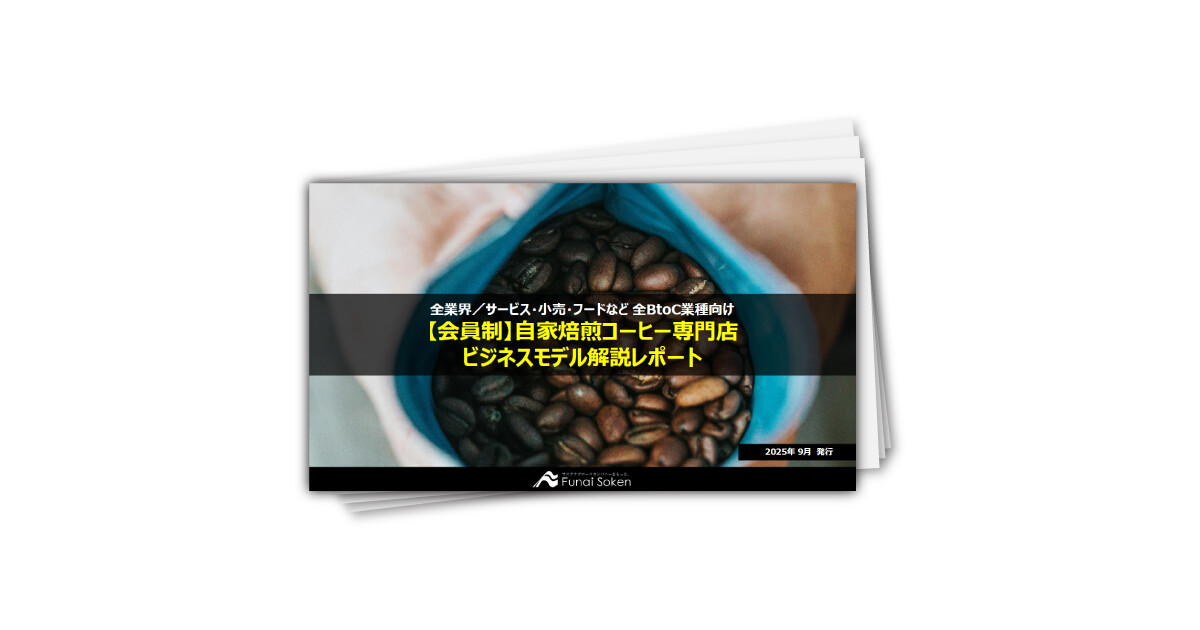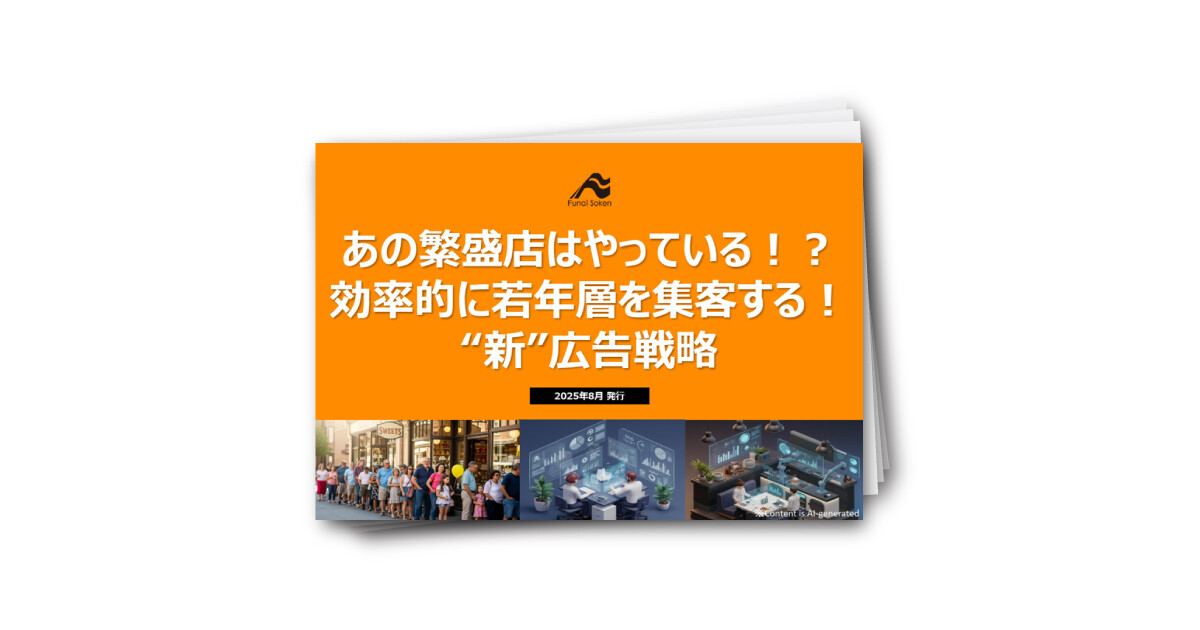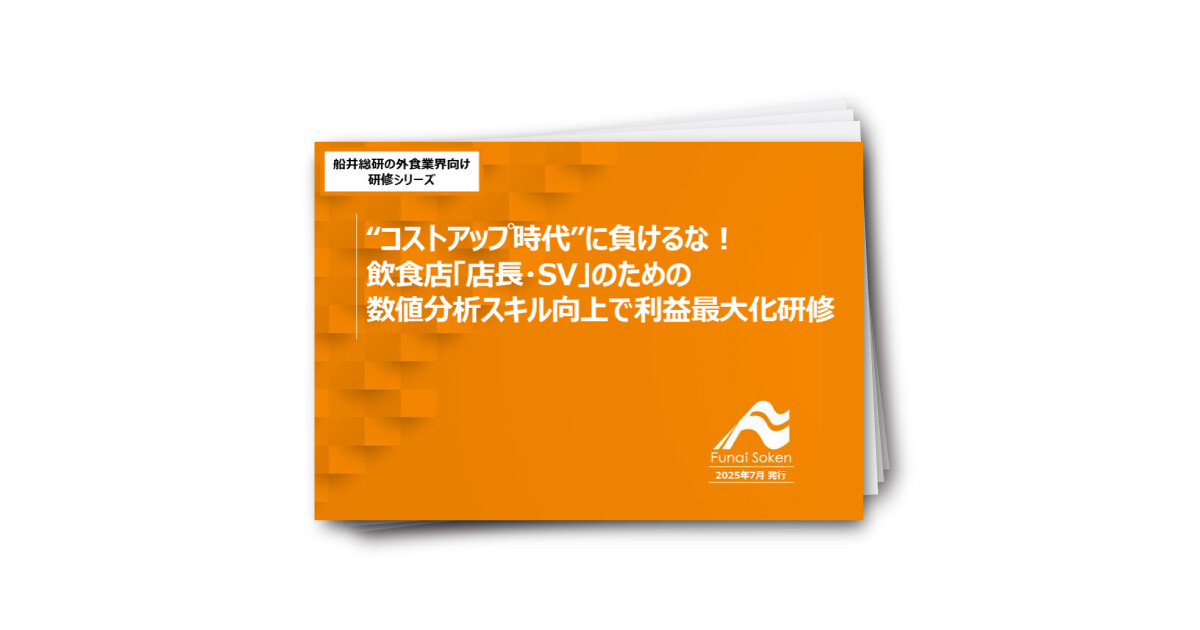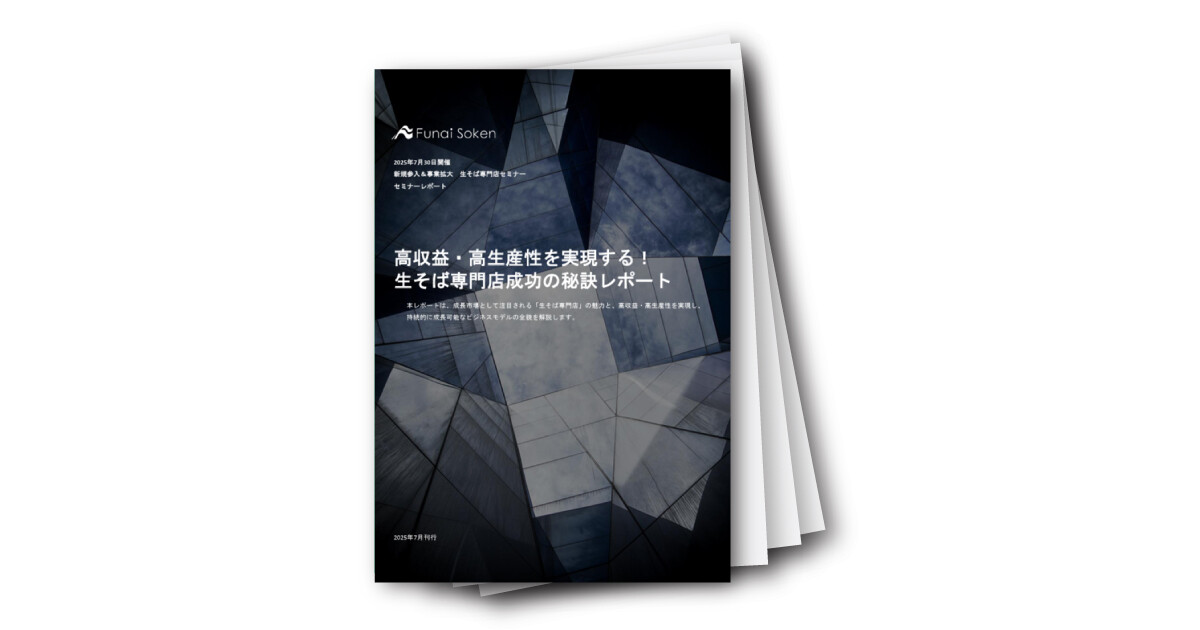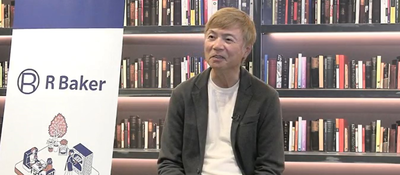2014.06.06
■ サクセスサマリー
【ビフォア】
板前の握る鮨懐石は、一般消費者にとって敷居の高い存在となる上に、ネタの質にこだわるあまり経営も下降気味に
【アクション】
ブランド力を活かし「鮨懐石みどりプロデュース」と銘打った宅配を開始。宅配で月売上+200万~300万円を確保、さらに150円均一と宅配のハイブリッド型店舗をオープン。宅配の販促ツールを実店舗の広告媒体として連動。宅配利用→店舗利用→会員化→DM→再来店の流れが構築された
【アフター】
均一料金という不安を与えない価格設定と宅配事業の連動が功を奏し、地域の人気店に君臨、売上は2.5倍に。テレビや業界紙の取材も多数
住宅地に建つ創業70年の寿司店が、坪客単価40万円という飲食店では驚異的な売上をたたき出す。客単価2~3,000円、原価は宅配と実店舗のトータルで50%台という驚異のバランスで、板前さんと向き合い、楽しむ、いわゆる“立ちの寿司”の再起に向けて一歩を踏み出す。

取締役 富田 勝之(とみた・かつゆき)氏
先代から地域の人々に親しまれ、選りすぐりのネタを仕入れてはふるまっていました。“立ち寿司”の形態は、いつしか高級で敷居が高く、お金持ち向けというイメージに変わってしまいました。
地域の人々が職人のこだわりに触れ、味わう空間ではなくなってしまったことを憂いながらも、途絶えさせたくない強い想いがありました。

リーマンショックなどの外部環境の変化から、宴会やハレの日需要が減少し、いよいよこのままではいけないという時が来ました。私は名古屋の大手企業で長年にわたり飲食の店長をしていた頃の経験から、持ち帰り需要の増加を実感していました。当社が持っている商品のクオリティーをそのまま食卓に届けることができれば、私どものブランドを伝え、残していけると考えましたが、良い伝え方がわかりませんでした。
その時、船井総研のセミナーに出合ったのです。職人は宅配に対して難色を示していました。「時間が経てば寿司ではなくなる」というのです。職人あがりの自分にもその気持ちはよくわかりましたが、この時流と生き残りを考え、またこの寿司が宅配によってたくさんの地域の方に親しんでもらえることを伝えると、納得してくれました。
宅配がつなぐ地域のきずな
取り組む上で心がけたことは、立ち寿司が賑わっていた時代のように、チラシから配達まで、とにかく地域の人々との接点を太く多くすることでした。15分以内の配達区域に商圏を決め、季節やイベントごとに目玉となるメニューを変えていきます。
メニューは、まぐろ、えびなどのネタと、利用シーンの両方向から選びやすいように工夫しました。チラシには実店舗も記載し、認知度を高めていきました。
船井総研さんの指導から作成したチラシを入れてみると、初日から電話が次々に殺到する状況でした。オペレーションが追いつかないという、嬉しい悲鳴でした。宅配と実店舗の相乗効果は、在庫の回転や収支バランスともに想像以上でした。

均一立ち寿司に賑わい戻る
さらなる展開として船井総研さんとともに計画したのが、客単価2~3千円の、どのネタもすべて150円均一の立ち寿司です。鮨懐石と回転寿司の間の価格帯で、美味しい寿司を安く楽しんでもらう形態です。
ここの需要は必ずあると睨んでいました。ビジネスモデルが成り立つかどうか、本店の鮨懐石店で約1年間かけてテスト・データ収集を繰り返し「これならいける」と確信し出店を決めました。
通りから1本入った住宅街の2階という立地にもかかわらず、鮨懐石みどりのブランド寿司が150円で食べられるということで、連日大盛況です。大トロやウニといった高価なネタが飛ぶようにオーダーされ、満足いただけているようでした。コストのバランスと若手職人の育成のために、板前に若手を採用しましたが、結果的にお客様との距離を縮めることに成功しました。

お客様の喜びを目の前で感じられ、どんどん腕前は上がっていきます。また20歳前後の職人は親しみがあり、立ち寿司の敷居を下げたようでした。お気に入りの職人を指名するお客様や、孫のように職人と話しにくるお客様もおられ、かつての立ち寿司の様相が私の脳裏で重なりました。もともと屋台から始まった立ち寿司は地域のコミュニケーションの場でした。
その文化を途絶えさせたくない、復活させたいという想いが、ここにきて形になりつつあります。日本中に、地域と職人とのあたたかいコミュニケーションである立ち寿司の文化をもう一度蘇らせることができると信じています。
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度