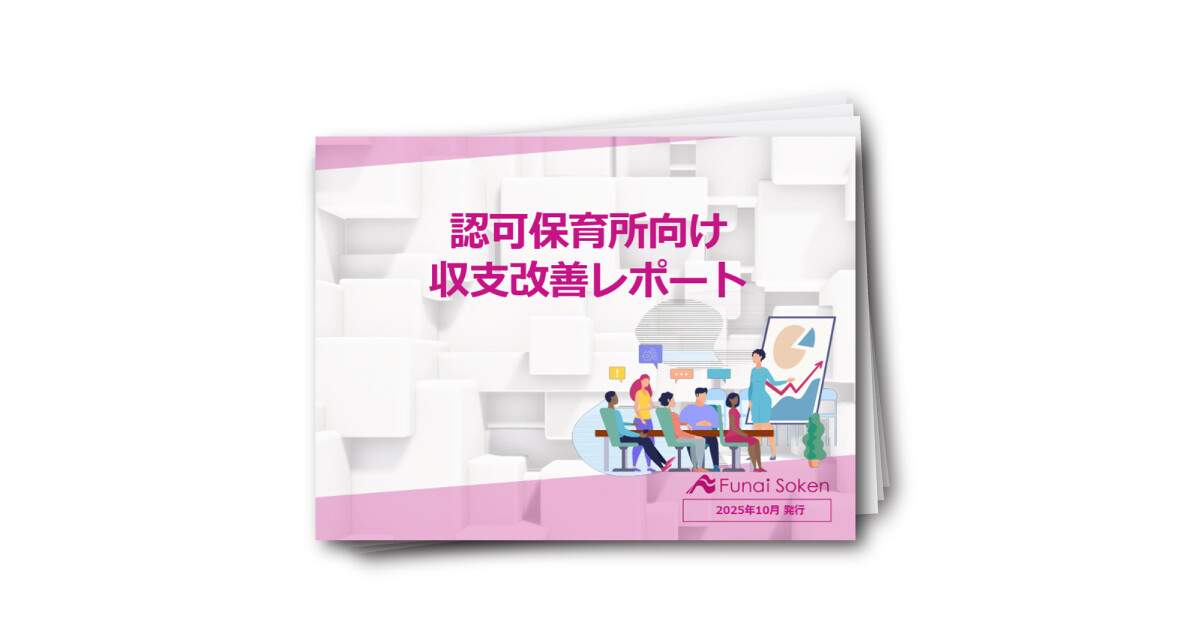企業主導型保育事業向け_令和7年度監査チェックサポート

企業主導型保育事業 業界の現状
今日の保育業界、特に企業主導型保育事業の業界の現状は、その監査の厳格化が年々進んでおり、多くの事業者様にとって事業継続における大きな課題となっております。令和5年度からは、新型コロナウイルス感染症の影響で一時的に見送られていた施設への立ち入りによる監査実施が本格的に再開され、同時に抜き打ちでの午睡調査も復活しました。さらに、専門的な労務監査や財務監査も毎年500施設を対象に行われるなど、監査の形式は多様化し、確認される項目は以前にも増して詳細になっています。
監査の現状と対策の重要性
監査の評価基準は毎年度変更や追加が発生し、児童育成協会からの通知から実際に監査が実施されるまでの期間が非常に短いことが特徴です。そのため、事業者様には常に最新の情報をキャッチアップし、事前の準備を徹底することが不可欠となります。
単に「監査項目を確認する」だけでなく、それぞれの項目がなぜ重要なのか、そしてどのようなリスクが生じるのかを深く理解し、日々の運営に落とし込むことが、監査対策の根本となります。適切な保育運営監査 対策を講じることは、助成金返還のリスクを回避するだけでなく、結果として質の高い保育提供と安定した経営へと繋がっていきます。
監査までの流れと準備
監査は以下の流れで進められます。
1. 協会からのメール通知
立入調査の約1ヶ月前に協会からメールが届きます。
2. 自主点検表と確認リストの作成
「自主点検表」と「乳幼児及び職員に係る確認リスト」を作成し、監査の10営業日前に返送します。
3. 準備書類の準備
「立入調査当日の準備書類」・「指導・監査評価基準」に基づいて、必要な書類を準備します。これらの書類は、企業主導型ポータルサイトからダウンロードできます。
4. 前年度の指摘事項の確認
前年度に立入調査を受けている場合は、指摘事項が改善されているかを確認します。
評価基準は毎年度変更や追加があるため、新年度を迎えたら早めに確認し、対応を進めることが重要です。
令和7年度監査における重要チェックポイント
船井総研が、これまでのコンサルティング経験を通じて特に重要視し、事業者様にご支援している監査チェックポイントは多岐にわたります。ここでは、具体的な項目と、船井総研がどのようなソリューションを提供しているかについて、実務的な視点からご説明いたします。
●直営・委託の区分及び事業類型等
まず事業者様の事業類型が適切に運用されているかを確認いたします。一般事業主型の場合、施設定員の1割(小数点以下切り上げ)を自社従業員枠とすることが必須であり、この枠が満たされない場合でも、その枠は空けておく必要がある点が令和5年度から必須化されました。
ただし、一時預かり余裕活用型での活用は認められます。保育事業者型に切り替えるには、保育事業の5年以上の実績が求められ、定員20名以上の施設では保育士比率75%以上が必須です。これらの要件は、各年度4月1日時点で満たしている必要があります。
●利用者負担額(いわゆる保育料)
利用者負担額、いわゆる保育料については、こども家庭庁想定価格を超えている場合、その理由を明確に説明できるよう準備が必要です。
原則としてこども家庭庁想定価格が上限ですが、エリア特性や社会情勢によっては、上限以上の設定が認められるケースもあります。
※内閣府想定価格※
| 4歳以上児 | 23,100円 |
| 3歳児 | 26,600円 |
| 1・2歳児 | 37,000円 |
| 0歳児 | 37,100円 |
●乳幼児の人権に対する十分な配慮
不適切保育の防止は、乳幼児の人権に対する十分な配慮の観点から強く求められています。
不適切保育・事故に関する報道を受け、令和5年度より追加された評価基準です。
定期的な点検が必要となります。
全国保育士会が作成した「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」などを活用した定期的な点検を行ってください。
●乳幼児の健康診断
乳幼児の健康診断については、年2回の実施が推奨されており、令和7年度からは歯科検診が年2回義務付けられます。1回も実施していない場合は指摘対象となり、1回のみの場合は令和7年度は口頭・文書指導はないものの、令和8年度以降は年2回実施を求められます。
●避難消火等の訓練・不審者対応訓練の計画
避難消火等の訓練・不審者対応訓練は、計画を立てるだけでなく、訓練後に実施した旨や職員間での反省を記録しているかが確認されます。
●事故防止及び事故発生時の対応マニュアルの作成
園独自のマニュアル整備は、事故防止及び事故発生時の対応において必須です。公表されているマニュアルを単にコピーペーストするだけでは不十分であり、ご自身の園で起こり得る事故や、実際にあったヒヤリハットなどを元に追記した、施設独自のマニュアルが求められます。特に午睡、水遊び/プール、食事中の誤飲、玩具の誤嚥、食物アレルギーの5項目については、記載されているかどうかが重要視されます。
●事故報告・ヒヤリハット報告
事故報告・ヒヤリハット報告は、区別して管理し、常時記録できる体制を整えることが求められます。月1回の会議でまとめて記録するのではなく、その場で記録する運用が重要です。
●児童出欠表
児童出欠表では、欠席事由が明確に記されているか、またその事由を確認する書類が保存されているかが厳しく確認されます。ICTでの記録が普及している一方で、紙の連絡帳を使用している場合は、保護者に渡してしまう前にコピーを取るなどの工夫が有効です。
●出退勤記録
加算職員の勤務実態が出退勤記録と合致し、加算要件を満たしているかは重要なチェックポイントです。児童数に対する適切な保育従事者の配置に加え、常駐が原則の連携推進員や、体調不良児保育担当の看護師などの記録・勤務実態が要件を満たしているか、特に注意が必要です。抜き打ち午睡チェックが増えている現状を鑑みると、記録と実態の乖離は助成金返還事例につながる可能性もあります。
●子育て支援員・保育補助者雇上強化加算
子育て支援員・保育補助者雇上強化加算については、令和5年度より、研修修了証に記載された日付から「子育て支援員」と認められるようになりました。研修修了見込みでの加算取得は不可となり、要件が変更されています。令和5年度より児童育成協会主催の研修がないため、自治体主催の研修情報を自ら調べる必要があります。
●処遇改善等加算
処遇改善等加算の監査では、職員への周知が行われているかが確認されます。専門的労務監査では、実際に職員に対して周知状況が確認される点に留意が必要です。処遇改善Ⅱについては、キャリアアップ研修要件が段階的にスタートしており、副主任保育士や専門リーダー等は令和7年度には「専門分野別研修」・「マネジメント研修」のうち3つ以上の研修分野の修了が必須となります(令和8年度からは4つ)。職務分野別リーダー等も令和6年度から「専門分野別研修」のうち1つ以上の研修分野の修了が必須です。
●衛生管理の状況
衛生管理の状況に関しては、調理・調乳に関わる職員だけでなく、食事介助者も月1回の検便が必須です。自治体ごとの保健所のルールと異なる場合があるため、確認が必要です。また、保育室・調理室内の衛生状況や整頓状況も確認されるため、改めて清掃や物の置き場の確認をしておく必要があります。
●安全確保(安全計画の策定)
令和5年4月1日より安全計画の策定が義務付けられ、監査の評価基準にも追加されました。計画を作成するだけでなく、職員への周知や、計画に基づく取り組みを保護者へ共有することも求められます。「園だより」などで計画策定の旨や具体的な取り組みについて積極的に発信することが重要です。安全計画のひな型は企業主導型保育事業ポータルサイトからダウンロードできるため、既存の書類と照らし合わせ、抜け漏れがないように作成しましょう。
●予算編成
予算編成においては、加算取得状況と園児数の見込みから目標収入を試算し、事業年度ごとの予算書を作成することが必要です。専門的財務監査では毎月の予実管理の実施も求められるため、安定した経営のためにも予算書の作成と予実管理を行う体制を整えることが重要です。
●帳簿の整備
帳簿の整備については、仕訳日記帳や総勘定元帳といった《主要簿》と、固定資産管理台帳、現預金出納帳、小口現金出納帳、未収金台帳、未払金台帳などの《補助簿》が適切に整備されているかが確認されます。特に小口現金の管理上限や、職員による立替払いについて厳しくチェックされます。
●収入
収入に関するポイントとして、実費徴収すべき対象項目が明確に定められています。これらは保育料に含めて徴収してはならず、利用者負担相当額以上の保育料を徴収している場合、これらの費用をその理由とすることはできません。逆に、これらの項目で法人が支出しているものがあれば、保護者から実費で徴収することが可能です(ただし、保護者への事前の周知が必要です)。
●支出
支出に関しては、助成金対象外となる経費の例が示されており、これらは自己負担となります。完了報告でも確認される重要な項目であり、特に誤りやすい項目がピックアップされているため、注意深く確認する必要があります。
●収入超過調整額の使途
最後に、収入超過調整額の使途についてです。積立資産の名目として、「人件費積立資産」「備品等購入積立資産」「修繕積立資産」「保育所施設・設備整備積立資産」が挙げられており、完了報告と同額かつ独立した勘定科目で処理されているかを確認されます。積立資産は専用の口座で管理し、積み立てた名目に合った使途であれば自由に引き崩して使用でき、その使途と金額を年度完了報告で報告する形になります。
まとめ 監査対策と経営改善に向けて
これら詳細なチェックポイントが示すように、企業主導型保育事業の運営においては、非常に複雑で多岐にわたる側面が求められます。適切な保育運営監査 対策を講じるためには、これらの基準を深く理解し、日常の運営に落とし込むことが不可欠です。
しかし、毎年度評価基準が変更・追加され、通知から実施日まで一カ月程度しかない状況で、事業者様が監査対策を完璧にすることは非常に厳しいかと思います。このような対応の難しさは、企業主導型保育事業の制度全般にも言えることと認識しております。
船井総研は、全国の企業主導型保育事業者様と密接に関わる中で、常に最新の情報をキャッチアップし、それを事業者様と共有することで、より良い保育園経営ができるようサポートさせていただいております。私たちの提供するソリューションは、単なる監査対策に留まらず、事業者様の経営全体を見渡し、持続可能な運営と成長を実現するための多角的な支援を目指しています。
船井総研への経営相談のお勧め
船井総研は、このような企業主導型保育事業における複雑な制度や、監査における現場の業務負荷の大きさに日々悩まれている事業者様を多数拝見しております。
保育運営監査 対策 はもちろんのこと、収支改善、園児募集、職員採用、事業計画策定など、保育園経営におけるあらゆる課題に対して、船井総研は専門的な知見と豊富な実績でサポートいたします。
もし、ご相談事や疑問点がございましたら、どうぞお気軽に船井総研までお問い合わせください。事業者様の安定した運営と発展のために、船井総研は全力でサポートさせていただきます。
関連するダウンロードレポート
ご相談の流れ
- 以下の流れにて、まずはお気軽にお問い合わせください。
貴社からのお問合せ
コンサルタントからご連絡
※目安1~3営業日以内無料経営相談
※45分~1時間程度