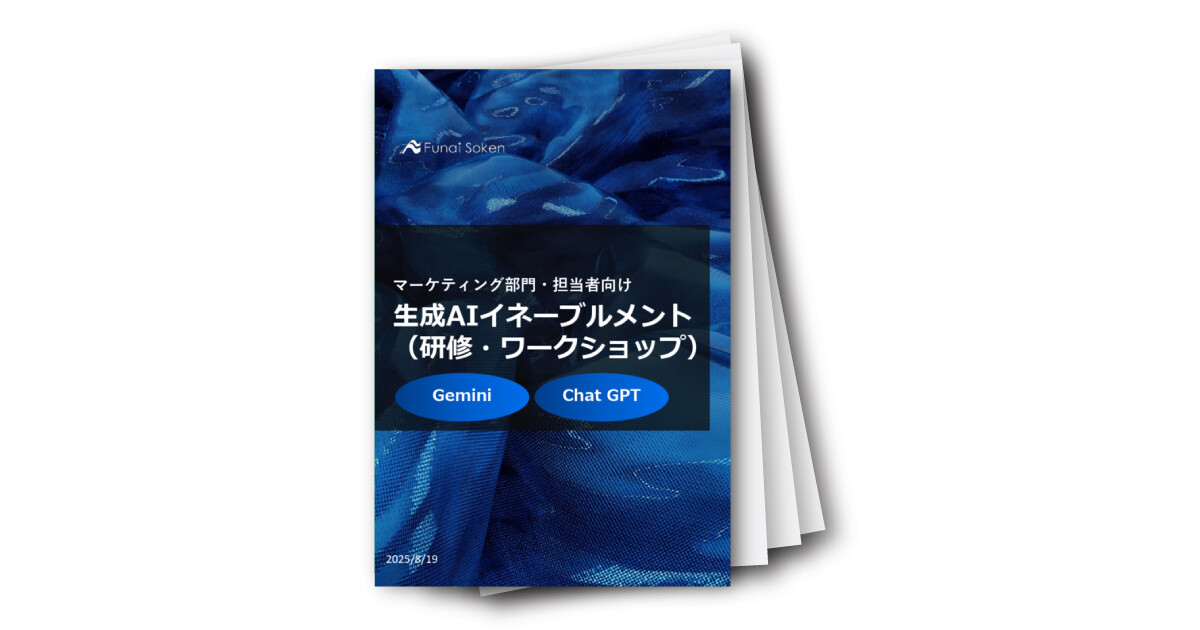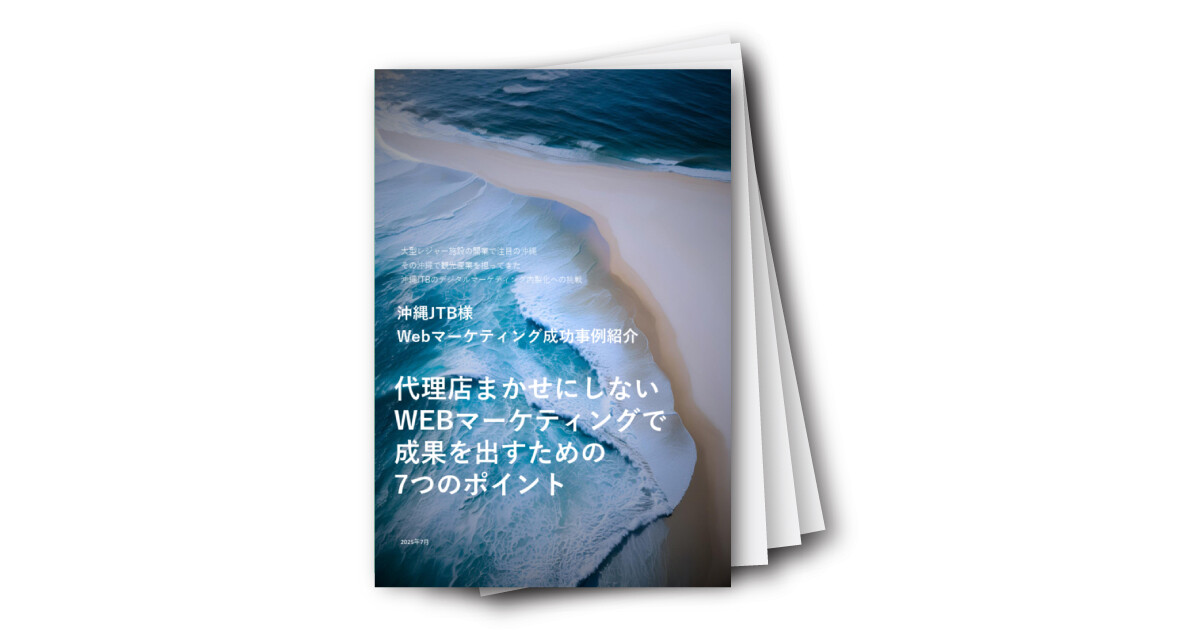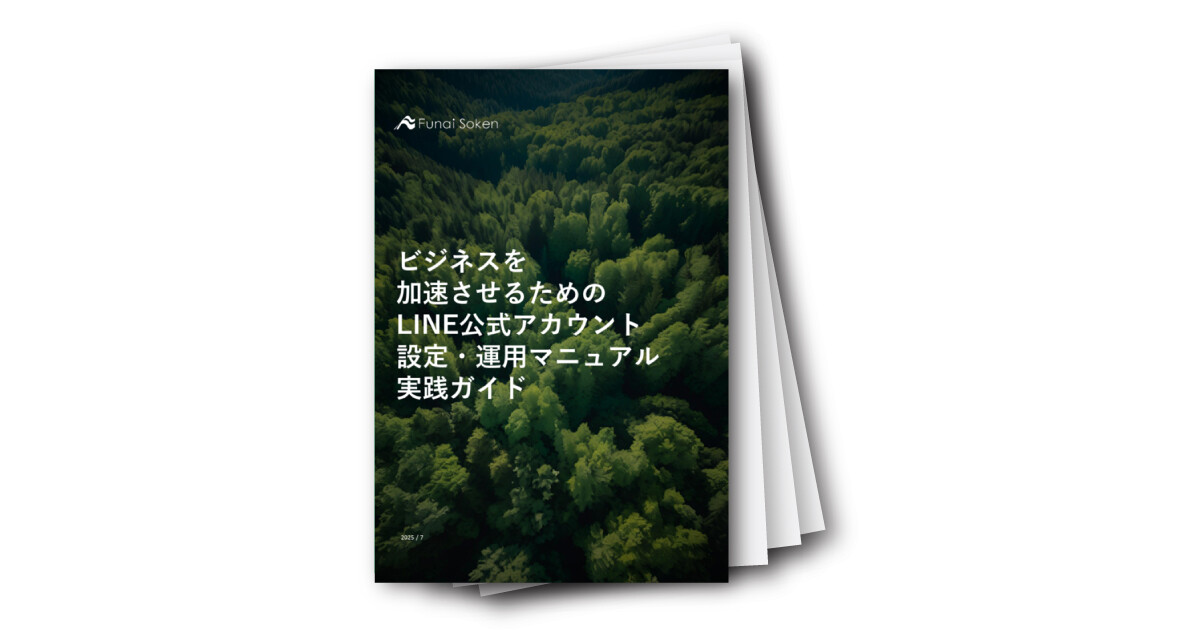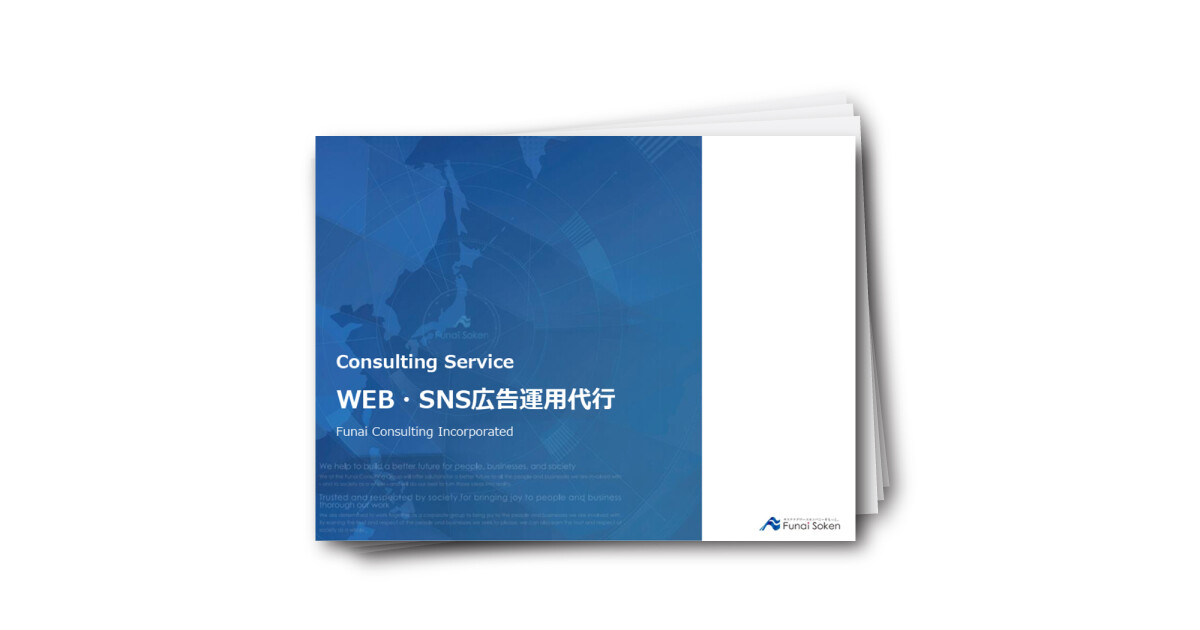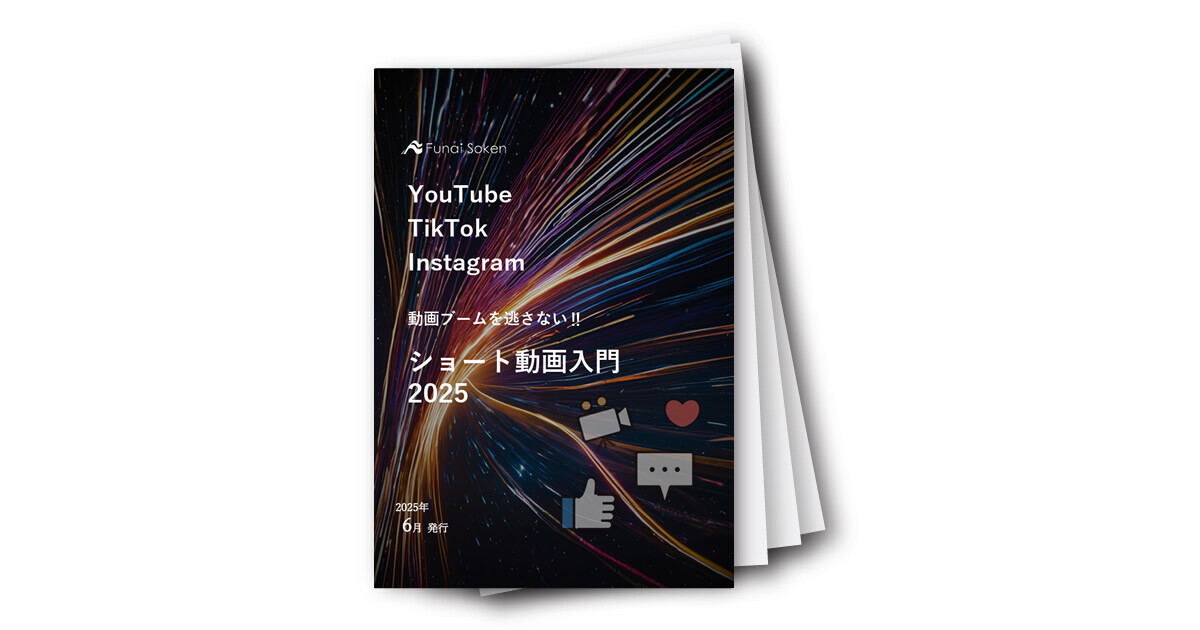経営戦略としてのデジタルマーケティング
船井総合研究所(以下、船井総研)は、変化の激しい時代でも、普遍的な経営原則に沿うことで、収益性の高い経営体質を築けると信じています。これを私たちは「船井流経営法」と呼んでいます。特に、インターネット革命以降のデジタルマーケティングの進化は目覚ましいものがあります。企業経営において、Web広告やSNS広告への投資は、経営判断が不可欠な重要事項です。現場任せにするのではなく、経営層や部長レベルの方々ご自身が、デジタルトランスフォーメーション(DX)の取り組みも含め、自社の将来に必要なものを判断することが、事業成長の鍵となります。
時代の変化とデジタル広告
近年、お客様の行動は多様化しており、それに伴いマーケティング活動も変化が求められています。新たな技術革新が市場を変える中で、デジタル広告の世界でも、データやAIの活用による自動化が急速に進んでいます。
事業規模を拡大するために新規顧客の獲得は最も重要な課題の1つであり、私たちはその解決策としてYouTube広告の活用を強く推奨しています。
インターネット革命の変遷とデジタル広告の台頭
船井総研が長年見てきた中で、インターネット革命はマーケティングのあり方を根本から変えてきました。
■ 1995年頃〜:インターネットが新たな販売チャネルに
1994年のAmazon創業や1997年の楽天創業を皮切りに、インターネットが販売チャネルとして確立されました。カカクコム(1997年)や食べログ(2005年)といったサービスも登場し、情報収集や購買行動がオンラインへ移行し始めました。■ 2000年頃〜:中小企業や医療分野でのインターネット活用
インターネットの普及に伴い、中小企業でもEC(電子商取引)で成功する事例が頻繁に見られるようになりました。2005年頃からは士業、2010年頃からは医療分野でも、インターネットを使った集客が一般的になりました。■ 2015年頃〜:広告費の主流がネット広告へ
テレビ、ラジオ、新聞、雑誌といったマスメディアから、インターネット広告が主流になりました。2022年には、ネット広告費がマスメディアの広告費を43%上回り、住宅や自動車、小売といった業界でもこの傾向が顕著です。
お客様の行動と広告戦略の変化
この10年で、お客様の情報収集や購買行動は劇的に変化しました。以前はGoogleやYahoo!での検索が主流でしたが、今やInstagramやYouTubeでのソーシャル検索、さらにはChatGPTやGeminiなどの生成AIを使ったAI検索も日常的に行われています。お客様は「欲しいもの・知りたいものだけ」を、おすすめや共有といった形で受け取ることを好むようになっています。
これに伴い、デジタル広告戦略やKPI(重要業績評価指標)も進化を遂げています。
・重要KPIの変遷
かつてのクリック数やCPC(クリック単価)といった指標に加え、CV(コンバージョン)やCPA(顧客獲得単価)、LTV(顧客生涯価値)など、ビジネス全体への貢献度を評価する指標が重視されるようになりました。・広告運用とリソース戦略の変化
検索上位表示を目指す時代から、データ分析と自動入札を活用したバナーや動画広告の併用、さらにはAIが顧客ニーズに合わせて最適な広告を生成・配信する時代へと移行しています。それに伴い、広告運用も自社兼任担当から専門部署、さらにはプロの広告代理店との連携へと、人材戦略も高度化しています。・AI活用の広がり
AIは入札単価やターゲティングの調整だけでなく、配信面の最適化やクリエイティブの自動生成までを担うようになりました。これにより、マーケティング部門の役割は「お客様の深い理解に基づいたメッセージ作り」へとシフトしています。
Webマーケティングの7つのトレンド
私たちは、企業が時代の流れに乗り、最適なデジタルマーケティング戦略を展開できるよう支援しています。特に、以下の7つの主要トレンドに注目すべきだと考えています。
1. キーワード検索から、文章・会話での検索へ
2. マルチモーダル:画像・映像での検索へ
3. データに基づいたパーソナライズされた検索結果
4. 広告(キーワード・画像)の自動生成
5. データに基づいたパーソナライズされた広告:費用対効果の最適化
6. 会話しながら必要な情報に辿り着く:AIチャットボットの活用
7. 検索、SNS、動画(YouTube等)+生成AI(Gemini等)の統合利用
YouTube広告の可能性
私たちの経験から、YouTubeはもはや単なる動画プラットフォームではなく、全世代の生活インフラと化しています。お客様が「商品・サービスを知る」という初期段階から「購入・意思決定」という最終段階まで、あらゆるシーンで利用される重要なメディアとなっています。
YouTubeの圧倒的なリーチと影響力
・世界第2位の検索プラットフォーム
YouTubeはGoogle検索に次ぐ、世界第2位の検索プラットフォームです。消費者の半数以上が、Google検索で商品やサービスを調べた後、詳細をYouTubeの動画で確認する行動をとっています。・幅広い年齢層へのリーチ
18歳以上のYouTubeユーザーは7,370万人以上おり、これは同世代人口の73%以上を占めます。さらに、「YouTubeは若者向け」という考えはもはや通用しません。45〜64歳のミドルシニア層でもユーザー数は2,740万人以上と、同世代人口の79%以上が利用しています。・高い愛着度
週に1度以上動画サービスを利用する人の80%以上が、YouTubeを「最も好きな動画サービス」と回答しており、単に利用されているだけでなく、深く愛されているサービスであることが分かります。
「出会い」から「行動」へ繋がる購買サイクル
YouTube上では、ユーザーの「出会い」が具体的な「行動」へと繋がる独自のサイクルが生まれています。
1. 新しい出会い:69%のユーザーがYouTubeショートのような短尺動画を通じて、知らなかった商品やサービスに出会います。
2. 興味の深掘り:その後、72%のユーザーが興味を深掘りするために、長尺動画を視聴します。
3. 購買行動への移行:最終的に75%のユーザーが、YouTubeで得た情報をもとに商品購入やサービス選択といった具体的な行動へ移っています。
主戦場は「ショート動画」と「テレビ画面」
近年のYouTubeトレンドとして、マルチフォーマット化とマルチデバイス化が挙げられます。
・YouTubeショートの成長
誕生から4年未満にもかかわらず、YouTubeショートの視聴者数は1年で20%以上増加し、ショート動画サービス全体で利用率第1位(ユーザー全体の62%)となっています。ショート動画は、新しい商品を知るきっかけだけでなく、購買ファネルの「理解」から「購入」に至る深い段階まで、高い効果を発揮します。軽自動車や医療保険、投資用不動産といった高価格帯・長期検討商材の購買にも繋がるデータがあり、幅広い年齢層にアプローチできるのが魅力です。・テレビ画面での視聴拡大
過去3年間で、コネクテッドテレビ(インターネット接続型テレビ)でのYouTube視聴時間は2倍以上に増加しました。1日あたりの視聴時間では、YouTubeが全ての放送局や他のデジタル動画サービスを抑えて第1位となっています。テレビスクリーンは「見たいものを投影するための1デバイス」へと変化しています。
これらのトレンドを捉え、モバイルでのショート動画視聴とリビングでのテレビ視聴、双方へのアプローチを強化することが、YouTube広告成功の鍵となります。
AIを活用したYouTube広告運用と戦略
YouTube広告は、単に動画を配信するだけでなく、お客様の購買ファネルの各段階に合わせた最適なアプローチ、Google AIを活用した効率的な運用、そして効果を最大化するクリエイティブが不可欠です。
Google AIを活用した広告メニュー
船井総研では、お客様のビジネス目的に応じて、Google AIを搭載した以下の主要な広告メニューを活用し、成果の最大化を目指します。
- ■動画リーチキャンペーン(VRC 2.0)
- 目的:ブランディング、商品認知の拡大に最適です。
- 特徴:複数のフォーマットを組み合わせ、Google AIが最も効率的にリーチを広げられるよう配信を最適化します。
- 効果:従来のキャンペーンと比較してリーチが54%拡大し、CPM(広告表示単価)を42%削減した実績があります。
- ■動画視聴キャンペーン(VVC)
- 目的:比較検討の促進、視聴回数の最大化に効果的です。
- 効果:従来の手法と比較して視聴回数が40%増加し、CPV(視聴単価)が30%削減されたほか、その後のブランド検索数も25%向上したと報告されています。
- 効果:従来の手法と比較して視聴回数が40%増加し、CPV(視聴単価)が30%削減されたほか、その後のブランド検索数も25%向上したと報告されています。
- ■デマンドジェネレーション(デマジェン)
- 目的:コンバージョン促進、購入意思決定の最終的な後押しをします。
- 特徴:YouTubeだけでなく、Google検索のフィードやGmailといった複数の面に広告を配信し、需要を喚起して行動を促します。
- 効果:既存のキャンペーンにデマジェンを追加することで、平均コンバージョン数が14%増加したという結果が出ており、活用している広告主の86%が成果に満足しています。
これらのAIを活用したメニューを組み合わせることで、認知拡大から販売促進まで、あらゆるビジネス目的を効率的に達成することが可能です。
データドリブン運用
YouTube広告の大きな強みは、効果を正確に測定し、改善を繰り返せるデータドリブンな運用ができる点です。
船井総研では、ユニークリーチレポートやブランドリフト調査など、Googleが提供する5つ以上のデータ計測ツールを駆使し、感覚的な評価ではなく、データに基づいた詳細な分析と改善サイクルをサポートします。これにより、皆様の広告費がより成果に繋がるよう支援します。
成果を最大化するクリエイティブ戦略:ABCDフレームワーク
どんなに優れた広告メニューや運用があっても、広告の成果はクリエイティブの質で決まります。Googleが提唱する「ABCDフレームワーク」は、成功するYouTube広告に共通する4つの原則です。私たちはこのフレームワークに基づき、効果的なクリエイティブ制作を支援します。
- 【A】 Attract(注目を集める)
- 視聴者の注目を集め、アテンションを維持します。
- ・ストーリー性:冒頭から視聴者を引き込み、感覚に訴える映像と音で最後まで見てもらう工夫が必要です。6秒以内にスキップされる可能性があるため、物語の核心に早く迫り、テンポの良い展開とクローズアップで引きつけます。
- ・視認性:音声やテロップでメッセージを補強し、モバイルの小さな画面でも見やすいよう、明るくコントラストの強い絵作りを意識します。
- 【B】 Brand(ブランドを認知させる)
- ブランドを認知させる工夫をします。
- ・頻度高くブランドを示す:広告の最初から最後まで、ブランドや商品を一貫して見せ続けることが重要です。
- ・音声の活用:YouTubeでは音声によるブランド名の言及が極めて重要です。ロゴや商品だけでなく、カラーやユニフォームなど、あらゆるブランド資産を活用して訴求します。
- 【C】 Connect(ブランドと繋がる)
- ブランドに対して考えさせたり、感じさせたりする繋がりを創出します。
- ・感情的な繋がり:商品やサービスを体験した時の喜びや実感を表現し、視聴者との間に繋がりを生み出します。
- ・共感:メッセージを絞って分かりやすく伝え、登場人物にストーリーを語ってもらうことで、ユーモアや驚き、好奇心といった感情に訴えかけます。
- 【D】 Direct(行動を促す)
- 視聴者の行動を促します。
- ・具体的な行動指示:広告を見た視聴者に、次に何をして欲しいのかを明確に伝えます。
- ・明確なCTA:「アプリをダウンロード」「今すぐ購入」といった具体的な行動を促すフレーズ(CTA:Call-to-Action)や検索バーを明確に入れます。画面上のCTAをナレーションでも伝えることで、メッセージがより確実に届きます。
船井総研がお手伝いできること
船井総研では、YouTube広告が全世代の生活インフラとなり、商品認知から購入・意思決定まであらゆるシーンで活用されている現状を深く理解しています。特に、モバイルでのショート動画視聴とリビングでのテレビ視聴が急速に拡大している中で、これらを捉えた戦略が不可欠です。
私たちは、単に広告を配信するだけでなく、Google AIを活用したメニューで「認知拡大」から「販売促進」まで、お客様のあらゆるビジネス目的を効率的に達成できるよう支援します。また、クリエイティブの「ABCD」原則に基づき、質の高い広告制作をサポートします。効果を正確に測定し、改善を繰り返すデータドリブン運用がYouTube広告の最大の強みだと捉え、皆様の広告運用力を高める支援を行います。
WebやSNS広告への投資は、経営判断が伴う重要な課題です。新規顧客を大幅に増やしたいという目標は、現場の担当者だけでは達成しにくいものです。テクノロジーやDXの取り組みについても同様に、経営判断が必要です。
船井総研は、貴社の状況を深く理解し、YouTube広告が貴社の将来に必要かどうかを判断するサポートから、具体的な戦略立案、運用、成果改善まで一貫して支援させていただきます。最短で本日からの広告開始も可能であり、素材がなくても、少額(1円から)でも始められるのがYouTube広告の利点です。
ぜひ一度、貴社のビジネスにおけるYouTube広告の可能性について、私たちにご相談ください。共に貴社ビジネスの成長を促進できることを楽しみにしております。