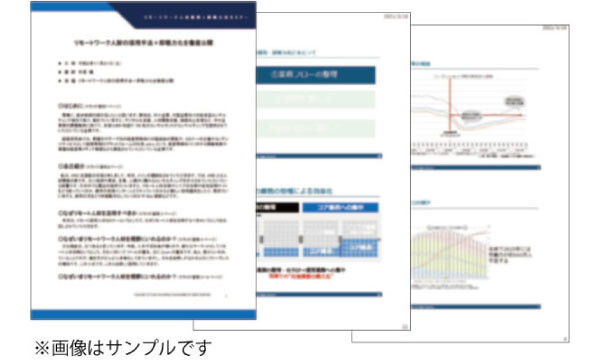第一講座振り返り-保育所等訪問事業のメリット
まず第一講座の振り返りでございますけれども、改めまして保育所等訪問支援のメリットについて、障害児通所支援事業をされている児童発達支援放課後等デイサービスをされている皆様でありましたら、新たな収益を得ることができますというところです。
なおかつ既存の人員を活かして運営できるというところもこちらの事業の大きなメリットになってまいります。今働かれている方を訪問支援という形を取ることができますので、既存事業活かしながら、なおかつ既存のリソースを使って、新たな収益を得られるというところが事業の大きなメリットではないかなと思います。
これから関係機関との連携というのはより重要になってくるんですけれども、こちらは非常に連携をしなければならない事業になります。なので、通所支援の営業というスタイルではなくて、関係性を作りながらしていくというところが結果的に通所事業の営業にもなりますし、私たちの専門性といったところも伝えることができる、そういった事業ではないかなと思います。
そして4番目、保護者の満足度向上ということで通所いただいている方を学校だったり幼稚園、保育園でご支援もできるというところで、支援をできる回数、見る時間というのをより増やしていくことができますし、保護者様とのコミュニケーションを、回数として非常に増やしていくことができる事業になっております。なので、非常に相乗効果を作ることができる事業ではないかと思います。
保育所等訪問支援立ち上げの前に…
これから立ち上げる前にというところでご確認の部分ですけれども、まず1番、保育所等訪問支援はあくまで付加事業ということです。こちらは保育所訪問支援だけを立ち上げることももちろん可能になります。しかしながら、今、全国的な保育所等訪問支援のうまくいっている例というところでいきますと、まずは児童発達支援、放課後等デイサービス、通所事業された上に付加をされるといったケースの方が軌道に乗せやすく、うまくいっております。また保育所訪問支援は非常に単価も高くあるんですけれども、回数自体を1日に何人も一気に増やしていくことが難しい事業ではございますので、まだ障害児通所支援事業である放課後等デイサービスをされていないということでありましたら、是非通所支援事業の方から順にご検討いただければなと思っております。
続きまして2番、より専門性が求められる事業というところでございます。これは、行政から保育所等訪問支援というのは専門機関という立ち位置を取るように指示をされております。ですので、訪問先で 福祉という側面からアドバイスを求められているという事業でございます。ですので、信用、信頼といったところがとても大切になってきます。また、この訪問先の方々からすると、外部の方が来るというところで専門性の部分が大事なんですけれども、この人はどういう人なのかなっていうところも疑問に思われることも十分考えられますので、社会人のスキルもとても大事になってきます。ですので、やみくもにどんどん行くわけにもいかず、しっかりと準備をして事業を始めていただきたいなと思っております。
それから、もちろん配置のルールがございますので既存に変化することは間違いないですけれども、状況によっては増員もしっかり必要になってくる事業ではございますので、この辺りを厳密に見ていきながら事業の準備をいただければなと思っております。
保育所等訪問支援のポイント-保育所等訪問支援事業を成功させるポイント
こちらのポイントに沿ってご説明をさせていただきます。まずは保育所等訪問支援の仕組み、続きまして始め方、保育所等との関わり方、支援の内容、支援の展開の仕方という順でご説明させていただければと思っております。
保育所等訪問支援-保育所や幼稚園、学校に行って直接支援、間接支援を行う
まず仕組みの部分ですけれども、まず保育所等訪問支援という、「保育所等」と書いておりますが、こちらは保育所、幼稚園、学校どちらも訪問が可能になります。学校でいきますと中学校や高校といったところも可能になります。内容としましては、直接支援、間接支援を行うというような位置づけになっておりますので、こちら後ほどご説明をさせていただきます。
保育所等訪問支援
人員の体制ですけれども、まず児発管の方が1名必要になります。児童発達支援管理責任者になります。それから訪問支援員という方が1名必要になってまいります。ただ、実際に利用が始まりますと訪問支援1名といった体制ではなかなか回ってこなくなりますので、こちら人数決まっている訳ではないですけれども、訪問支援の体制4名のような形で、通所事業と兼務しながら運営されているところもございます。それから事業所については、相談室の方は共有で大丈夫な形になっているのと、この訪問支援といったところが、自発、放課後デイと兼務で配置することができるといったところが既存人員を活かすことにつながってまいります。
保育所等訪問支援
訪問支援というのは何かというところなんですけれども、こちらはそのままの文章でございます。障害児支援に関する知識及び相当の経験を有する児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士又は心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者、というような定義付けがなされております。ですので、この児童指導員、保育士というところが入っておりますので既存人員を活かすことができる可能性が非常に高いというような立ち位置でございます。また、専門的支援加算を取られている事業様では、理学療法、作業療法士がいらっしゃる事業様もあると思うんですけれども、そういった方が訪問支援をすることも可能となっております。
保育所等訪問支援-職員配置の目安
こちらは職員配置の目安というところで、あくまで目安ではございますけれども、何人ぐらい必要かといったところを書かせていただいております。上の方が計算の軸になるのですが、1日の通所の平均人数が10名以下と仮定いたしまして、訪問支援の1日平均が0、1、2というように入れさせていただいております。左側3列が営業日数が週5日、右側が週6日というところでございます。必要数としましては、こちら、サービス提供時間6時間、条件時間160時間というところを目安に計算させていただいておりまして、訪問支援の時間というのは大体3時間で計算されるところが多くなります。実際の支援の時間としては1時間から2時間になるのですが、書類作成の時間だったりも含めるといった形で1回3時間という形でこちらは計算させていただいております。
見ていただきましたらわかる通り、訪問支援が1日1名というところでありましたら、常勤換算でいきますと週5日営業の場合、1.9というところになります。ただ、週5日営業で訪問支援が1日2名のような体制になった時に、2.3という値になってまいります。ですので、2.3を超えてくるというところがありましたら明らかに既存人員を超えて必要というところになってきますので1日1名支援以上になってきますと、増員がおそらく必要ではないかなという状況でございます。また、週6日営業の場合でも、毎日1名の段階から2.3というところで2を越えてくるような状態になってきますので、訪問支援の回数自体が20回程度を月で超えてきますと、恐らく増員が必要な状況に近づくのではないかなと考えております。皆様の配置の人数については、それぞれ違いますので一概には言えないですけれども目安としてこちらの数値を意識いただければなと思っております。
保育所等訪問支援-タイムスケジュールの例
続きまして、こちらはタイムスケジュールの例ということで、こちらはある事業者様の例でございます。児童発達支援放課後等デイサービスのサービス提供時間と保育所等訪問支援のサービス提供時間、被ってももちろん可能ではあるのですが、被ってしまいますとその時間分は通所の時間から削らないといけません。ですので、こういった形でサービス提供時間を分けて、1日の中で二つの仕事をしていただいて常勤計算するというところも出てきております。なので、このパターンでいきますと、午前中に訪問支援に行きまして、午後から通所の方で働くというような内容になっております。訪問支援の方は、特に幼稚園、保育所等ですと「午前中に来てください」というようなケースが比較的多くなってまいりますので、通所のほうの利用時間と合わせながら、どういった時間割りにするのかというのも是非検討の中では決めていく必要がございます。
保育所等訪問支援-報酬単位
続きまして、報酬単価になります。基本報酬といったところが 1,071 単位になります。大きな加算としましては、訪問支援員特別加算というものがございます。こちらを取得する想定でいきますと、処遇改善加算を除き、1,071~1,921 単位というところになります。保育所等訪問支援というのは 1 人当たり月 2回支援というようなルール設定になっておりますので、仮に月 2 回支援いたしまして、1 人当たりが大体38,420 円というような単価になってまいります。これは単純計算で契約者が 8 名いますと、大体 30 万円程度というような形になってくるのが保育所等訪問支援の売り上げになります。その他の加算としまして、初回加算や家族支援加算などがございますけれども、主にはこの上のほうの基本報酬といったところが売り上げになってまいります。この人数自体を何人まで増やしていくのかというラインと、あとは先程の訪問支援回数を増やしていくと増員も必要になってきたりとか、サービス提供時間によっては現段階で既にもう増員しないとできないという可能性もありますので、その辺りの人件費のバランス等を見ながら、訪問支援を始めていただくというような流れになってまいります。
▼続きは下記からダウンロードいただけます。