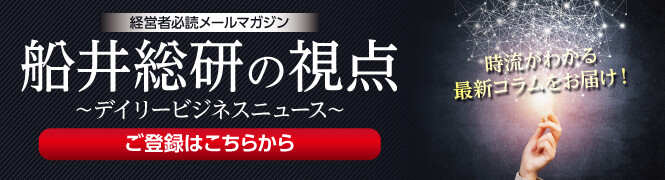2025年1月~6月における経営コラムの上位アクセスTOP5をご紹介いたします。
第5位:地域コングロマリット経営のメリット・目指すべき理由
https://www.funaisoken.co.jp/press/14936
こちらは「地域コングロマリット経営」を解説したコラムです。
【内容】
地域コングロマリット経営とは「特定の地域で複数の事業体を持つ経営」を意味します。
これは単なる多角化経営とは一線を画し、縮小経済下で成功確率が低いとされる、管理コストがかさみシナジーが生まれない多角化とは異なります。
地域コングロマリット経営の条件として、それぞれの事業が互いにプラスをもたらしシナジーを生むこと、そしてそれぞれの事業体を「会社として経営する」役割を担う人材が多数いる、強い組織になっていることが挙げられています。
また、「第二本業」を創出し、新たな事業を十分な規模に成長させることを推奨しています。
この経営のメリットは多岐にわたり、例えば「不人気業種」とされる事業の弱点を、カフェなど人気の高い事業と組み合わせることで採用力を高められます。
また事業の数だけ経営者が必要となるため、経営を担う力のある人材が次々と輩出され、多くの優秀な人材が集まり育つことで、地域経済をリードする存在となることを目指します。
地域にとって不可欠な存在となることで、後継者難の企業からのM&A相談を優先的に得られたり、地域からの様々な協力依頼が来るようになったりといった好循環が生まれると説明されています。
これは地域で一番化した企業が目指すべき、有効な経営戦略として位置づけられています。
この「地域コングロマリット経営」については、2023年8月31日に発売された書籍『新規事業を立ち上げ第二本業へと育てる 地域コングロマリット経営』で詳しく解説されており、「100億企業化」を目指す経営者に向けた内容となっています。
【詳細はこちら】
第4位:“アナログ”トランスフォーメーション(AX)
https://www.funaisoken.co.jp/press/8113
こちらは「アナログトランスフォーメーション(AX)」を解説したコラムです。
【内容】
AXはデジタルトランスフォーメーション(DX)と共に理解されるべき造語です。
一般的にDXが「“デジタル”技術で世の中をより良いものにする」と定義されるのに対し、AXは「“アナログ”技術で世の中をより良いものにする」とされています。
さらに具体的に言うと、AXは「人間が行うマニュアル化・標準化」を指します。
このコラムで伝えたい主要な点は、DX(デジタルトランスフォーメーション)成功の最大のポイントが「アナログトランスフォーメーション」であるということです。
例えば営業管理のDX化を検討する際、営業担当者それぞれが異なるフォーマットで管理し、それが会社全体で共有されない状況では、営業が属人化し、個人の経験やスキルに差が生じがちです。
このような状況で高額なSFA(営業管理システム)を導入しても、営業マン個々人のバラバラなフォーマットを全社で標準化・統一するという「アナログトランスフォーメーション」ができていなければ、データ入力が進まず、結果としてDXは失敗に終わる典型的なパターンであると説明されています。
したがってDXを成功させるためには、アナログ段階での全社的な標準化が非常に重要であることが強調されています。
【詳細はこちら】
第3位:経営『者』コンサルティングで、サステナグロースカンパニーをもっと
https://www.funaisoken.co.jp/press/20559
こちらは船井総合研究所による事業承継・M&Aのワンストップサービスを提供する新会社の設立を解説したコラムです。
【内容】
船井総合研究所は2024年11月25日に、あがたグローバル経営グループと合弁で新会社「船井総研あがたFAS」を設立したことを発表しました。
この新会社設立の背景には、現在日本経済の今後を左右する重要課題であると認識されている、中堅・中小企業の事業承継問題があります。
新会社「船井総研あがたFAS」は親族承継、従業員承継、第三者へのM&A(譲渡・譲受)といった多様な事業承継の選択肢や、それぞれの準備に関する経営者の悩み、相談事に対応します。
具体的には、自社の企業価値(譲渡価格)の考え方や、M&A(譲受)を成長戦略にどう位置づけるか、持ち込まれる案件の見極め方なども含め幅広い相談に応じます。
船井総研の業種コンサルタント、事業承継コンサルタント、M&Aコンサルタントに加え、税理士、公認会計士といった専門家が連携し、総合的なワンストップサービスを提供することを目指しています。
船井総研は2017年から事業承継・M&A専門部門を設置し、財務・税務面ではあがたグローバル経営グループと協力してきました。今回の合弁会社設立により、その専門性と総合力をさらに高め、中小企業の経営課題解決に貢献していく意向です。
【詳細はこちら】
⇒経営『者』コンサルティングで、サステナグロースカンパニーをもっと
第2位:年商30億の壁を越え、100億企業となるための戦略シフト
https://www.funaisoken.co.jp/press/13245
こちらは「年商30億円の壁を越え、100億円企業となるためのコングロマリット化戦略」を解説したコラムです。
【内容】
高成長を続ける中小企業が年商20~30億円で成長が鈍化する「壁」を乗り越え、年商100億円を達成するには、短期的な「事業戦略」だけでなく中長期的に企業価値を高める「経営戦略」へのシフトが重要であると指摘されています。
これは「費用対効果」から「投資対効果」への戦略転換を意味します。
その具体的な戦略が「コングロマリット化(多角化)の事業投資」です。
まず本業の高収益化でキャッシュフローを改善して、金融機関からの信用力を高めて融資枠を拡大し、その既存事業を担保に融資を受け、成長分野に投資して「第二の柱」となる新規事業を創出します。
さらに多角化を進め、第三、第四の柱を築くことで業績アップを加速させます。
新規事業の選択では既存事業との「市場関連性」や「商品関連性」が極めて重要であり、これにより本業を含む他事業にも相乗効果が生まれるコングロマリット構築が成功の鍵とされています。
コラムでは、関連性の高い新規事業で本業売上を倍増させた住宅会社の事例が紹介されており、船井総合研究所がこの「コングロマリット化×新規事業」によるロードマップ作成を支援しています。
【詳細はこちら】
第1位:【働き方改革の注意点】「年間休日数」を増やす前に「生産性」向上
https://www.funaisoken.co.jp/press/8646
こちらは「働き方改革における年間休日数増加の注意点と生産性向上の重要性」を解説したコラムです。
【内容】
近年、採用難や従業員の働きやすさへの配慮から年間休日数を増やす企業が増えていますが、コラムでは時期尚早な増加は危険だと警鐘を鳴らしています。
有給休暇取得の推進や、年間休日増加による労働者の時間単価上昇、時間外手当の膨らみといった経営上の考慮点があるためです。
年間休日を増やしつつ、求職者や従業員への魅力を高める流れは続くものの「生産性向上」が働き方改革推進には不可欠であると強調されています。
生産性向上のための具体的な施策として、ビジネスモデルのブラッシュアップ、新規業態の立ち上げ、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進による業務効率化、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の活用などが挙げられています。
また企業側の仕組みだけでなく、従業員一人ひとりが自身の時間単価や業務の生産効果を意識し、生産性向上に取り組むことの重要性を訴え、まずは生産性の見える化から意識改革を図ることを提案している内容です。
【詳細はこちら】
⇒【働き方改革の注意点】「年間休日数」を増やす前に「生産性」向上
以上、TOP5の紹介でした。
2025年上半期の第1位は「働き方改革」に関するコラムでした。
永遠の課題とも言われるこの取り組みはまだまだ注目が集まりそうです。
今後も注目の経営コラムをランキング形式にてお届けいたします。