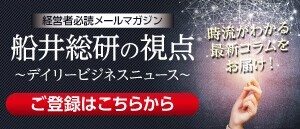スマートフォンの普及、5G通信網の拡大、そしてYouTubeや各種SNSの隆盛により、動画 マーケティングは現代の企業活動において欠かすことのできない中核的な施策となりつつあります。テキストや静止画では伝えきれない情報量と熱量を届けられる動画は、顧客の理解を深め、強いエンゲージメントを生み出す力を持っています。
しかし、「とりあえず動画を作ってみたが、成果に繋がらない」「YouTubeチャンネルを開設したが、再生回数が伸び悩んでいる」といったご相談をいただくケースも少なくありません。
多くの企業が動画 マーケティングに乗り出す一方、その戦略設計に課題を抱えているのが実情です。
単発的な動画制作や、「バズらせたい」という漠然とした期待だけでは、継続的な成果創出は困難です。そこで重要となるのが、Googleが提唱する動画コンテンツの戦略的フレームワーク、「HHH戦略(スリーエイチせんりゃく)」です。
本コラムでは、このHHH戦略の基本的な考え方と、成果を生み出すための活用ポイントについて解説します。
HHH戦略の概要
HHH戦略とは、Google(YouTube)が提唱した、動画 マーケティングにおけるコンテンツを3つの異なる役割・目的に分類するフレームワークです。3つの「H」は、それぞれ以下の頭文字を表しています。
- Hero(ヒーロー)コンテンツ:認知拡大・潜在層へのリーチ
- Hub(ハブ)コンテンツ:見込み客との関係構築・ファン化
- Help(ヘルプ)コンテンツ:顕在層の疑問解決・顧客サポート
これら3つのコンテンツは、ターゲットとする顧客のフェーズ(認知・興味関心・比較検討・購買)や、動画に持たせる目的が明確に異なります。HHH戦略の最大のポイントは、これら性質の異なる動画を単体で考えるのではなく、全体として体系立てて設計・配置することにあります。
やみくもに動画を量産するのではなく、顧客の態度変容プロセスに合わせて、適切な動画を適切なタイミングで届けるための「地図」が、HHH戦略なのです。
3つの「H」それぞれの役割と具体例
HHH戦略を構成する「Hero」「Hub」「Help」それぞれの役割と、どのような動画が該当するのかを具体的に見ていきましょう。
1. Hero(ヒーロー)コンテンツ:認知拡大
Heroコンテンツの目的は、「圧倒的な認知獲得」です。
まだ自社や自社の商品・サービスを知らない、あるいは関心度の低い「潜在層」に対して、広くリーチすることを狙います。大規模なキャンペーンや新商品の発表など、企業が最も伝えたい「大きな話題」を発信する際に用いられます。
- ターゲット:潜在層、一般大衆
- 目的:ブランドの認知度向上、大規模な話題喚起(バイラル)
- 特徴:
- エンターテインメント性、感動、驚きなど、感情に強く訴えかける内容
- 高いクリエイティブ品質と制作コストがかかる傾向
- 有名タレントやインフルエンサーを起用することも多い
- 配信頻度:低頻度(四半期に1回、半年に1回など、大型イベント時)
- 具体例:テレビCMと連動したWeb動画、感動的なブランドストーリー動画、社会的なメッセージ性の強い動画
2. Hub(ハブ)コンテンツ:関係構築
Hubコンテンツの目的は、「見込み客との継続的な接点の構築とファン化」です。
Heroコンテンツで認知した層や、既に一定の関心を持つ層(見込み客)に対し、有益な情報や魅力的なコンテンツを「定期的」に届けることで、関係性を深め、ブランドへの好意度を高めていきます。YouTubeチャンネル運営の「核(ハブ)」となるコンテンツです。
- ターゲット:見込み客、既存顧客
- 目的:継続的なエンゲージメント獲得、ファン化促進、ブランドロイヤルティ向上
- 特徴:
- ターゲットの興味・関心事に寄り添ったシリーズ企画
- 継続視聴を促すための工夫(番組仕立て、定期配信)
- Heroほどのコストはかけず、継続性を重視
- 配信頻度:中頻度(週1回、月2回など、定期的に)
- 具体例:業界トレンドの解説シリーズ、商品の活用術(応用編)、開発秘話、顧客インタビュー、対談企画
3. Help(ヘルプ)コンテンツ:疑問解決
Helpコンテンツの目的は、「顕在層の具体的な悩みや疑問の解決」です。
自社の商品やサービスに関連する「具体的なキーワード」で検索している、ニーズが明確な層(顕在層)に対して、「How to(ハウツー)」や「Q&A」といった形で直接的な答えを提供します。顧客の課題解決に直結するため、信頼獲得や購買・導入の後押しに繋がります。
- ターゲット:顕在層(具体的な悩み・疑問を持つユーザー)
- 目的:検索ニーズへの対応、問題解決、顧客満足度の向上、購買の意思決定支援
- 特徴:
- 「〇〇 やり方」「〇〇 比較」「〇〇 トラブル」といった検索キーワードを強く意識
- 実用性、明確さ、簡潔さを重視
- 一度作成すれば資産として蓄積される(ストック型コンテンツ)
- 配信頻度:随時(顧客のニーズや検索トレンドに応じて追加・更新)
- 具体例:商品の使い方マニュアル、サービス導入の手順解説、よくある質問(FAQ)動画、トラブルシューティングガイド、導入事例(課題解決ストーリー)
HHH戦略を成功に導く3つのポイント
このHHH戦略を導入し、動画 マーケティングの成果を最大化するためには、以下の3つのポイントを意識することが重要です。
1. 「全体最適」で設計する
Hero、Hub、Helpは独立したものではなく、相互に連携してこそ真価を発揮します。例えば、「Hero動画で広く認知を獲得し、興味を持ったユーザーをHub動画(チャンネル登録)に誘導して関係性を深め、検討段階に入ったユーザーが検索するHelp動画で疑問を解消し、購買を後押しする」といった導線設計が不可欠です。どれか一つに偏るのではなく、自社のリソース配分を考慮しながら、3つのHのバランスを取ることが求められます。
2. 「誰に・何を」を明確にする
全ての動画で「バズ」を狙う必要はありません。Helpコンテンツは、再生回数が少なくても、濃い見込み客の課題を解決できれば成功です。逆にHeroコンテンツは、直接的な売上よりも、どれだけ多くの人に届いたかが重要です。各コンテンツの目的(KGI/KPI)とターゲットを明確に定義し、その目的に応じた動画制作と評価を行う必要があります。
3. 継続的な運用とデータ分析
特にHubコンテンツとHelpコンテンツは、一度作って終わりではありません。Hubは定期的な配信による「接触回数の担保」が、Helpは「顧客ニーズの網羅性」が重要です。また、配信後はYouTubeアナリティクスなどのデータを分析し、「どの動画が視聴維持率が高いか」「どのような検索キーワードから流入しているか」を把握し、常にコンテンツの改善を続けるPDCAサイクルを回すことが、動画 マーケティング成功の鍵となります。
まとめ
動画 マーケティングは、単なる「動画制作」ではなく、顧客とのコミュニケーションを設計する「戦略的活動」です。GoogleのHHH戦略は、その設計図を描く上で非常に有効なフレームワークと言えます。
自社の顧客が今どのフェーズにいて、どのような情報を求めているのか。それに対し、「Hero」で広く呼びかけ、「Hub」で関係を深め、「Help」で疑問を解決するという体系的なアプローチが、動画という強力なツールを真の経営成果に結びつけます。
まずは自社の現状の動画コンテンツが、HHHのどれに該当するのか、あるいはどれが不足しているのかを棚卸しすることから始めてみてはいかがでしょうか。
【詳細はこちら】
 | 執筆者: マーケティングイノベーション支援部 ディレクター 松本 治 まつもと おさむ |
EC広告運用・集客の成果を最大化するポイント:AI・動画活用と人間の役割