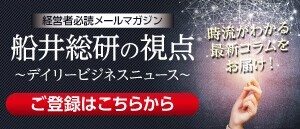2025年はIPO(新規上場)をとりまく環境が大きく変化しております。
まず知っていただきたい事実として、2025年の新規上場企業数ですが6月末時点でグロース市場が18社に対して、TOKYO PRO Market(東京プロマーケット)が21社となっており、新規上場企業数でTOKYO PRO Marketがグロース市場を上回っている状況です。このペースで進んだ場合、通年ペースでもTOKYO PRO Marketへの新規上場企業数がグロース市場を初めて上回る可能性があります。
(東京証券取引所のデータを船井総研にて集計)
今まではIPO、新規上場といえば「まずグロース市場を目指す」というケースがほとんどでしたが、「まずTOKYO PRO Marketへの上場を目指す」、もしくは「グロース市場を目指していたがTOKYO PRO Marketへの上場へ変更する」という会社が増えてきている状況になります。では、なぜこのような大きな変化が起きているのでしょうか。
■グロース市場時価総額100億円について
東京証券取引所(以下、「東証」)が2025年9月2日に公表した「グロース市場における今後の対応」により、実質的にグロース市場上場後の5年以内に時価総額100億円以上とすることが求められることになりました。
| 2025年9月2日の東証による「グロース市場における今後の対応」にて公表されたグロース市場の新基準の内容としては、 ①上場10年経過後から時価総額100億円未満の場合 「事業計画及び成長可能性に関する事項」において100億円を意識した成長戦略を開示・実行 ②2030年時点で、追加で必要な期間とその計画を開示した場合は、当該期限まで上場を認める |
となっており、2025年4月22日に公表された「案」の内容が基本的に新基準として適用されております。これらは突然決まったことではなく、2023年12月頃から東証の「市場区分の見直しに関するフォローアップ」にてグロース市場についての検討が進められておりましたので、以下、経緯を一部抜粋してご紹介します。
| ■2023年2月15日 市場区分の見直しに関するフォローアップ会議にて ・近年は毎年100社前後が上場(約7割がマザーズ・グロース市場に上場)している ・IPO時の時価総額規模・資金調達額は海外と比べて相対的に小さい ・時価総額100億円未満かつ資金調達額10億円未満のIPOが過半を占めている ・機関投資家の参入は限定的(配分先の8割以上が個人投資家) ・資金調達額よりも売出総額の方が大きいIPOが約6割を占める (引用:市場区分の見直しに関するフォローアップ会議 2023年2月15日) 以降、おおむね2,3か月起きに開催された「市場区分の見直しに関するフォローアップ」にてグロース市場に関する議論が重ねられています ■2025年4月22日 東証の「グロース市場における今後の対応(2025年4月22日)」にて グロース市場の上場維持基準の⾒直し(案)として ・上場維持基準を 現行:上場10年経過後から、時価総額40億円以上 案 :上場5年経過後から、時価総額100億円以上 *2030年以降、上場5年経過している上場企業に適用 が公表 (引用:グロース市場における今後の対応 2025年4月22日) |
東証のこのような議論と並行して、IPO準備企業においては
「証券会社が上場時に時価総額100億円もしくは200億円を見込めないと主幹事契約をしてくれない」
「主幹事証券と契約して、直前期もしくは申請期まで進んでいるが、時価総額の観点から主幹事証券から上場時期を先延ばしにするようにいわれた」
などというご相談が少しずつ増えてきておりました。
2025年に入ってからは、特に
「グロース市場への上場を目指して主幹事証券と契約しているが、予定していたスケジュールでの上場が難しいので、東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)への上場を検討したい」
というご相談が多くあります。
■IPO準備中の会社の対応
グロース市場時価総額100億円に直面して、主幹事証券との契約もしくは上場スケジュールが進まない企業の選択肢としては
①事業計画を見直して(M&Aも含め)上場時期と合わせて再検討
②地方市場への上場を検討
③東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)への上場を検討
④M&Aでの売却を検討
のいずれかで検討されているケースが多いです。
そこで、「③東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)への上場を検討」する企業が増えてきたこともあり、東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)への新規上場企業数がグロース市場を上回っていることにつながっています。
(写真:船井総研がJ-Adviserとして2025年12月にTOKYO PRO Marketに上場したBABY JOB株式会社様の上場セレモニーの様子)
■J-Adviserについて(船井総研もJ-Adviser)
ここで、東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)への新規上場企業数が増加している背景として、J-Adviserによる活動もご説明させていただきます。
東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)へ上場するにあたっては主幹事証券ではなく、東証から認定されたJ-Adviserと契約する必要があります。J-Adviserによって上場の適格性を審査して新規上場する流れになります。
船井総研も2022年4月にJ-Adviser資格を取得して、J-Adviserとして活動していることから多くのリアルなご相談を頂いている状況にあります。J-Adviserによる上場準備中の企業様向けのアプローチも増加しています。そのようなことから、東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)という市場の制度だけでなく、メリット、デメリットも広く知っていただけ機会が増え認知度が高まっている状況にあります。
今回、お伝えしたいのは、「グロース市場時価総額100億円」というテーマはもちろん、IPO(新規上場)を目指す企業の経営者様には、IPOの最新の状況をキャッチアップした上で上場準備を進めていただきたいということです。
経験者である上場経営者の方にご相談されるのも非常に大事なことではありますが、10年前、20年前にIPO(新規上場)された経営者の場合、基準や制度に関する知識などがそこで止まっている可能性があります。
よく聞くのが「上場企業の社長に東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)の相談をしたら、そんな市場上場しても意味がないよ、と言われた」というコメントですが、そのようなケースの場合、東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)という市場が
・2024年は1年間で50社が上場した
・合計で約200社近くが上場した市場
・2025年6月末時点では新規上場企業数がグロース市場を上回っている
という事実を知らないケースがほとんどです。
今回ご紹介させていただいたように、IPO(新規上場)に関しては、東証の制度としての大きな変化がありますし、また市況に合わせたトレンドの変化、さらには証券会社や監査法人の対応状況の変化もあるため、常に最新の情報をアップデートしておく必要があります。
IPO(新規上場)に関しての最新情報を知りたい、東京プロマーケット(TOKYO PRO Market)について詳しく知りたい、という経営者の方は、IPOコンサルであり、かつ東京プロマーケットのJ-Adviserである船井総研にお気軽にご相談ください。