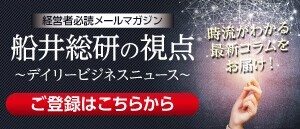弊社では新規事業開発のコンサルティングを数多く実施させて頂いておりますが、その中で事業計画についても策定させて頂いております。また、ご相談を頂く中でも、「事業計画を作らないといけないが、何から手を付けたら良いか分からない」といったお声も多く頂いております。そこで、本コラムでは弊社のこれまでの支援事例を踏まえて、事業計画づくりにおいてポイントとなる点をいくつか解説させて頂きます。もちろん弊社にご相談頂くのは大歓迎ですが、まずは自社だけで取り組みたい方に向けてポイントを解説させて頂いております。巻末にはこれらの点も含むレポートも無料でダウンロード可能でございます。
そもそも、新規事業開発において事業計画書が重要なのか?
「どうせ将来のことなんか分からないんだから、精緻な計画なんて必要?」
とのご意見もあろうかと思いますが、結論としては、事業の目指す姿やその検討背景・ロジックを明確に示すことにより、事業推進をスムーズにするとともに変化への対応力を向上させ、新規事業の成功確率を高めることが可能になると考えます。
特に作成後にインタビューさせて頂いた中で、「意外な効果」として、例えば以下のような声は頂いております。
- ①目指す姿を言語化・定量化・図式化することで、事業推進メンバー間での齟齬を無くしてスムーズに推進ができる。 意外とメンバー間で実は齟齬があったり、重要なポイントを推進者1人しか理解しないまま進めてしまうケースが多いのが実態です。また、重要な前提条件や市場調査の結果が間違ったまま、それに気づかずに進めてしまうケースもあります。検討フェーズの初期段階で、「今分かっていないこと」も含めて、アイディアや考え方、前提などを洗い出して全員の前に出すだけでも、十分に価値はあると考えています。
- ②前提条件やベンチマーク企業、検討に用いたロジック等を記すことで、状況変化に対して「どのくらい事業に影響するか」が追えるので、柔軟に対応しやすくする冒頭で説明した通り、将来のことは見えないことも多くあります。しかし、将来何かが変わった際に、それが事業全体にどう影響するかを振り返るためにも、事業の前提を整理して書き出しておくことは重要です。
事業計画書には何を書くべき?
よくある誤解として、事業計画を「数値シミュレーション(売上や投資額、利益の計画)」のみと認識されている方も多いのですが、上に書いた通りそれだけでは不十分です。船井総研が考える事業計画の典型的な記載事項(目次)としては以下の通りです。
それぞれにどういったことを記載すべきかについては、詳細は巻末からアクセスできる資料をご確認いただければと思いますが、以下では多くの新規事業開発でポイントになる箇所について解説させて頂きます。
ビジネスモデルを表現する
簡単そうに見えて、意外と「誰でも分かる」ように表現するのが難しいページです。ただし多くの推進者の頭の中にはすでにあることが多い(逆に、これを表現しようとして考え切れていなかった視点が洗い出されるケースもあります)
まずはこの事業を理解していない社内の方に説明して伝わるか、そのフィードバックをもらいながら作っていくのが良いと思います。そしてその際に重要なのが、いまの既存事業との違いです。例えば、顧客が同じであればそこまで顧客にフォーカスする必要はないと思いますが、既存事業と顧客層が異なるのであれば、下の「ペルソナ例」のように、かなり解像度を上げて表現する必要があります。また事業スキームについては、ビジネスモデルキャンパスのように既存の戦略フレームワークも無いわけではないですが、実際に使ってみると伝わりにくいケースが多いです。下のようにプレーヤー相関図で表現することも多いですが、実際には何パターンか作ってみて「必要な情報が整理されて表現されている表現形式は何か?」と考えてみることが有効です。
成功確率を高める重要指標・要因を特定する
数値シミュレーションとも大きく関係しますが、事業をまずロジックツリーのような形式で表記してみます。その後で、以下のような視点でチェックしてみると、KPI(簡単にいうと、コレさえ押さえていればこの事業の管理ができる、という要素。戦略フェーズごとに変えることもある)を特定することが可能になると考えます。
✔KPIがすべて達成されたら、KGIは達成できるか?(他の要素は無いか?)
✔KPIの中には、結果を示す遅行指標(例:受注率)だけでなく、結果に繋がる行動を示す先行指標(例:提案数、見込み客数)が含まれているか?
✔類似事業(他社での成功事例)ではどのような数値を重視していたか?
数値シミュレーションを組み立てる
数値シミュレーションの立て方としては、まずは事業を定量化するために、売上高(または営業利益)を構成する要素を分解します。基本的には、四則演算(足し算・引き算・掛け算・割り算)や最大・最小などで表現できるロジックツリーに分解し、それぞれの指標(自社でコントロールできる指標/外部環境で決まる指標)の推移を計画します。
それぞれの要素については、外部データから推計したり、競合調査から目安数値を取得したりして推計していきます。そしてそれらを時系列で組み立てていきます。具体的には、上の各数値が、事業推進・戦略実行によりどの程度で推移するか、他社事例等に基づき推計を行い、事業の定量化を行っていきます。
いかがでしょうか?本コラムでは、事業計画書づくりにおいて特にポイントになる点を解説させて頂きました。「事業性評価」「ミッション・ビジョンの設定」「マーケティングプラン策定」「人材・組織戦略」「ロードマップ策定」といった、本コラムで解説しきれなかったその他の点含め、以下のダウンロードレポートではさらに深掘りした情報を無料でご提供しております。ぜひこちらもご確認ください。
 | 執筆者: 価値向上支援本部 事業イノベーション支援部 マネージャー 内田 洋平 うちだ ようへい |