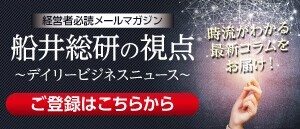企業が成長し社員数が100名、150名、そして200名を超えてくると、組織内の人材はますます多様化します。年齢、性別、キャリア、価値観、働き方、スキル。あらゆる切り口での「違い」が組織に混在するようになり、「うちの会社の人材はこういうタイプだ」といったひとくくりの感覚的な認識では、もはやマネジメントが追いつかなくなってきます。
とくに社員数が200名を超えたあたりからは、従来のようなExcelやスプレッドシートでの人事情報管理だけでは、現場に必要な「粒度の細かい人材分析」や「タイムリーな課題抽出」が難しくなります。
ここが、人事データのBI化(ビジネスインテリジェンス化)を検討すべき大きな分岐点です。
□人事データBI―生産性―
部門別に生産性と達成率を一目で比較でき、課題のある部署を瞬時に把握可能。
多軸での絞り込みにより、人材タイプ別や年次別の傾向分析ができ、ピンポイントな打ち手に直結。
□人事データBI―定着率―
部門・属性別に可視化でき、離職傾向のある層や要因を素早く特定可能。
感覚では見えない「どこで・誰が・なぜ辞めるか」をデータで捉え、的確な定着施策につなげられる。
--------------------------------------------
■ ひとくくりでは見えない課題——こんな分析が可能になる
BIツールを用いることで、従来では困難だった複合的な人材分析が一気に可能になります。以下は、その一例です。
--------------------------------------------
▷ 例1:中途入社人材の生産性の推移
「直近5年で入社した中途社員」のうち、
・入社時点の経験職種や前職規模別
・入社後の配置部門別
・入社1年以内のOJT有無別
などでフィルタリングし、生産性の推移(売上・利益・アウトプット)を可視化。
中途入社のどんなパターンが成果につながっているかが見えてくる。
--------------------------------------------
▷ 例2:離職傾向の早期把握
「勤続3年未満で退職した社員」のデータを抽出し、
・配属部門
・入社経路(人材紹介/リファラル/媒体)
・入社前後のエンゲージメントスコア推移
などを比較分析することで、定着を妨げているボトルネックを特定できる。
--------------------------------------------
▷ 例3:育成効果の部門間比較
各部門ごとの「育成計画の実行度」や「上司の1on1実施率」と、
メンバーの成長指標(スキルテスト結果、昇進スピード、MBO達成率など)を掛け合わせ、
育成の成果が出やすい環境/出にくい環境の特徴を可視化。人事施策の精度が高まる。
--------------------------------------------
▷ 例4:エンゲージメントと業績の相関分析
エンゲージメントサーベイのスコアと、個人やチームのパフォーマンス指標を連動させて分析。
エンゲージメントが高くても業績が上がらないケースと、低くても成果が出ているケースの両方を見つけ出し、真のボトルネックを特定する。
--------------------------------------------
■ なぜ今BI化が必要なのか?
今の時代、「採用すればなんとかなる」はもはや幻想です。
・採用難だからこそ、「自社にフィットする人材」はどんな属性なのか?どんなチャネルで出会っているのか?
・価値観が多様だからこそ、「働き方や上司との関係」に対する満足度がどこで分かれるのか?
・流動性が高いからこそ、「定着しやすい部門」と「辞めやすい部門」の違いは何なのか?
これらはすべて、感覚や経験則では対応しきれない課題です。
その背景にある真因を探るには、データの力が不可欠です。
--------------------------------------------
■ BI化の前に立ちはだかる「壁」——データの質
BIを導入するだけで劇的に変わるかというと、そう簡単ではありません。
実際には、以下のような壁が立ちはだかります。
- 人事データがバラバラに管理されている
- 項目定義が部門ごとに違っている
- 入力漏れ・更新漏れが多発している
この状態では、BIツールを使っても「見せたい数字」が出ません。
まずは「データのクレンジング(整備・統一)」が前提条件です。
その上で、
・何のためにどんな分析をするのか?
・どのKPIを追うべきか?
・誰がどのタイミングで活用するのか?
といった人事部門の設計力と運用力が重要になります。
--------------------------------------------
■ まとめ——200名超えは「感覚の限界点」
社員数が200名を超えると、組織はもはや「家族」や「村」ではなく「都市」になります。
部門や年次、価値観が異なる人々が一緒に働く中で、感覚的なマネジメントでは対応できない課題が急増します。
このタイミングこそ、人材マネジメントを「見える化」し、精緻なデータ分析に基づいた意思決定へと転換すべきです。
採用、育成、配置、定着、エンゲージメント――
あらゆる人事活動の打ち手は、正確な現状把握があってこそ初めて効果を発揮します。
BI化は、単なる「ツール導入」ではなく、これからの人的資本経営における基盤づくりです。
200名を超えたら、まずは「人材データの整備」から。
未来の組織成長は、そこから始まります。
このBI化を主導すべきは、間違いなく「人事」です。
人材の採用・育成・定着のすべてに関わる人事こそが、データを俯瞰し、組織の真の課題を見つけ出し、現場と経営をつなぐ役割を担うべきです。
「感覚」から「根拠ある打ち手」へ。
 | 執筆者: ヒューマンキャピタル支援部 ディレクター 中川 洋一 なかがわ よういち |