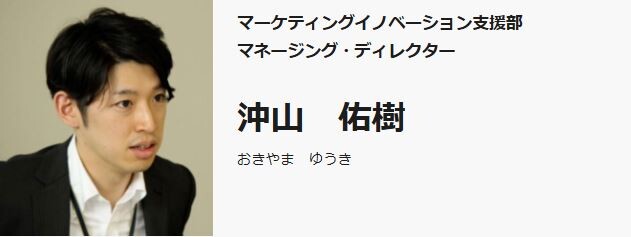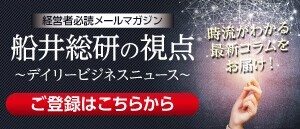多くの企業様がWeb広告を活用されていますが、思うような成果が得られない、具体的な改善策が見えにくいといったお悩みをお持ちの方も少なくありません。
たとえば、過去1年のWEBマーケティングの目標売上とその達成度を確認出来ていますでしょうか。WEB広告が一定の成果が出るようになると、経営層は結果を見ることはあっても新たな目標の妥当性が掴みにくくなって、競合他社がWEB経由で自社よりも急成長しているといったことに気付かされた経験がないでしょうか。これは、投資効果の大きいWEBやSNSには、高い目標とそれを実現する予算や体制が必要で、その判断は経営者自ら行う必要があります。また、現場は達成できる、手に届く範囲を目標設定してしまい、成長領域に踏み込みが甘くならざるを得ないといった側面もあります。
Web広告でビジネス成果を創出し、費用対効果を改善して売上を拡大することは、経営戦略上、重要なテーマになります。船井総合研究所では、Web広告で成果を飛躍的に向上させるために、網羅的かつ着実に実施すべき10の重要なポイントがあると考えております。これらのポイントは一見基本的な内容に見えますが、継続して実行できている企業様は少ないのが現状です。Web広告運用で成果を最大化するために必要な、これら10のアプローチの概要を船井総研の視点から解説いたします。明確な数値目標設定から始まり、現状とのギャップ分析、3C分析による顧客理解、ボトルネックの特定、予算配分の最適化、ターゲティングの再設計、クリエイティブ改善、分析基盤の整備、広告以外の成功要因活用、そして媒体拡張・予算増額によるスケールアップに至るまで、一連の流れで成果創出を目指してまいります。これらのステップを丁寧に実行することで、広告運用は単なる費用ではなく、事業成長のための重要な投資になります。
1.広告運用における明確な数値目標設定の重要性
Web広告運用で成果を創出するためには、まず明確な数値目標を設定することが重要になります。この目標は、マーケティング活動全体の指針となり、進むべき方向性を具体的に示してくれます。広告運用においては、「費用対効果を改善したい」あるいは「売上を伸ばしたい」という二つの大きな方向性があります。それぞれで広告運用の進め方は異なります。そのため、初期段階で定量的な目標を設定し、チーム全体で「成果が良いのか悪いのか」を判断する基準を共有することが大切です。目標が設定されることで、具体的な数値を分析する前に現状の良し悪しを判断する基準ができ、現状と目標の間にどのくらいのギャップがあるかによって、取るべき施策も変わってきます。船井総合研究所では、お客様のビジネス目標達成に必要な指標と数値基準を明確にし、最適な広告運用の方向性をご提案しています。広告運用は目標設定から始まると言っても過言ではありません。この初期段階での明確な目標設定が、後の広告運用の成果を大きく左右することになります。適切な目標設定こそが、成功する広告運用の第一歩となります。
2.広告運用効果を高める目標と現状のギャップ分析
具体的な目標数値を設定したら、次に行うべきことは、Web広告運用の成果を多角的に分析し、目標と現状とのギャップを把握することです。Web広告運用の成果は、顧客属性、季節性、Webサイトの行動データ、各広告媒体のパフォーマンスなど、様々な要素が複雑に絡み合って決まるものです。これらの重要な要素を一つ一つ確認し、最適な組み合わせを見つけ出すためには、現状の数値を正確に把握することが不可欠になります。多くの場合、ビジネス全体のデータと広告運用の成果データには類似性が見られますが、成果が出ていない企業様では、この二つのデータに大きな違いが見られることがございます。広告運用の成果を改善するためには、広告管理画面上のデータだけでなく、ビジネスデータ、Webデータ、広告データという3つの視点からデータを比較・分析することが重要です。船井総合研究所では、これらのデータを横断的に分析し、費用対効果の改善や売上拡大につながる広告運用の課題を特定いたします。このギャップ分析を通じて、次にどのような広告運用の施策を実行すべきかが見えてきます。現状の正確な把握は、効果的な広告運用のために欠かせません。
3.広告代理店に頼らない訴求軸を3C分析で見極める
広告運用で成果を出すためには、顧客(Customer)、自社(Company)、競合(Competitor)を分析する3C分析は大切です。顧客が商品やサービスを購入する際に何を重視するのか、どのような検索行動を取るのか、自社の強みは何か、そして競合と比較してどのような優位性があるのか。これらをWebサイトを起点に顧客視点で情報を整理し、商品やサービスの魅力を最大限に伝える方法を分析します。特に広告運用を外部の広告代理店に委託している場合でも、自社で訴求軸を明確に持つことが重要になります。自社の強みや顧客ニーズを深く理解することで、広告代理店任せにせず、より効果的な広告運用戦略を立案できます。広告代理店との連携を強化する上でも、この3C分析に基づいた自社の明確な方針は、より成果の高い広告運用を実現するために役立ちます。船井総合研究所は、この3C分析を通じて、お客様が広告運用で訴求すべき本質的な価値を見つけ出すサポートをいたします。広告運用の成否は、この訴求軸にかかっていると言えます。顧客のインサイトを深く理解することが、成果につながる広告運用の出発点となります。
4.広告運用のボトルネック特定と課題整理の実態
これまでの調査結果、すなわち目標設定、ギャップ分析、3C分析を踏まえ、具体的な課題と改善策の仮説を立てます。定量的な目標数値と現状を比較し、広告運用におけるボトルネックの特定と、目標との乖離を数値で可視化します。この「実態」把握が非常に重要になります。例えば、コンバージョン数(CV数)が目標に達していない場合、Webサイトへのセッション数が不足しているのか、それともコンバージョン率(CVR)が低いのかを切り分けて分析します。さらに、セッション数が不足しているなら、広告の表示回数が足りないのか、クリック率(CTR)が低いのか、といったように要因を深掘りしていく必要があります。このボトルネックの要因を深掘りし、業界平均値などとの比較も踏まえながら、改善すべきポイントを明確にしていきます。この課題設定の精度が、その後の広告運用の成果に大きく影響してくるのです。広告運用の「実態」を正しく把握し、的確な課題を設定することが、成果改善への最短ルートになります。船井総合研究所では、データに基づいた客観的な分析で、広告運用の真のボトルネックを特定いたします。正しい広告運用は「実態」の把握から始まるのです。
5.費用対効果を最大化する広告運用の予算配分最適化
広告運用における成果向上のためには、媒体ごとの予算配分を最適化することが不可欠になります。これまでの調査結果、目標設定、ギャップ分析、3C分析、そしてボトルネックの特定を踏まえ、具体的な課題と改善策の仮説を立てた上で、広告媒体別に予算配分を見直していきます。しかし、単純に成果の良い媒体に予算を多く配分すれば良いというわけではありません。広告運用においては、媒体ごとにコンバージョン(CV)の定義が異なる場合や、一つの媒体への投資効率が次第に低下していく点(収穫逓減)、さらには媒体間で重複してCVが計測される可能性などを十分に考慮する必要があります。これらの要素を無視した広告運用は、予算の浪費につながりかねません。船井総合研究所では、各媒体の特性や間接効果も考慮した上で、お客様の広告運用全体の費用対効果が最大化されるよう、戦略的な予算配分をご提案しています。継続的な効果測定と調整により、広告運用の精度を高めていくことが重要になります。最適な予算配分は、広告運用の効率と成果を大きく向上させます。
6.ターゲティング再設計による「広告運用」の精度向上
媒体ごとの予算配分が最適化された後、次に取り組むべきは「広告運用」のターゲティングの再設計です。広告の成果は、主に「広告キャンペーンごとの入札戦略 × 年齢 × 性別 × 地域 × ターゲティング設定」といった要素の複雑な組み合わせによって決まります。それぞれの媒体のそれぞれのキャンペーンを確認し、設定された目標の達成状況や実際の売上データなどと比較しながら、調整を行っていく必要があります。具体的には、投資を拡大すべきターゲティング、逆に投資を停止または縮小すべきターゲティング、LP(ランディングページ)などを改善してから再開すべきターゲティング、といったように、各ターゲティング設定を戦略的に分類し、メリハリのある「広告運用」を実施します。船井総合研究所では、ロジックツリーなどを用いて全体像を把握し、ターゲティングの最適化を通じて、「広告運用」の費用対効果改善を支援します。データ活用時代には精緻なターゲティングこそ、効果的な「広告運用」の鍵となります。この見直しは「広告運用」の効率を飛躍的に高める可能性があります。
7.成果に繋がる「広告運用」とクリエイティブ作成の秘訣
Web「広告運用」には、ブランドの認知拡大を目指す「認知系」の広告と、直接的な顧客獲得を目指す「獲得系」の広告があります。認知系の「広告運用」ではクリエイティブそのものの魅力がより重要視され、獲得系の「広告運用」ではWebサイトやLP(ランディングページ)を含めた全体の設計とクリエイティブの連携が成果を左右します。ターゲティングの最適化だけでは、どうしても「広告運用」の成果には限界が生じます。そこで、広告クリエイティブを改善することで、さらなる成果向上を目指すことが重要になります。効果的なクリエイティブを作成するには、事業コンセプトを見直し、3C分析や顧客インタビューなどで得られた定性的な情報も踏まえることが不可欠です。顧客の意思決定のポイント、自社ならではの強み、既存顧客の満足度、競合他社との明確な差別化要素などを多角的に考慮し、デザインに落とし込んでいく必要があります。船井総合研究所では、これらの要素を体系的に整理し、具体的な「広告運用」戦略に基づいたクリエイティブ作成をサポートします。訴求力の高いクリエイティブは、「広告運用」の成果を加速させます。
8.「広告代理店」も注目する好調・不調要因の分析基盤
Web「広告運用」の現場では、月ごとの成果に波が生じることは避けられません。そのような時、最も重要なのは「この変動は一時的なものなのか、それとも何らかの明確な原因があるのか。そもそも広告だけが原因なのだろうか」といった疑問点を迅速かつ正確に解消できる分析スキルと、そのための環境整備です。この能力や環境が不足していると、誤った課題設定をしてしまい、結果的に対策も的外れなものになる可能性があります。これは自社で「広告運用」を行う場合だけでなく、「広告代理店」に運用を委託している場合にも当てはまります。経営者視点からすると、Web経由の問い合わせや予約が増減した際に、その「実態」と向き合い、データに基づいて分析し、説明責任を果たしてくれる広告代理店や担当者と連携することが、継続的な成長のためには重要です。「広告運用」の成果を安定させ、さらに向上させるためには、好調・不調の要因を迅速に特定し、次の一手を打てるデータ分析基盤の構築が不可欠です。
9.「広告運用」の枠を超える成功要因の活用法
「広告運用」の成果改善のヒントは、意外にも広告管理画面の外に隠されていることが多いものです。顧客が「どこで、何をきっかけに自社の商品やサービスを知り、問い合わせや申し込み、あるいは購入に至ったのか」というカスタマージャーニー全体を把握し、その情報を「広告運用」に積極的に活用することが重要になります。例えば、GA4(Google アナリティクス 4)の分析で、特定の参照元サイトからのコンバージョン率が際立って高いことを発見したとします。実際にそのサイトを確認したところ、質の高い紹介動画が掲載されていたかもしれません。この動画の構成やメッセージングを参考に新たな広告動画を制作し、活用した結果、問い合わせ数が大幅に増加した、という事例もあります。また、SEO経由で流入し、特に成果に繋がりやすい記事コンテンツのテーマやキーワードを「広告運用」の検索広告やディスプレイ広告のターゲティング、クリエイティブに反映させることも有効です。このように、「広告運用」担当者だけでなく、他のWebマーケティングツールや分析に長けた人材と連携し、得られたヒントを柔軟に「広告運用」に応用できる体制が、更なる成果改善に繋がります。
10.「広告運用」の最終段階:媒体拡張と予算増額でビジネスをスケールアップ
これまで解説してきた9つのステップを着実に実行することで、多くの場合、「広告運用」の費用対効果は顕著に向上します 。しかし、それでもなお設定した事業目標の達成に至らない場合には、既存の広告媒体を見直すだけでなく、新たな広告媒体への拡張も視野に入れる必要があります 。そして、費用対効果が十分に改善された段階で、さらなる売上増加と事業成長を目指し、広告予算の増額を検討し、ビジネス全体のスケールアップを図りましょう 。ただし、この「広告運用」の拡大フェーズにおいては注意すべき点があります。広告費を増額する際、一つの媒体に投資を集中し続けると、徐々に獲得効率が悪化し、費用対効果が頭打ちになる可能性があるのです 。どの程度の投資額が限界点となるかは、実際に試行してみないと判断が難しい部分もありますが、複数の媒体や異なる商材へ広告投資を戦略的に分散することで、費用対効果の悪化リスクを抑制し、継続的に成果を上げ続けることが可能になります 。一方で、複数の媒体をまたがる「広告運用」は、効果測定が複雑化したり、運用管理のコストが増大したりする新たな課題も生じさせます 。そのため、これらの問題を的確に把握し、適切に解決できる専門知識と経験を有したパートナーと緊密に連携しながら「広告運用」を進めることが、売上最大化の観点から非常に重要になります 。船井総合研究所は、お客様の「広告運用」が常に最適な状態を保ち、事業の持続的な成長に貢献できるよう、戦略的な媒体拡張と予算配分をサポートします。
ここまで10のアプローチをご紹介させて頂きました。WEB広告運用は広告費という成長にドライブをかける重要な投資分野になっている企業様も多く、その技術やスキルもAIの発展や多様化するSNSにより複雑化している側面もあります。自社のビジネス目標を適切に設定して、投資効果の大きい投資分野で成果を上げることが、経営者の判断・決断になっていきます。このコラムの詳細なレポートをご用意させて頂いています。ぜひ、自社の成長余地の発見にお役立て頂けますと幸いです。