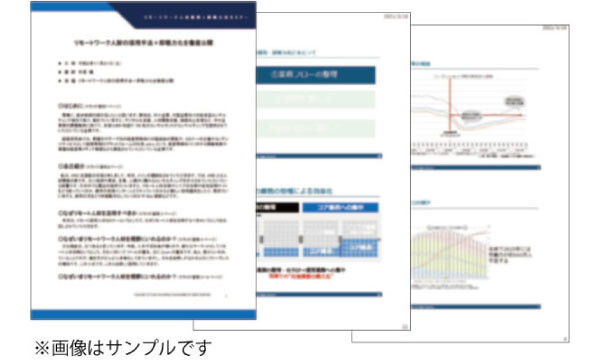新会社移行に関するご案内
この度、船井総合研究所の人的資本経営支援本部は、グループ会社である株式会社HR Forceと2026年1月1日付で事業統合し、新たに「船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング」を発足いたします。
これに伴い、本講演録のダウンロード後の情報配信やご案内につきまして下記の通り変更となりますのでご了承ください。
1. メールマガジンの配信について
本講演録をダウンロードいただいたお客様へは、新会社「船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング」より、人的資本経営に関する最新情報や実践事例を盛り込んだメールマガジンを配信させていただきます。
2. 無料相談のご案内について
本講演録ダウンロード時に、無料相談へお申込みいただいたお客様には、新会社「船井総研ヒューマンキャピタルコンサルティング」の担当者より、無料相談に関するご案内を差し上げる場合がございます。
はじめに

皆様、おはようございます。株式会社船井総合研究所の山根でございます。本日は、長丁場のセミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。
近年、「人的資本経営」という言葉を多くのメディアで目にされる機会が増えているかと存じます。弊社、船井総合研究所におきましても、私が所属する部門が今年から「人材支援部」から「人的資本経営支援部」にリニューアルするなど、市場が非常に注目し、力を入れているテーマでございます。お客様からのご相談も急増しており、これまでの「採用」を中心とした相談に加え、人材の育成、定着、評価、さらには人事のDXといった多面的なご相談が増えています。
本セミナーでは、この人的資本経営の概要と、特に中小企業における実践的な解釈についてお話しさせていただきます。
人的資本経営が重要視される背景
なぜ今、これほどまでに人的資本経営が重要視されているのでしょうか。その背景には、大きく分けて以下の要因が挙げられます。
1. 一般的な背景
■ 人口減少と少子高齢化: 日本全体で人口が減少し、企業が労働力を確保することが困難になっています。
■ 働き方の多様化: ジョブ型雇用、スポットワーカー、ギグワーカーといった新しい働き方が登場し、これまでの常識に当てはめた従業員マネジメントが通用しなくなっています。
■ 賃上げと働き方改革: 業界問わず賃上げや働き方改革が進展しており、これまでのアプローチとは異なる人材戦略が求められています。
2. 中小企業に特化した課題
中小企業の成長を阻害する要因は、労働力の文脈で以下の2点に集約されます。
■ 構造的な人手不足
「人がいれば売上が上がる、新規事業ができる、お客様にもっと価値貢献できるのに、人がいないから何もできない」という状況が全国で発生しています。
・採用力の急激な低下: 求人要件を工夫しても募集団が減り、採用の歩留まりが悪化しています。
・定着期間の短期化: 多大なコストと手間をかけて採用しても、従業員の定着期間が短くなり、結果として投資が無駄になるケースが増えています。
・マネジメント層の育成不足: 若手の入社が少ないため、中間管理職が育たず、マネジメント不足がさらなる定着率の低下を招く負のスパイラルに陥っています。
■ テクノロジー導入の遅れと成果のなさ
人手不足を補うために、AIによる生産性向上やDXによる効率化といったテクノロジーの導入が図られますが、中小企業にとっては大きな壁があります。
IT化、DX、AIといった新しい技術が次々と登場し、導入して効果を実感する前に次のトレンドがやってくるため、売上や利益に反映されにくい実態があります。
さらに、新しい技術を使いこなせるIT、DX、AIリテラシーのある人材の採用自体が困難であるため、この二重苦に苦しむ企業が非常に多いのが現状です。
3. 企業規模別の人的資本経営の現状
企業規模を問わず、人的資本経営への関心は高いものの、その取り組みの実態には課題が見られます。
・大手企業: 上場企業などでは開示義務があるため、形式上は人的資本経営に取り組んでいます。しかし、その内容は「絵に描いたような人事」であり、対外的な発信や義務を果たすためのポーズに留まっているケースが多いです。
・中堅企業: 投資余力はあるものの、面談ツール、マネジメントシステム、採用管理システムなど、ツールや道具への投資に偏り、それが従業員の幸福や企業の成果に直結していないケースが散見されます。目の前の採用応募数の減少や人材の質の低下といった課題に追われているのが実情です。
・中小・零細企業: 採用担当の専門部署や人的リソースが不足しており、兼任で対応しているため、そもそも十分な力を入れられていません。特定のツール導入など単発的な施策に終わり、効果が得られないか、または「そんなことよりもまず採用が先だ」と足踏みしている状況です。
このように、どの企業規模においても、人的資本経営を導入し、具体的な成果にまで結びつけられている企業は非常に少ないのが現状と言えるでしょう。