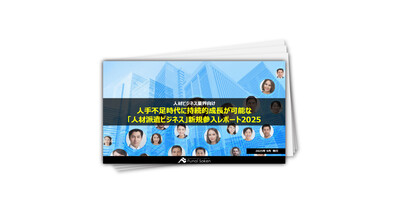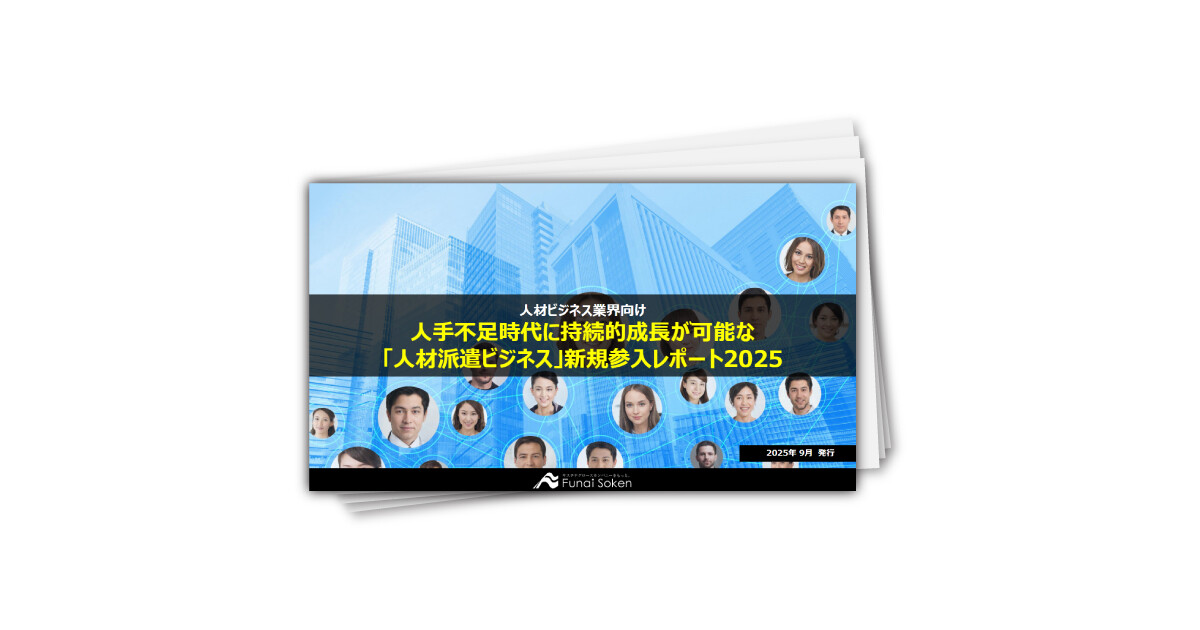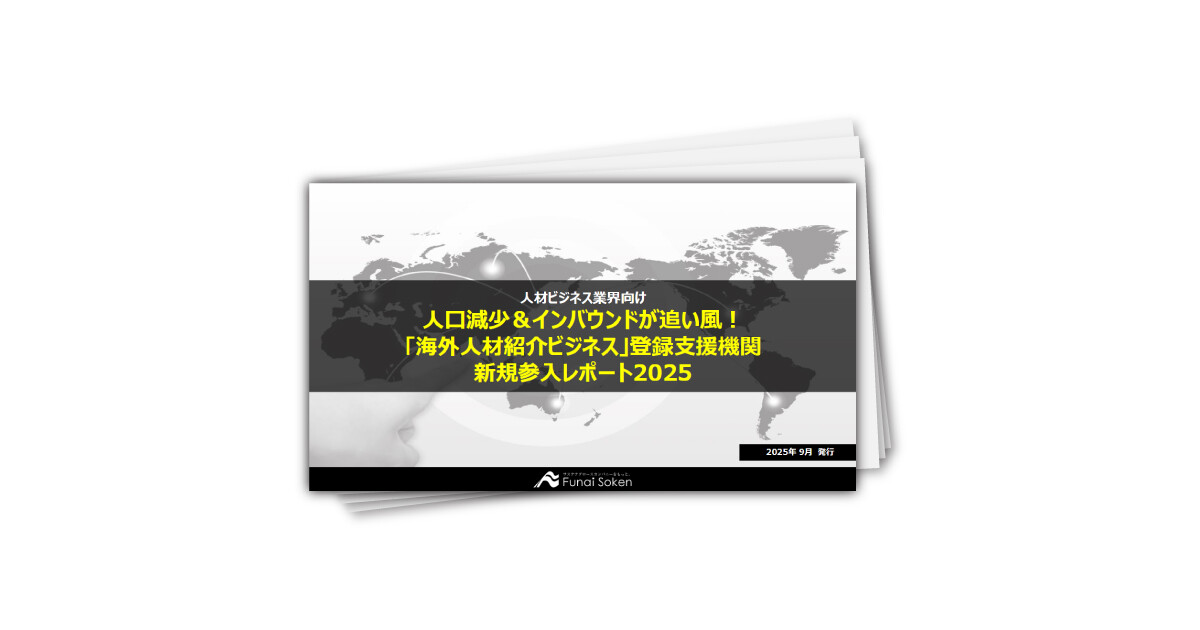◆開催日時:2020年9月25日(金)
◆講師:船井総合研究所 藤木 晋丈
◆演題:「合同説明会に頼らないオンライン採用を1 か月で導入する方法」
はじめてのオンライン採用で失敗しないための3つの注意点―合説からオンラインへ集客手段が変わることによる強化ポイントの違い
早速ですがページをめくっていきたいと思います。
コロナの状況の中でリアルの採用活動ができずにオンラインを推進していく会社さんというのは非常に多いです。
リアルの採用活動と違いオンラインで採用活動を進めるにあたって、注意しなければいけないポイントが三つほどございます。
一つ目が合説からオンラインへ集客手段が変わることによる強化ポイントの違いということになります。
例えば、合同企業説明会で集客をする場合は声掛けを強化しなければいけなかったりとか、ブース作りで自社のカラーを出したりとか、デザイン性を高めたりとかをしなければいけません。
もっと言うと合同企業説明会でプレゼンテーションする人事の見た目などにも気を使わなければいけません。
さらにブース作りも含めて、賑わい感や社風を合同企業説明会のリアルの場にいかに持ち込むかということも大事なポイントになりますが、オンラインになりますと、右のように声がけの代わりにライティングスキルが必要になります。
求職者にオファーを出すライティングスキルや自社ホームページのライティングスキル等になります。
そして、ブース作りの代わりに必要なものは自社の看板になる採用ホームページのデザインです。
採用担当者の見た目ということで言うと採用サイトなどのオウンドメディアのコンテンツの中身のことになります。
また、賑わい感というのはネット上の口コミ等のことになります。
こういったポイントが重要になってくるということで、合同企業説明会で集客をするのとは大きく異なってきます。
さらにはリアルでスタッフ間のやりとりを見せたりとか、プレゼンテーションをしたりとか、クロージングをしたりするということで比較的対人能力が強化の対象になります。
オンラインなった瞬間にSNSなどを通じた情報発信のスキルや動画コンテンツの精査、あとはオンライン上の導線設計が大事になります。これらのポイントをしっかりと押さえた上で強化をしていかなければいけません。
特に最後お伝えしました導線設計に関しましてはこのようなかたちで、どこでどういうツールや媒体を通じて応募まで持っていくか。といったところをしっかりとカスタマージャーニーマップの簡易verを作っていかなければいけないということです。
特にオンライン採用で失敗しないための強化のポイントというのは、これまで使っていた求人ナビ媒体はもちろん使い__慣れているため良いのですが、その前の段階の認知度アップのためのSNSの活用や入社意欲向上のための惹きつけゾーンにある採用活動自体のデジタル化をするということです。
オンラインでどのような説明会をするのか、オンラインでどのようなインターンシップをするのか、オンラインでどのような面談や面接をしていくのか、そしてオンラインでどのような求職者フォローやケアをしていくのかが大切になってきます。
このあたりの強化のポイントを間違えずに行っていくことがまず大切となっています。
はじめてのオンライン採用で失敗しないための3つの注意点―採用担当者(≒会社自体)のオンラインスキルの低さ
次に、これは最近進めていくうえですごく私のクライアントにも感じることですけれども、採用担当者もしくは会社自体のオンラインスキルの低さが挙げられます。
そもそもオンラインで採用活動しようとしたときに、そもそも不慣れだということで例えばzoomなどで会社説明会をやろうとしているのですが、そもそもの操作方法に不慣れで何か音が鳴ってしまったりとか、例えば学生をホスト権限でミュートにしたりとか、入室を許可したりとか、例えばブレイクアウトルームを使ってグループ座談会をすることも、なかなかうまくできないと、さらには画面共有であったり、ミュートのままにして学生に向けて話してしまったり、何かクライアントさんのオンライン採用活動を見ていると、そういった不手際が非常に多くて、何となく学生が、「たいしたことないなこの会社」というところをその時点で思ってしまっていることがあります。
もしくは逆に妙にテンションが高くて、何かYouTuberになったような高いテンションのまま学生対応してしまう、何かある意味で初めてオンラインやっています。みたいなご担当者の方も逆に学生であったり、求職者の方々からするととても痛々しくて、と言いますのも、例えば求職者が学生の場合、今は大学の授業がほぼオンラインで実施されていますし、様々なオンラインツールを使い慣れているというのが今の学生の特徴かなと思います。
ですので、採用担当者のオンラインスキルが低いと、それだけでレベルの低い会社だと思われてしまいます。
そもそも担当者のレベルが低い会社の特徴としては、会社のオンライン環境が整っていないです。
具体的に言うと本当に初歩的なことですが、無線LANの電波が弱いとか、弱くて途中声が聴きづらいとか、もっと言うと説明会の途中で企業側の担当者が抜けてしまうみたいなことも散見されています。
あとはオンライン環境ということで、人事がオンラインの説明会をやっているところが周りの雑音が入ってきたり、電話の音が入ってくるとか、プレゼンに集中できない環境になってしまっていることがあります。
もっと言うと普段パソコンを使って仕事をしない業種の場合なかなかパソコンの台数が揃っていないということもあり、複数人の社員さんが一つのパソコンで入ってしまって学生からすると顔が見えないとか、そういったオンラインの環境の整備っていうところが非常に不慣れな会社さんというのも多くいらっしゃいます。
1番とも通じるのですが、そういったところで普段の会社説明会であれば来場した求職者の方に「こんにちは」と声をかけたりとか、「どうぞお飲み物をお飲みください」とか、ちょっとした気遣いをするのは当然ですけれども、ことオンラインなっていると自分が操作でいっぱい、いっぱいだったり、どういう気遣いをしたらいいのかが分からず、配慮が足りない。一方的なプレゼンテーションやプレゼンとプレゼンの合間の無音の時間が2、3分続いてしまったり、そういったところが結局、求職者の志望度を下げてしまいます。
結論はこの下に書いてありますが、オンラインスキルが低い=会社のレベルが低いと判断されてしまいます。
これが注意点の二つ目になります。
はじめてのオンライン採用で失敗しないための3つの注意点―臨場感・現場感が感じられず志望度が上がらない
三つ目が臨場感や現場感が感じられず志望度が上がりづらいということです。
基本的にオンラインだけで採用活動を進めていこうとすると、ちょっとした工夫や臨場感や現場感を出す取り組みが必要になってきます。
ただ、応募の段階で臨場感や現場感を出す必要はありません。
特に会社説明会に来て現場を見てもらって、うちを気に入ってもらって選考に進んでもらいたいと、そういう考えを持った経営者の方非常に多いですけれども、それはちょっとあの早いかなとむしろ、選考が進んで志望度が上がってきて、最後の決め手や確認という意味で現場感や臨場感が感じられるリアルの場に引き込む必要があると思います。
なので、応募段階ではオンライン程度がちょうどいいということになります。
二つ目、単純なプレゼンや写真、動画では臨場感が伝わらないということです。
先ほども申しましたが、普段使っているプレゼンテーションのプレゼンをいかにオンラインで伝えようとも、普段使っている採用用の動画を使ってアピールしようとも、なかなか臨場感は伝わってきません。
なので、今日のセミナーの中でもお伝えしますが、いかに例えば360度カメラを使ったりVRとか、そういった最新のテクノロジーを使って臨場感やライブ感を出していくのかが大事になります。
求職者は入社を決意するまでには、志望度が上がったタイミングで臨場感やリアル感を感じたいと考えているということです。
以上三つの注意点をオンライン採用に取り組む会社さんは注意をしていただければなと思います。
最新採用テクノロジー活用法―「採用活動におけるSNS活用」
続いて事例といいますか、最新採用テクノロジー活用法ということで話を進めていきたいと思います。
最新の採用テクノロジー活用法というテーマで一番最初にお伝えするのがSNS活用ということで、特に最新というわけではないですが、SNSを使った採用活動を上手に取り組めていない会社さんが非常に多いかなと思っております。
ただ単純にFacebookやInstagramに記事や写真をアップすればいいというわけではございませんので、しっかりとした導線設計やジャーニーマップが必要になってきます。
そしてさらには、そこに自社のブランドや風土を魅力的に発信するためにはどうしたらいいかという戦略を立てていく必要があります。
これが全体像になります。
それぞれ実際に活動を進める際に重要なポイントを四つほどお伝えしていきたいなと思います。
一つ目が戦略の設計図の目標設定です。何をゴールとしてSNSを活用していくのかになります。
二つ目がペルソナの設定です。誰向けのSNS活用なのかということです。
平たく言うと自社の求める人物像をどのように設定をしていて、その人向けのSNSを更新していくのかということです。
そのターゲットに合わせたSNSの剪定ということで、いろいろSNSございますがそのターゲットの年次や思考にあったSNSを設定していくということです。
SNSは比較的誰にでも自由にアプローチができる反面、炎上などのトラブルも起こしやすいツールとなっております。
なので、そういったものを起こさないためにも運用マニュアルを作っていく必要があります。
ではそれぞれ一つずつ簡単にではございますが、説明していきたいと思います。
一つ目が目標設定ということで、例えばブランドの認知度の向上であればファン数、リーチ数、インプレッション数などが目標設定として掲げるのが正しいです。
ブランドの好感度向上でいうと、いいね数やコメント数やTwitterでいうとリツイート数などになります。
自社サイトのアクセス数の向上でいうと、そもそものURLのクリック数やアプリのダウンロード数などです。
あとは検索数の向上でいうとハッシュタグの数ということで、左側のSNSを活用する目的や狙いをどこに定めるかによって、目標となるKPIが変わってくるということです。
まずはどの目標に向けて何の数字を上げていくのかをしっかりと明確にすべきということをお伝えさせていただきました。
二つ目がペルソナの設定についてです。
多くの会社さんが何となくぼんやりとペルソナの設定はやっているのですが、明確な人物像まで落とし込めていないなと思います。
こちらのテキストを見ていただければ、分かるとおり左側がぼんやりとしたペルソナ設定の例です。
20代の会社員みたいなかたちのぼんやりとしたものです。
女性とかは決まっていますし、未婚とか既婚とかぐらいは決まっているんですけれども、細かい設定ができていないということです。
つまりターゲットが不明瞭だと投稿内容や施策が決まらないので、できるだけ明確にするということがSNS活用の際のペルソナ設定では特に重要事項として挙げられております。
設定したペルソナに合わせて利用するSNSを剪定ということで、恐らく今日お聞きになられている皆さんも、FacebookやInstagramやTwitterあとLINEで何となくFacebookは30代中盤から後半以上の登録者数が多くてInstagramは比較的若い世代が多いかなと、Twitterはどちらかというと情報収集向けでYahoo!ニュースなどを見る代わりにTwitterで情報を集めている人が多いかなと、LINEはどちらかというと万人受けするのですが、集客手段としては、なかなか活用は見えてこないかなと思います。
そういった各種SNSの特徴というものを何となく感じてはいらっしゃると思うのですが、これをしっかりと落とし込んでいただいて、どれが自社のペルソナターゲットにあった媒体なのかを選んでいただくといいと思います。
こちらには記載していませんが、最近だと10代の子達のマーケティング要素でいうとTikTokなんかも、重要なSNS活用の媒体の一つとなっているかなと思います。
近年こと採用活動においてどういったものを活用している会社が多いかというと、中堅企業にあたる会社さんは自社のTwitterアカウントを持って運用してファンを集めていっているので、比較的プロモーションと兼ねてTwitterを使っている会社さんは非常に多いかなと感じております。
Instagramに関してはどちらかというと映えるという言葉が正しいのかどうか分かりかねるのですけれども、そういった要素の強い業種や職種の会社さんの活用が特に目に付くようなかたちになっております。適切なSNS選定をしていただければと思います。
続いて運用マニュアルの作成についてです。
こちらは先ほどもお伝えしたように、SNS活用していきますと、どこかでコンプライアンス違反や炎上という小企業の根幹を揺るがしかねない問題にも発展しないとは言い切れません。
従ってしっかりと運用マニュアルの作成をしていただければと思います。さらに言うと運用マニュアルを作成しただけではなく、例えばミーティングの設定や定点チェックということでPDCAをしっかりと回せるようになるのが大事かなと感じております。
一つだけ具体的なInstagramを使った活用事例をお伝えします。
Instagramを活用した採用活動ということでハッシュタグ検索をします。例えば皆さんが設定したペルソナの人物が趣味、嗜好でいうとサッカーをしているとすると、ハッシュタグサッカーというように検索をします。
例えば大学生で体育会系の子がいて、しかもやっているスポーツがサッカーだとすると、例えば近隣の大学のサッカー部の名前を検索していただいて、ハッシュタグ検索をすると大体該当するページやハッシュタグを付けている人が現れます。
そうすると、そこのページやハッシュタグをつけている人のページに飛んでいただいてリアクションという意味でいいねを、こちらからどんどんしていきましょう。
いきなりアカウントを見つけてフォローしてフォローバックしてもらえるかというとそうではないです。
最近は意味のないというか企業側からの無作為なフォローもありますので、ほとんどの場合が無視されてしまったりとか相手にされないケースが多いのですが、そこを定期的にリアクションすることで何回かいいねを押したり、コメントを残させてもらったりするうちにある程度の距離感ができて、そこからアカウントをフォローすると逆にフォロワーとしてフォローバックしていただけるという流れになっております。
なので、基本的にはハッシュタグでターゲットを見つけていいねやコメントで心の距離や信頼感を勝ち取り、最後にフォローしてつながりを作っていくという手順になっております。
これが一つ目のSNS活用の事例となっております。
最新採用テクノロジー活用法―「ダイレクトリクルーティング」
続いて、ダイレクトリクルーティングということでこれはどちらかというと、といろんな媒体があります。
offerboxさんやキャリアチケットさんやニクリーチさんやキミスカさんとか様々な媒体がありますが、今日われわれがお伝えしたい媒体さんに関しましては、新卒版ダイレクトリクルーティングで最も勢いのある媒体さんですし、登録学生数の多いofferboxさんの活用事例になります。
offerboxさんの活用事例としましては、基本的にはオファーを送信して内定承諾までで理想値を掲げると40通送って1人内定承諾を得られるというKPI設定がモデルとして挙げられています。
個別対応型だとそうは行くのですけれども、少人数だった場合や説明会集団対応型だと数値の1/40が1/67になったり1/110になったりするということで、歩留まりが悪くなるかたちになります。
ですので、できるだけダイレクトリクルーティングを活用される場合は合同企業説明会と同じように誰でもいいから声をかけようというかたちではなく、ちゃんと自社に合った自社の求める人物像に限りなく近い人たちに少数声をかけて、承認してもらって入社まで引っ張っていくという1/10の採用とかではなくて1/2とか少なくとも1/3、1/4ぐらいの採用方法であるという認識を持っていただければと思います。
そうなってきますと、検索の仕方が大事になります。
条件検索で大事になってくるのは、媒体をいつ活用したのかっていうログイン日時の設定と後は志望勤務地の設定です。
あとは大学名や志望業界と志望職種というところでセグメントをかけて行きますし、さらに優秀な学生かどうかが極めてわかりやすいのが、適性診断による絞り込みです。適性診断である一定の数値以上の学生さんだけを絞り込んでアプローチをすると、今まで会ったことがなかったり、今まで会った中でも特にいいなと思う学生を集めることができます。
そういったかたちで適性診断の結果を用いて絞り込んでいくことも大切になります。
あと、われわれが設定したペルソナについて言うと、出身高校名などのキーワードで検索をすると、貴社の求める人物像に近い学生を検索することができます。
そういった学生に向けてしっかりと個別感のあるメールを送っていくことが大事になります。
では、どういったとメールを送って行けばいいのかというとこのようなかたちで学生のプロフィールを拝見して、特にどういったところを見なければいけないかというと学生の写真ですどんな写真を掲載しているかや思考をつかんでいきます。
ベンチャーなのか、大手老舗なのか、どういう業界を見ているのか、その学生の特性をつかんでいくときにオファーメールで個別性のあるメッセージを送るんですけれども、その際に重要なのは、学生における特異性のある部分をしっかりと抽出することが大事になります。
ですので、何か一般的な学生がPRしているポイントをあなたは前向きな姿勢がであることやリーダーシップ取れることを言ったところで学生からすると、自分でPRしておきながらもあまり嬉しくないオファーになってしまって承認が得られづらいという傾向があります。
それらをまとめた図がこちらの図となっております。
offerboxの学生対応の流れということでSTEP1オファーメールの送信で特に承諾率が高いのは、例えば写真を加工している女性に対してその写真を褒めるシンプルなメッセージ送ると大体100%承認をしてくれます。
逆に写真だけ登録している学生もいて、文章を書いてないと写真はいいのに文章がなくてどういう学生か気になりました。
できれば話したいのですけどというようなかたちで逆説的に、マイナス面をプラスに捉えてオファーをかけると承諾率が上がってきます。
そういったかたちで、どの学生にどういったメッセージを送るのか、送っていって承認を得られていく都度、自社内にノウハウとして蓄積することができます。
そのようなポイントを押さえて活動していくと、このようなかたちで例えばオファー送信数が1062通、この会社さんすごく頑張ってオファーを送信してくれているのですが、そこからオファー承認224名、そこからカジュアル面談が118名、会社見学が80名、最終選考30名、内定承諾8名ということです。この会社さん最終選考前30名から8名ということですが、辞退されているわけではなく、来るという子にしか内定を出さない方式をとっております。
シンプルに8名絶対来るかたちになったということです。
しかも、去年から今年にかけてofferboxの倍率が企業側にとってはすごく良くなっています・・・
※ セミナーの講演録と当日使用したテキストをダウンロードいただけます。