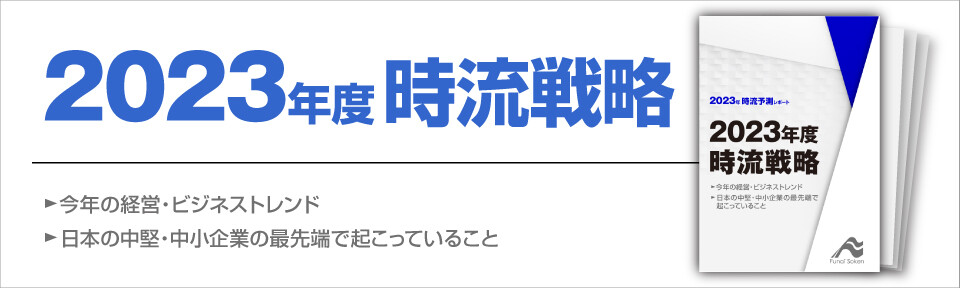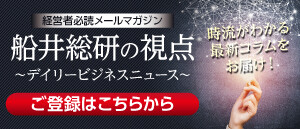現在の経営課題から見えてくるインフレ時代の特徴
原材料費の高騰に、資材費の高騰、そして、燃料費UPに、物流費UP、
さらには、外注費の高騰に、特殊技術職の採用コストも上昇、・・・、
あらゆる業界において急激なコストUPが現実の経営課題として突き付けられています。
コストUPだけではなく、仕入調達の遅延やそもそもの仕入調達自体が困難になったり、
外注会社や下請からの納期や工期が遅延するなど、企業経営にとっては難しい時代になりました。
コストだけではなく、納期・工期・業務の遅延により、売上計上の遅れ等、
深刻な影響が出ている企業が多いようです。
「おカネはあるがモノが届かない」という典型的なインフレ時代の特長です。
インフレ意識の高まり
 ※「GoogleTrends」より
※「GoogleTrends」よりここで、参考までに「インフレ」の検索ボリューム推移を掲載しておきます。
これは、「インフレ」という語句のGoogle検索数の5年間推移で、2021年末以降が過去5年間で最も検索数が多い状態です。
この図からも、全国的にインフレ意識が高まっていることが分かります。
ところで、この流れは短期的かと言うとそうではなく、すぐ解決されるかと言うとそれもあり得なく、悪く言えば諦めなければいけません。
むしろ、これらの流れを前提条件と考えて、「インフレ基調を前提とした経営のあり方」を改めて見つめ直さなければならないようです。
まさに、本コラムのタイトルにあるような「インフレ時代に強い経営とは?」を自問自答する絶好の機会です。
インフレ時代に強い経営とはどんなものか
さて、この問いに対する答えですが、実は意外にもシンプルです。それは以下です。
②圧倒的に儲かる(高付加価値な)体制にすること
こう書くとあまりにも当たり前すぎると思われそうですが、
よく考えるとより深い意味があります。
まず、上記①ですが、限られた原材料の争奪戦においては、
結局はより売れる企業にその原材料は集中します。
その結果、業界内・商圏内の一番企業が1人勝ち状態になりやすいものです。
なので、圧倒的に集客して顧客を獲得し続けることが大事です。
上記②の圧倒的に儲かる(高付加価値な)体制作りの為には、
DX化による効率化がもはや絶対に必要な条件となります。
そして、単純に「モノを仕入れてそのまま売る」というビジネスモデルでは付加価値を高めることは出来なくなり、より原材料調達難に振り回されるでしょう。
「高付加価値を付けて商品を高く売る」ビジネスモデルへの転換が必須となります。
「圧倒的集客」×「圧倒的高付加価値」、これが「インフレ時代に強い経営」の方程式です。