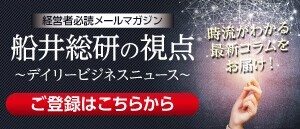DX(デジタルトランスフォーメーション)は、単に最新のデジタルツールを導入することだけではありません。AIやロボット、各種システムといった技術の活用はもちろん含まれますが、それ以上に重要なのは、ツール導入前の段階で業務のあり方そのものを見直し、改善すること、そして従業員がシステムを使いこなすためのインフラを整備することです。これは、デジタル技術を用いて業務プロセス、組織文化、さらにはビジネスモデルそのものを変革し、競争上の優位性を確立する取り組みを指します。その結果、生産性や利益の向上が期待できます。
DX推進は、多くの場合、複数の課題に同時に取り組み、中長期にわたり多様なプロジェクトを段階的に実行する性質を持っています。短期間で全ての変革を完了させることは難しく、数年単位で進めるケースが一般的です。このような複雑かつ長期にわたる取り組みを進める上で、「グランドデザイン」は非常に重要な道標となります。グランドデザインを策定することで、DXを通じて「何を」「いつまでに」「どのように」達成するのかという中長期的な計画を明確にできます。
最も重要な点は、このグランドデザインが、経営層、IT部門、現場の各担当者など、全ての関係者が同じ目的意識を持って計画を実行するための共通認識となることです。異なる立場の関係者が目指すべきゴールとそこに至るまでのステップを共有することで、プロジェクトの一体感を高め、スムーズな推進が可能になります。また、グランドデザイン策定に向けた検討プロセス自体が、現状の課題や目指すべき理想像をより明確にする貴重な機会となります。これは単なる計画書の作成に留まらず、組織全体でDXの方向性を議論し、共有するプロセスそのものに大きな価値があるのです。
DX推進における共通の課題とグランドデザインの役割
DX推進において、多くの組織が直面する共通の課題が存在します。まず、システムが部門や拠点ごとに個別に導入・運用され、連携が不足しているケースが散見されます。これにより、同じ情報を複数のシステムへ二重に入力する必要が生じたり、必要な情報を集約するのに膨大な時間を要したりと、業務の非効率性が顕著になります。また、デジタルツールが導入されていても、依然としてExcelや紙ベースでの業務が中心となり、情報が個人のPCやファイルに点在し、特定の担当者に業務が属人化してしまう問題も発生します。長年利用している既存システムが老朽化し、改修や他システムとの連携が困難になっていることも、DX推進の大きな足かせとなるでしょう。
さらに、業務・システム面だけでなく、DX推進体制や人材に関する課題も少なくありません。大規模なDXプロジェクトの推進経験を持つ担当者が社内に不足している、あるいは全くいない場合も多く、プロジェクトの進め方が分からずに停滞することがあります。全社的な業務全体を見渡せる人材が少ないために、具体的な課題整理や対応策の検討が十分にできない状況も一般的です。社内リソースの不足やITに関する専門知識の欠如は、プロジェクトを主体的に進める上での大きな障害になり得ます。
加えて、経営層はDX推進に意欲的であっても、その目的や重要性が現場レベルまで十分に浸透しておらず、業務改革への意識にずれが生じていることも大きな課題です。これらの複合的な課題が組織全体の生産性低下や情報活用の遅れを引き起こしています。
グランドデザインは、これらの課題に対する有効な解決策を提供します。具体的な計画として「道標」を示すことで、システムがバラバラな状態を統合する方向性を示し、アナログ業務からの脱却を促します。また、DX推進の経験不足に対しては、段階的なアプローチや外部有識者の活用といった計画を組み込むことで、組織的なノウハウ蓄積を支援します。何よりも、グランドデザインを策定するプロセス自体が、経営層と現場の意識のずれを解消し、共通の目的意識を醸成する強力な機会となるのです。
グランドデザイン策定と実行を成功させる秘訣
グランドデザインの策定は、いくつかの重要なステップと成功のための秘訣が存在します。まず、DX推進の出発点となるのは「キックオフ」です。ここでは、組織のビジョンや経営戦略に基づき、DXによって達成したい目的や目標を明確に設定することが最も重要です。そして、その目的達成に向けた推進体制を構築し、関係者全員で「自分事」として捉えるための意識統一を徹底します。
次に、「調査(現場ヒアリング・課題抽出)」を通じて現状の業務フローを把握し、様々な部門や拠点から意見を集約して組織全体の課題を洗い出します。単に課題をリストアップするだけでなく、その根本原因を明確にすることが肝要です。洗い出した課題に対しては、「対応策の検討・優先順位付け」を行います。ここで重要なのは、いきなりシステム導入ありきで考えるのではなく、まずは業務フローの見直しによる「業務改善」で解決できないかを探ることです。システム対応が必要な場合は、データの連携・一元化を意識した対応策を検討します。優先順位は、重要度、期間、費用、難易度、目標への寄与度合いなどを踏まえて決定し、特にDX推進に慣れていない場合は、難易度の低い対応から着手し、小さな成功を積み重ねることが有効な戦略となります。
その後、予算や社内リソースを考慮して「取り組み範囲を決定」し、最終的に「ロードマップとして策定」します。この際、無理のない段階的な計画を立てることが重要です。策定したグランドデザインは、詳細なスケジュールに落とし込み、プロジェクト実行中は関係者間で定期的なコミュニケーションを取り、進捗状況や課題を常に共有することが不可欠です。複数のプロジェクトが並行する場合でも、全体を統括し、全体最適の視点を持つマネジメントが求められます。外部のITベンダーと連携する際は、要求仕様書(RFP)をしっかりと作成し、認識の齟齬を防ぐことが重要です。最終的には、外部有識者の知見を活用しつつも、自社でプロジェクトマネジメントや業務改善、ITに関する知見を持つ人材を育成し、自立的にDXを推進できる体制を構築することが理想的な姿といえるでしょう。継続的な改善(PDCA)を組み込むことで、グランドデザインは変化する状況に柔軟に対応し、持続的な成果に繋がります。
詳しくは以下のセミナーレポートをご覧ください(製造業以外の方にも推奨)。
無料でダウンロードいただけます。
 | 執筆者: DXコンサルティング部 ディレクター 山木 裕 やまき ひろし |