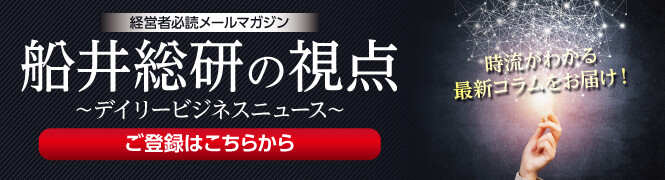年間休日増加の落とし穴『採用難と働きやすさの狭間で』
昨今続く採用難、従業員の労働時間削減による働きやすさの観点から、会社規定の年間休日数を増やす企業が増えています。
データを見ると年間休日100~109日という会社が割合として多いですが、年間120日を超える中小企業も見かけることも増えました。
しかし、時期尚早に年間休日数を増やすことは危険です。
例えば、有給休暇の取得に関するルールが改定されたことで、今までほとんど有給消化されていなかった企業でも取得を推進しています。
有給休暇は上記年間休日とは別に取得できる休暇であり、有給消化されていなかった企業で規定の年間休日を増やすと、年間休日の増加に加えて有給の取得日数分を考えなければなりません。
また、年間休日を増やすことは労働者の時間単価アップに繋がる可能性が高く、経営者としては時間外手当などの膨らみも考慮しなければいけません。
年間休日増加と生産性向上『両立への道筋』
このように年間休日の設定においては慎重にならなければいけない部分もありますが、休日数を増やして求職者や従業員への魅力を高めていくという流れは続きます。
しかし、働き方改革を推進していくためには「生産性向上」は避けて通れません。
ビジネスモデルのブラッシュアップ、新規業態の立ち上げ、DX推進によって業務生産性の向上を図る、BPOの活用など様々な施策検討ができますが、働き手自身の生産性に対する意識も非常に重要です。
自分の時間単価はどのくらいなのか?
そのために時間当たりいくらぐらいの業務をしなければならないのか?
本日の業務の生産効果はどのくらいなのか?
それらの意識を持ち、業務に邁進しなければ会社の仕組みだけでは生産性向上が進みません。そのために、まずは生産性の見える化を行い、全従業員への意識改革を図ってはいかがでしょうか。
 | 執筆者: 人的資本経営支援本部 本部長 宮花 宙希 みやはな ひろき |